
2025年秋、本格的な修学旅行シーズンを迎えている。2024年度の修学旅行実施率は、コロナ禍前の水準に完全に戻っており、探究的な学習の浸透に伴い、受入れ地や施設でも新しいプログラムが続々と展開されている。
一方で、物価高に伴う修学旅行費用の高騰、インバウンド増加による混雑、ドライバーや旅行会社の人手不足といった課題が深刻化しており、現場は厳しい状況に直面している。持続可能な修学旅行を実現するにはどうすればよいか。先ごろ日本修学旅行協会が開催した「教育旅行シンポジウム」では、教育現場、受入地、旅行会社の担当者がそろい、今後の展望を語った。
教員と保護者の姿勢に表れた変化とは
基調講演に登壇した日本修学旅行協会理事長の竹内秀一氏は、修学旅行を取り巻く環境が年々変わっているのとの見解を示し、費用の高騰、人手不足といったすでに顕在化している課題に加え、「教員の働き方改革の影響や保護者の姿勢の変化が大きい」と指摘した。
学校現場では、働き方改革の進展により学校行事の精選・整理が進んでおり、特に修学旅行以外でも林間学校といった宿泊を伴う行事の縮減、日数の短縮が検討されている。竹内氏は「イレギュラーな業務への抵抗感が強くなっており、学年以外の教員に引率を依頼することが困難になっている」との現状を説明。教員の長時間勤務に対する安全配慮、手当てのあり方も課題とした。
費用高騰に伴う保護者への対応も重要だ。「これまで以上に費用負担に見合う教育効果が求められている。保護者の理解を得られる旅行先や活動内容とともに、合理的に説明できるようにしなければならない」(竹内氏)。
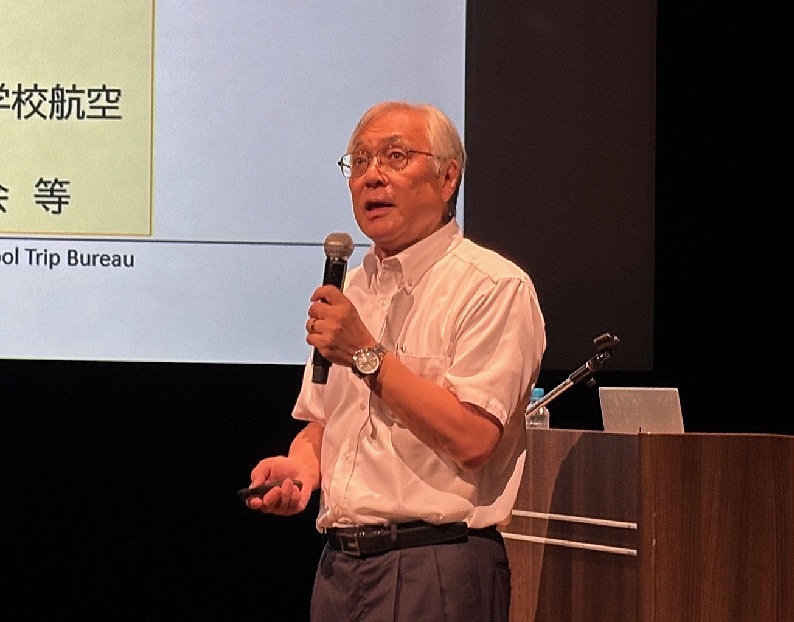 日本修学旅行協会理事長の竹内秀一氏
日本修学旅行協会理事長の竹内秀一氏
海外から国内へ、地域格差も顕著に
シンポジウムでは、教育関係者、受入地、旅行会社の担当者がそれぞれの視点で修学旅行の現況と課題を語ったうえで、「持続可能な修学旅行に向けて」をテーマとしたパネルディスカッションがおこなわれた。
教育現場からは東京都立飛鳥高等学校校長の渋谷寿朗氏と狛江市地域学校連携支援専門員の亀澤信一氏が登壇。国際理解教育と英語教育に力を入れている飛鳥高校は2002年以降、台湾、ベトナム、シンガポール、ハワイ、マレーシア、韓国、グアムと海外修学旅行を実施してきたが、費用負担の増加が大きな課題となっている。
渋谷氏は「2025年度は日程短縮、実施時期を8月から2月まで広げるなどの対応を取り入れて韓国修学旅行を計画したが、費用面で折り合わず業者の応札がなかった」と述べ、2025年度、2026年度は沖縄を目的地としたことを明らかにした。前向きにとらえ、沖縄ならではの魅力を伝える動画を活用するなど生徒のモチベーションを高める工夫や対応を丁寧におこない混乱は生じなかったという。しかし、海外修学旅行の価値について「母語が通じない環境での経験や異文化体験が生徒の成長に重要であり、学校行事という安全・安心できる枠組みの中で国際経験させる意義は大きい」と強調した。
亀澤氏も「海外修学旅行を通じて、その後の学習や進路に大きな影響を受けたとの報告をよく受けている」と同調。課題解決には行政による経済支援も重要だと指摘した。
東京都62区市町村のうち、2024年度に修学旅行の補助を打ち出していたのは、全体の55%にあたる34自治体。地域差が顕著だ。具体的には、港区が全区立中学校3年生を対象に海外修学旅行を実施し、保護者負担は7万円に抑えて、それ以外の費用は公費で負担した。こうしたケースを紹介したうえで、亀澤氏は「家庭環境や地域によって学校外での体験活動の機会に差が生じる『体験格差』」を少しでも解消するため、すべての子どもたちが参加できる環境を整え、一人ひとりにとって充実した修学旅行になるべきだ」と語った。
 パネルディスカッションの様子
パネルディスカッションの様子
時間分散、小規模校などへの対応
受入れ地にも変化が起きている。北海道観光機構事業企画本部プロモーション部担当部長の長野博樹氏は、北海道への修学旅行の傾向について、「これまで周遊型が中心だったが、近年は滞在型にすることで貸切バスの利用をできるだけ減らす状況が顕著」と報告。その変化の要因として費用高騰の影響をあげ、一例として函館で2連泊する3日間の日程で、2日目は終日班別行動するスタイルが主流になっていると説明した。
また一部では、コロナ禍で負債を抱えた宿泊施設が観光消費額の大きいインバウンド客を選択するケースもあると現状もある。「背景に根本的な問題を抱えているのも事実だが、閑散期の促進、たとえば函館山のように混雑する観光地の訪問時間帯の分散など、道内の施設と連携する必要がある。探究にふさわしいコンテンツ開発を進め、オーダーメイドで応えられる体制にしていきたい」などと展望を語った。
旅行会社も、リソースやネットワークを活かして環境変化への対応に尽力している。JTB福島支店(いわき店)の佐藤しおり氏は、「都市部から離れた地域や人口減少地域に位置する学校は、旅行会社として十分に営業活動ができず、入札時期が集中する場合には依頼を断らざるを得ない場面がある」と厳しい現状を説明。飛鳥高校の渋谷氏が言及した物価高に伴う費用高騰以外にも、地域格差で修学旅行の実現がままならない状況が発生していることを明らかにした。
実際、佐藤氏も自身の営業エリアの公立中学校の校長から「どのようにしたら、旅行会社は我々のような小規模学校でも修学旅行の企画をしてもらえますか?」という切実な相談を受けた経験がある。
事前準備の打ち合わせをオンラインで実施し、オーダーメイドでありつつモデルプランに最小限のアレンジを加えていくJTBの新サービス「らくらくオーダー修学旅行」の取り組みなども紹介したうえで、佐藤氏は「小規模校の合同実施、自治体との連携による支援などを含めて、単なる手配・準備にとどまらず、子どもたちが主役になるために何ができるか。担当者としての熱意をもって考えつづけたい」と力を込めた。
子どもたちにとって、かけがえのない体験、学びの場である修学旅行。環境変化に左右されず、 円滑かつ持続可能な教育活動として実施するため、さまざまな角度から模索が続いている。
 トラベルボイス | 観光産業ニュース 読者数 No.1
トラベルボイス | 観光産業ニュース 読者数 No.1