
ジャーナリストの坂元隆です。新聞記者出身で今春まで旅行会社の経営に携わってきました。
観光産業にとって異業種企業の参入は珍しいことではありません。私が在籍していた旅行会社は新聞社の子会社ですし、デパートやスーパー、物流企業、印刷会社なども旅行・観光部門を法人化しています。
ただ、ここ数年の異業種企業の参入は、これまでとは質的に違うような気がします。コロナ禍によって決定的になった観光の質的な変化に業界内の企業が十分応えられないうちに、それらの異業種企業がデジタルやインフラといった自らの得意技を駆使して、観光のあり方そのものを変えていこうとしているからです。
ゼロから観光産業に参入する異業種企業の奮闘ぶりを垣間見ることは、観光産業の可能性を展望することにもなりそうです。
「従来型の観光ではなく、地域の文化や自然、食などを新たな観光の価値に変えて、世界をびっくりさせたい」
観光の未来について真っ向から夢を語る人に久しぶりに会いました。NECの子会社、NECソリューションイノベータの川村武人ディレクターです。
川村さんの手掛けたオンライン販売システム「NEC ガイド予約支援」を導入して、北海道道東地域のバス会社など観光事業者が取り組んだ「ひがし北海道観光DX」は、今年のジャパン・ツーリズム・アワードの経済産業大臣賞を受賞しました。今回は、川村さんが観光事業者とタッグを組んで、大臣賞を受賞するまでの奮闘から、その背景にある考え方を取材しました。
川村さんは、NECグループのシステムインテグレーションにおける中核会社のイノベーションラボラトリという部署で観光分野の事業の立ち上げにゼロから取り組み、経済産業大臣賞を受賞する事業まで育て上げた人物です。社内における観光分野の位置づけを確立するまでは相当な苦労があったようです。
「ひがし北海道観光DX」プロジェクトとは?
「NEC ガイド予約支援」は、タビナカの観光商品をオンラインで販売するシステムです。システムを導入した観光業者は、売上の5%をNECソリューションイノベータに支払うことで、商品をウェブ上で販売し、在庫管理をすることもできます。電話やファックスに頼っていた業者にとっては業務の大幅な効率化につながります。
ただ、川村さんが地域とともに取り組んだ「ひがし北海道観光DX」が評価されたのは、システムの利便性だけではありません。コロナ禍で落ち込んだ業績をなかなか回復できずにいた道東のバス事業者や飲食店、観光施設などの事業者が連携し、観光による地域全体の経済活性化につなげたところが注目されたのです。
プロジェクトで地域の旗振り役となった阿寒バスの取締役営業本部長、西岡一麻さんによると、システム導入にあたって最初に考えたのは、阿寒バス以外の道東のバス事業者との連携だったといいます。
「観光客に、ここ(道東)はレンタカーでなければ来られない場所と思われていたので、バスでも観光できるんだということを示したかった」。
道東に限らず、全国の過疎の観光地の二次交通の問題は深刻です。路線バスも本数が多くありません。同じサイト上で各社のバスの予約や時刻表の確認ができればバスでも観光が可能になる。そう思って、網走バスや根室交通など道東の他社にも声をかけることにしたそうです。さらに、飲食店や観光施設にも参加をよびかけ、観光客がサイト上で道東観光を一元的に計画できることを目指しました。
2023年から昨年にかけて、西岡さん、システム導入を阿寒バスに勧めた、当時釧路観光コンベンション協会勤務の佐藤明彦さん、そして、川村さんらNECソリューションイノベータ担当者の3人が道東の観光関係者を一軒一軒回ってプロジェクトへの参加をよびかけました。目標は観光DXでしたが、参加を促す方法は「とてもアナログだった」と西岡さんは言います。
比較的小規模で互いに競争している飲食店の参加はハードルが高いのではないかと思われましたが、「(地域の)人口減少を目の当たりにして観光客を引っ張ってこないと事業が成り立たない」と考える経営者が多かったそうです。
地を這うような営業活動が実り、合計47事業者をNECソリューションイノベータのオンライン販売システムで結んだ、ひがし北海道観光DXが実現しました。中核となる「ひがし北海道観光ナビ」にアクセスすると運営元の阿寒バスはもとより、ほかのバス会社や飲食店、観光施設などの予約や情報、食事券などをそれぞれの販売サイトから獲得することができます。
サイトを通じた予約や受注は順調に伸びています。阿寒バスの定期観光バスの乗車人員ひとつとってみても、2021年から2024年までの5倍近くになりました。
 ツーリズムEXPOでの授賞式の様子。写真中央が西岡氏
ツーリズムEXPOでの授賞式の様子。写真中央が西岡氏
成功の理由とNECソリューションイノベータの役割
ひがし北海道観光DXが成功した最大の理由は、参加する個々の事業者が主体性を持って、自らの利益だけに固執せず、地域全体の活性化が自らの利益につながると納得して取り組んだことでしょう。
食事券をオンライン販売している「釧路炉ばた学会」は釧路地区の炉端焼き店12店などの集まりです。過疎化が進む中で事業を継続していくには地域として炉端焼きを観光コンテンツ化して観光客を呼び込んでいくしかないと競争相手同士が手を組みました。
阿寒バスの西岡さんは「(参加事業者から)手数料をもらおうというような考えは、最初からなかった。地域にたくさんの人に来ていただいて、その中でバスにも乗ってもらえればいいという考え方でスタートした」と言います。コロナ禍で需要がほぼ消滅するという厳しい経験をしたからこそ、業種の壁を越えて観光を盛り上げようという決意が道東の関係者の間に浸透したのではないでしょうか。
地域の活性化を最優先するという考え方は、NECソリューションイノベータの考えでもあります。川村さんは「我々は地域に寄り添い、観光業に伴走し続ける」と断言します。異業種出身の人だからこそ言える言葉かもしれません。
そして、その強みの背景には生成AIの活躍がありました。「ひがし北海道観光ナビ」には、道東をめぐるたくさんのモデルコースが掲載されていますが、コースの大半が生成AIによってつくられているそうです。旅程を見ると、旅行会社の企画担当者が作ったパッケージの旅行商品と見まごうような出来栄えです。システム会社のNECソリューションイノベータならではの強みを発揮しているわけです。旅行企画のノウハウのない事業者でも各自の観光素材を持ち寄れば、AIがモデルコースを作ってくれ、多言語でデジタル販売してくれる。旅行会社やOTAの力を借りなくても、タビナカについては地域が自力で観光商品を世界中に販売できる。地域観光DXのお手本だと思います。
NECソリューションイノベータが考える「新しい観光」とは?
「ものすごく儲かるわけではないけれど、皆が少しずつ持続的に儲けていくというのが、我々が考えるツーリズム、新しい観光なんです」と川村さんは言います。地域が主体的に新たな観光商品を発掘して提供していくことにより、全国の特定地域に人気が集中するのを回避でき、オーバーツーリズムの解決策にもなると考えています。分散型でサステナブルな観光こそ、川村さんの目指す「新しい観光」なのです。全国に営業展開する従来型の旅行会社では、ともすれば地域そのものより自社の利益を優先して、「売れるもの」をとにかく売るという傾向に陥りがちです。昔ながらのやり方に固執する関係者には、川村さんの考え方は耳の痛い話かもしれません。
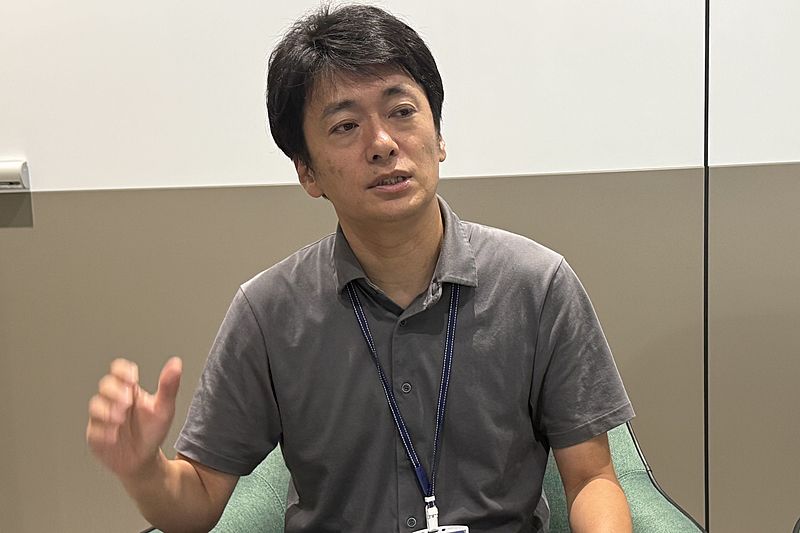 NECソリューションイノベータの川村武人ディレクター
NECソリューションイノベータの川村武人ディレクター
「新しい観光」はすでに地域的な広がりを見せています。NECソリューションイノベータのオンライン販売システムを導入している地域は300近くにのぼります。茨城県大洗町では、地元のヨガ教室が観光客向けにビーチでのワークショップを開くなど、これまでになかった観光素材を掘り起こし、地域全体のブランディングに役立てようとしています。
ひがし北海道のような地域を全国で30から50くらい作り出すのが当面の目標です。さらにAIとこれまでに蓄積したデータを活用して、高付加価値の富裕層向け商品を作り出すなど、観光商品の幅を広げていきたいと、川村さんは話しています。
もちろん、「新しい観光」の前途は容易ではありません。最後に、2つの課題を指摘しておきたいと思います。一つは、観光産業の既存のプレーヤーとの関係です。ひがし北海道観光DXで扱っているのは、2次交通と飲食店、観光施設などのタビナカ商品で、宿泊施設や1次交通は扱っていませんが、旅行体験はそれら全部の要素の集合体です。川村さんは、今後プロジェクトを北海道全体に広げていく構想を持っていますが、プロジェクトが大規模に成長すればするほど、旅行会社やOTA、航空会社やJRなどとの有機的な関係を構築していくことは必須と思います。
もう一つは、地域観光DXをリードするのはだれか、という点です。ひがし北海道の場合は、阿寒バスのような地域全体の共存共栄を図る旗振り役に恵まれました。そして、川村さんら地域外のパートナーが黒子役としてDXの土台を作り、地域の動きを支えたのです。しかし、ほかの地域でも同じように行くとは限りません。自分だけの利益にこだわらず地域を引っ張っていく地元のリーダーを地域ごとに見つけられるかが今後の展開の鍵を握るのではないでしょうか。

坂元隆(さかもと たかし)
ジャーナリスト。1983年、読売新聞社入社。国際報道担当記者としてニューデリーやワシントンに駐在、アフガニスタン内戦や米同時テロなどを取材。国際部長、編集局次長、論説副委員長などを経て、2014年読売旅行に。代表取締役社長、同会長などを務め、2025年6月に退任後、フリージャーナリストとして観光産業を中心に取材している。
 トラベルボイス | 観光産業ニュース 読者数 No.1
トラベルボイス | 観光産業ニュース 読者数 No.1