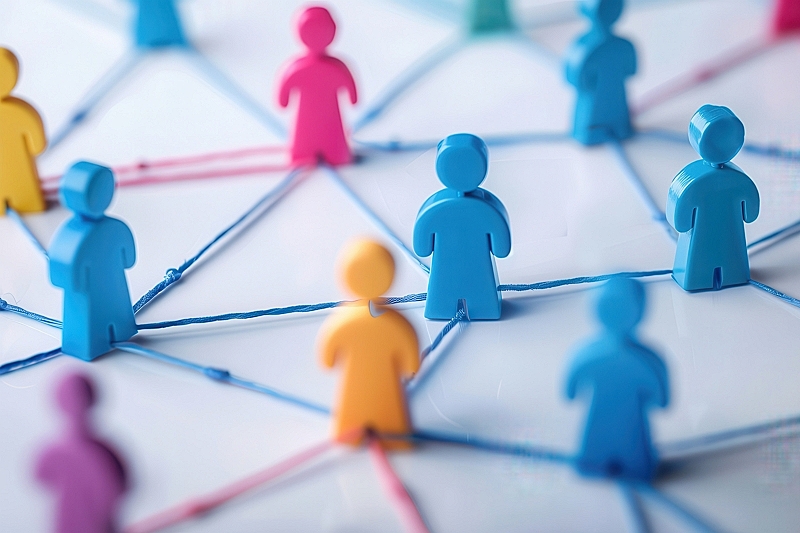
日本観光振興協会は、先ごろ「DMO観光地域づくりセミナー」を開催した。世界の観光最新トレンドの講演では、旅行・観光コンサルティング企業のネクストファクター社のカサンドラ・マッカリーCEOが世界のDMOの最新動向を調査した「フューチャーズ・スタディ2023」の結果を説明。日本と世界のDMO動向の違いと共通点を明らかにした。
ネクストファクター社は、世界最大の地域観光組織の協会「デスティネーションズ・インターナショナル(DI)」とのライセンス契約によって、観光地域診断ツール「DestinationNEXT」を開発。「フューチャーズ・スタディ」は、2014年から実施され、2023年は4回目。世界62カ国・837団体が参加した。日本からも40団体が参加している。
世界も日本もトップトレンドは「AI」
まず、マッカリー氏は、調査結果からDMOのトップトレンドを解説。世界でトップトレンドとなったのは、「人工知能(AI)は、加速度的に普及していく」で前回調査から84ポイントも増えた。
2位は「顧客は、他では味わえない本物の旅行体験をますます求めるようになってきている」、3位は「コミュニティは、地域住民と旅行者のためにデスティネーション、商品、体験の開発にもっと関与することを期待されている」。このほか、「住民感情は、重要な測定項目になりつつある」(6位)や「旅行業界の各種部門では、労働力およびスキル不足を感じることが多くなっている」(7位)も大きく順位を上げた。
一方、日本でのトレンドトップは、同じく「AI」。マッカリー氏は、2位に「あらゆる立場の旅行者に配慮し、アクセシビリティの向上に力を入れている」が入っているのが特徴とした。3位は「一般の人々のコンテンツ制作と発信が、デスティネーションのブランドと体験を活性化している」(世界では11位)、4位は「本物の体験」、5位は「産業界、地域社会、行政の連携強化が、デスティネーションの競争力とブランドを高める」(世界では5位)。
マッカリー氏によると、世界的にDMOは積極的にAIの活用を始めている。多くのDMOが取り入れているのが公式サイトでのチャットボット。このほか、年間250万人が訪れるカナダのジャスパーのAIガイド導入の事例では、ビジターセンターのスタッフを減らすとともに、効率的なガイドを実現していると話した。
戦略として重視される「住民感情の改善」
そうしたトレンドを踏まえたうえで、DMOが進める戦略についても調査。世界、日本ともトップとなったのは「現在の資金レベルを維持するため、財源を確保する」となった。マッカリー氏は「どのように財源を多様化し、収入を上げていくか。多くのDMOが注力している」と説明。その背景として、パンデミックの期間、資金調達が困難になったことを挙げた。
また、世界で新たに重視されている戦略の一つとして、マッカリー氏は「住民の感情を改善し、観光経済への支持を高める 」(15位)を挙げ、「どのように地域と関係を築いて、地域を手助けすることが重要との認識が高まっている」とした。
日本でも同様に、「観光経済の課題に対処する為に、地域社会との関係を強化する」が13ポイント増加の5位、「地域社会の発展と促進を支援する取り組みを拡大する」が29ポイント増の10位に入り、大きく順位を上げた。
未来のDMOの役割とは
調査では、DMOの役割について、現在と未来とを比較。世界では、現在も未来も「デスティネーションマーケティング」が最も重要な役割となった。今後、重要になってくる役割としては、「データ調査とビジネスインテリジェンス」が5位から2位に、「デスティネーションおよび商品の開発」が6位から4位に上昇した。
日本のDMOを見ると、現在の役割として「デスティネーションマーケティング」「コミュニティとの関係」「ブランドマネージメント」のトップ3は世界と変わらず。一方で、「国際会議セールス」については、世界が10位に対して、日本は18位と役割の差が大きくなった。
DMOの役割の中で、マッカリー氏は「観光業界のアドボカシー活動」(世界7位、日本12位)について言及。アドボカシー(Advocacy)とは、政治的、経済的、社会的なシステムや制度における決定に影響を与えることを目的とした活動や運動のこと。マッカリー氏自身も、DMOでのキャリアの中で、アドボカシーに注力してきたという。
マッカリー氏は、「DMOには、業界の地位を高めていくためには、パートナーが必要。アドボカシーとは支援者を募るという意味がある」としたうえで、「政府や自治体に対して、観光の重要性やDMOの役割がどれほど重要かを戦略的かつ長期的に唱えていく必要がある」と強調した。
また、「人材育成」」(世界17位、日本11位)についても触れ、「世界では、人材開発がどんどん高度化している」と説明した。例えば、米国メンフィスでは、DMOがホスピタリティ専門の学校を運営し、カナダ・カルガリーではオンライン教育を充実。また、カナダ・バンクーバーでは、観光事業に関心のある人に市内のアトラクションに参加できるパスポートを発行することで、利用を促進するとともに、その情報をアドボカシーしてもらう取り組み進めているという。
現在のDMOのKPIについては、世界と日本とで違いが見られた。世界、日本とも「観光の経済的影響」がトップだったが、2位は世界が「宿泊来訪者数」、日本が「宿泊稼働率」、3位は世界が「スタークホルダーの支持とビジネス開発」、日本が「来訪者の満足度」。また、「住民感情」では世界は13位だが、日本は5位と重視傾向となった。
将来の日本のKPIを見ると、「来訪者の満足度」が1位に、「会員/パートナーの満足度」が4位に、「スタークホルダーの支持とビジネス開発」が6位に、「コミュニティの利益と社会的影響」が7位に、それぞれ上昇しているのが特徴となった。
DMOは地域の経済開発の役割も
フューチャースタディでは、未来のDMOに向けた取り組みも提示。需要サイドでは、旅行者のエンゲージメントとパートナーの支援、供給サイドではデスティネーション開発とコミュニティの連携を挙げた。
マッカリー氏は、4つの取り組みのサイクルを回していくうえで、ガバナンス、テクノロジー、専門家の育成、資金調達の重要性を指摘。「ステークホルダーやコミュニティと関わる中、またテクノロジーの活用を考えていく上でも、チームをプロとして育成していく専門家の育成は欠かせない」と話した。また、資金調達では「資金の多様化と分散」の必要性を唱えた。
そのうえで、DMOが目指す姿として、訪れてよし、住んでよし、働いてよし、投資してよしの「四方よし」を地域社会の活性化サイクルとして挙げた。訪れたい場所をつくれば、住みたくなる場所になる。住みたくなる場所ができれば、働きたい場所になる。働きたい場所ができれば、企業や住民が投資したい場所になる。投資したい場所になれば、訪れたい場所にできる。
マッカリー氏は、「DMOは目先の仕事に注目しがちだが、もう少し広い視点で見ることが必要。DMOが行っている仕事は、より広いインパクトを持っている」と強調。観光産業は経済発展には欠かせないことから、DMOは地域の経済開発の役割も担っていると強調した。
 トラベルボイス | 観光産業ニュース 読者数 No.1
トラベルボイス | 観光産業ニュース 読者数 No.1