
東京観光財団は、「観光活性化フォーラムTOKYO2025」を開催した。同財団は地域の特色を生かした魅力ある観光施策を支援。各地域での観光施策の参考にしてもらう目的で、今回は基調講演にスタートアップファクトリー代表の鈴木おさむ氏を招いたほか、施策の事例として、八王子観光コンベンション協会および岐阜県の長良川リトリートによる取り組みが紹介された。
鈴木氏、「目線を変える」「結局は体験が一番強い」
鈴木氏は「ヒットメーカーと考える観光活性化のヒント」をテーマに講演。鈴木氏は、数々の人気テレビ番組を手がけてきたが、2024年3月いっぱいで放送作家・脚本業を引退。現在はTOC向けファンド「スタートアップファクトリー」を立ち上げ、その代表を務めている。
鈴木氏は、これまで携わったバラエティ番組や個人的体験から、効果的な観光プロモーションに繋がるヒントを紹介した。
まず、例に挙げたのが1996年4月に開始された人気番組「SMAP×SMAP」。鈴木氏は、「SMAPという新しい器に、それまで芸人などがやってきたことを載せることで、新しいメニューになると考えた」という。「人が今まで見たことのないものを見せようとすると、視聴者は、それに驚いたり嫌悪感を覚えたりする。根本から新しいことを考えようとしすぎて、それがなかなか視聴者に届かないことがある」と話したうえで、「たとえば、器を変えることで、それに乗るマグロがカルパッチョに見えるような見せ方をやってきた」と振り返った。
また、器と同様に目線を変えることの大切さも主張。伊勢神宮によくお参りに行く鈴木氏は、最近若い女性の参拝者が増えたと感じている。その理由を「明確にテレビの力」として、スピリチュアルブームが起きて、新たに「パワースポットという言葉が生まれたことで、それまで年配の文化だったお伊勢参りがヤングカルチャーとなった」と指摘した。
さらに、テレビ番組制作にあたっては、「自分たちが届けている情報が新しいかどうか、視聴者が見たいと思ってるかどうかを考えることは非常に大事なこと」と話した。たとえば、『お願いランキング』では、ランキング下位の商品を紹介することで、ランキング上位の商品の売上が増加したと紹介し、「マイナスのことを伝えたからこそ、プラスのことが引き立ち、それが新しい情報、知りたい情報になった」と解説した。
目線を変えるという文脈では、東日本大震災からの復興プロジェクトとして、福島県田村市にある「ムシムシランド」での取り組みにも触れた。それまで人気昆虫を中心に展示を行ってきたが、鈴木氏の監修で、2018年夏に「世界三大奇蟲展」を開催。自治体や地元の学生の協力も得て、「気持ち悪い虫だけれど、子供達がワクワクしそうだ」という考えから、実施したところ、開催期間だけで1万人以上が来場したという。
翌年には、投票によってカブトムシ・クワガタ界のNo.1を決める「世界のカブクワ総選挙」を実施。それぞれのカブトムシやクワガタの選挙ポスターも作成した。鈴木氏は「ランキングにすることで、子どもたちの参加性が高まり、何回も訪れる子どもたちも現れた」と明かした。
「ウェブ3.0とか言われているが、結局は体験が一番強い。しかし、貴重な時間やお金を費やすことになるので、みんな他でやったことない体験がしたい」と鈴木氏。石垣島への家族旅行で参加した危険生物ツアーに感銘を受けことを紹介し、「石垣島にサソリがいるという情報は、このツアーに参加して初めて知った。一般的な観光情報では出てこない。知りたい情報が届いていなかった」と振り返った。
そのうえで、「旅の基本は、訪れた人にワクワク、ドキドキさせること。観光地が売りたいとPRするものと僕たちが面白いと思うものは結構違う。そこに対して冷静な目を持つことは観光においてとても大事なこと」と強調した。
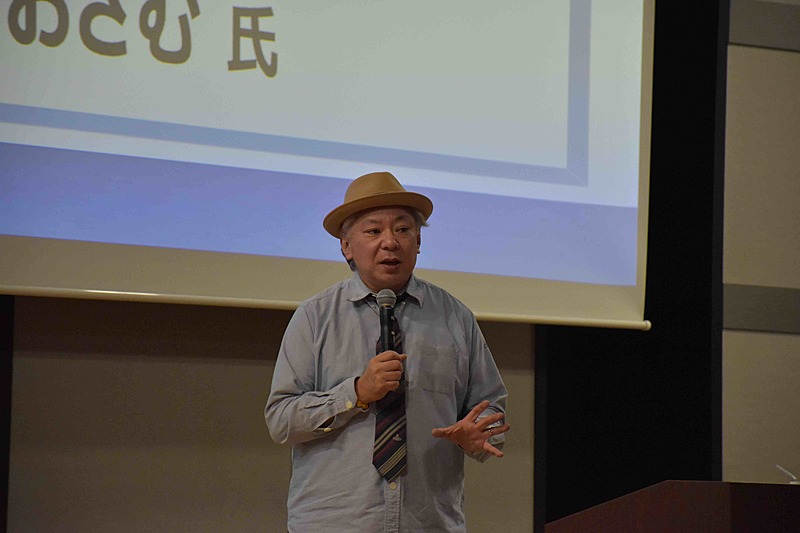 「結局は体験が一番強い」と鈴木氏
「結局は体験が一番強い」と鈴木氏
東京・八王子、日本遺産ストーリーで高尾山をブランディング
八王子観光コンベンション協会は、「東京観光財団の助成を活用した持続可能な高尾観光まちづくり」について報告。2020年に「霊気満山 高尾山~人々の祈りが紡ぐ桑都物語~」のストーリーで認定された日本遺産を中心としたプロモーションを展開していると説明した。
助成事業では、まずマーケティング調査を実施し課題を抽出した。消費が期待できないレクリエーション客が7割を占め、観光消費単価は3000円~3700円と低く、8割がリピーターで50代以上が5割。11月と2月の繁閑差が大きく、来訪者の日本遺産についての認知度は低いという課題が浮かび上がったという。
その解決策として、高尾山ブランディングの確立を目指し、2023年度から循環型商品の開発とウェルネスツーリズムの2本柱を推進。BtoCおよびBtoB向けに情報発信を始めた。2024年度からは、ブランド戦略の策定に着手。利用の平準化、消費単価の向上、誘客の多角化、持続可能性の向上の課題解決に向けて、20~30代をターゲットに設定した。
そのうえで、地元でのワークショップを通じて、ブランドコンセプトを「都心から近く、誰でも、何度でも、心を潤すことができる特別な場所」に決定。ブランディング強化に向けて、ロゴ、ポスター、動画、ブランディングツールなどを制作し、プロモーション素材として活用を始めた。
一方、循環型商品の開発では、高尾山応援基金を創設し、商品の売上の一部が還元され、高尾山の自然保護に繋がる「循環」を進めるほか、サステナブルな素材や廃材活用の「循環」、将来に向けて販売が継続できる世代間の「循環」を念頭に置く。
ウェルネスツーリズムでは、高尾山での健康プログラムを造成。企業向けコース、インバウンドを含めた個人向けにコースの開発を進めていく。
今後については、ブランディングの浸透、循環型商品の定番化、日本遺産を活用した来訪者の平準化を推進していくとともに、国際的なサステナビリティ認証「グリーンデスティネーション認証」の取得を目指す。
 八王子観光コンベンション協会
八王子観光コンベンション協会
岐阜県・長良川、日本を代表するサステナブル観光を
岐阜県の長良川リトリートは、「長良川リトリートが目指す、取り戻したい持続可能な懐かしい未来づくり」に向けた取り組みを説明した。岐阜県には、ユネスコ世界遺産の「白川郷・五箇山の合掌造り集落」など多彩な観光素材があるが、長良川リトリートは、独自の文化が根付いている長良川流域を「清流の国」として「日本を代表とするサステナブルツーリズムのメッカにする」ことを目指している。
その目標に向けて、宿泊滞在を促す観光コンテンツの造成、宿泊施設との連携、エリア・プランディングの構築を進めている。
観光コンテンツでは、鵜飼など長良川の伝統文化体験、E-bikeやウォーキングなどエコアクティビティ、ヘルスケアプログラム、養蜂など環境・文化体験、薬草や和綿を用いたオーガニック体験、健康食体験などの造成に注力。地場産業の和綿については、リブランディングによる新たな商品開発を進め、保存・継承にも繋げていく。
このほか、地域連携の強化に向けてデジタル技術やデータの活用も積極的に行っていく方針。全ての事業をウェブサイトでリンクし、効率的なプロモーションを展開していくほか、着地型ツアーの販売では、主要OTAとの連携でワンストップ予約を進めていく。また、デジタルマーケティングを導入し、施策のアップグレードも推進していく。
さらに、体験プログラムから個人のヘルスデータを取得し、パーソナライズされたヘルスケア観光商品の開発も検討していく考えだ。
今後は、岐阜県の強みを再認識し、今の時代に合った観光を展開。「懐かしい未来のために」をタグラインに、ターゲットを富裕層に絞ったアプローチで稼げる地域づくりを目指していく。
 長良川リトリート
長良川リトリート






















 観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】
観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】








