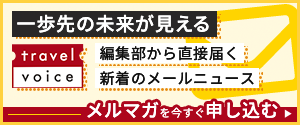日本全国のスキー場をひとつのパスでホッピング。そんなサブスクサービスが2021年10月にスタートした。立ち上げたのはスタートアップの「Pionnerwork (パイオニアワーク)」。プラットフォームは「Earth Hopper (アースホッパー)」と名付けた。SNSでバズったこともあり、サービス開始から約半年で当初想定を上回るユーザーの獲得に成功した。
「自然のフィールドでの遊びにはツーリズムの要素がある。それをアーススポーツとしてカテゴライズしていきたい」。そう話す同社社長の後藤陽一氏に、アースホッパー立ち上げの背景や描く未来図を聞いてきた。
日本にも欧米のようなスキー場の共通パスを
後藤氏がアースホッパーを着想したのは2018年頃のことだ。「なぜ、日本には欧米の『Epic Pass(エピックパス)』のようなものがないのだろうか」。エピックパスとは、米国、カナダ、欧州、オーストラリアなど8カ国66の山岳リゾートでスキーが楽しめる国際的な共通パスのこと。日本でも長野県の白馬バレーが参加。このパスを持っているスキーヤーは、白馬バレーで連続5日間無料で滑ることができる。
また、後藤氏は、日本の上質な雪に観光コンテンツとしての可能性も感じていたという。特に、2022年の北京冬季五輪を契機にウィンタースポーツ熱が高まっている中国は、日本のスキー場にとって大きなマーケットになるのではないかという目論みがあった。
2021年春に、まず9ヶ所のスキー場で春シーズンだけ使える2万円の共通パスを発行して、実証を行った。その結果、利用者はシーズン中に20回以上滑るヘビーユーザーのみで、ライトからミドルユーザーは取り込めず、偏りが見られた。そのことから、本格的なサービスローンチに向けては、ワンシーズン中に1ヶ所のスキー場で上限2回だけという条件をつけた。一方で、リフト券だけでなく、スキー・スノーボードレンタルも一部スキー場で利用可能とした。
正式なサービスは30ヶ所のスキー場でスタートした。そのうち半数ほどは後藤氏のネットワークで獲得したものだ。全国さまざまなスキー場に、参画のための営業をかけたが、半分ほどは断られたという。「新規客はいらないという反応もあったし、サブスクは単価が下がってしまうので、そこまでして集客することに疑問を感じるスキー場もあった」と明かす。
それでも、SNSでバズったこともあり、ローンチ後半年で当初想定を上回るユーザーを集めることに成功する。しかし、やはりヘビーユーザーが中心。気軽にウィンタースポーツを楽しむ層の取り込みに課題を残している。また、現在のところ関西のスキー場の加入が少なく、ユーザーが東京に偏りすぎている点も今後改善していく余地があるとの認識だ。
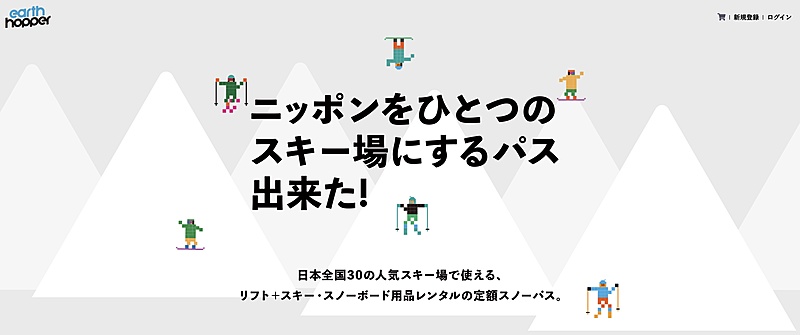 アースホッパーのサイトよりフリーライドスキー国際大会の日本誘致に奔走
アースホッパーのサイトよりフリーライドスキー国際大会の日本誘致に奔走
後藤氏のビジネスとしてのウィンタースポーツとの関わりは、大手広告代理店・電通時代に遡る。新規事業に携わるなかで、バックカントリースキーに興味を持ち始め、特にフリーライドと呼ばれる競技にハマった。
「この大会を白馬に誘致したら面白いのではないか」。大会を主催する「フリーライド・ワールド・ツアー(FWT)」の本部が、後藤氏が留学していたスイス・ローザンヌにある縁もあり、電通のなかで日本誘致のプロジェクトを進めることになる。「趣味と仕事が合致した」と後藤氏。2014年9月のことだ。
現在でもそうだが、当時も、日本では指定コース外で滑るバックカントリースキーは賛否両論があり、基本的に認めていないスキー場が圧倒的に多い。後藤氏は、大会誘致や普及にあたって「運営会社との調整はとても大変だった」と振り返る。
後藤氏によると、欧州ではスキー場を守る法律が整備されているという。F1レーサーのミハエル・シューマッハが2013年にフランスのスキー場で深刻な事故を起こしたときも、この法律によってスキー場は多額の賠償を避けることができた。一方、日本にはそういう法律はない。コロナ前はパウダースノーを求めて多くの外国人が日本のスキー場を訪れていたが、バックカントリーで不測の事態が発生しても、スキー場の免責を保証する法的土台がないため、日本ではバックカントリースキーが普及しない。
後藤氏は「これは、スキーだけでなく、アドベンチャーツーリズム全体に言えること」と話す。
後藤氏は、スキー場に理解を求めるだけでなく、パトロール・マネージメントや緊急時の対処法などの研修のために、スキーパトロールのスタッフを本場スイスに派遣するなど、実務的な啓蒙にも努めてきた。その結果、白馬八方尾根には数カ所の「フリーライドゾーン」が設けられ、多くの外国人が多く訪れるようになった。
2018年2月に電通を退社。日本のFWT運営事務局として「FWTジャパン」を設立し、独立した。今年3月もFWTのワールドツアーとして「TOYO TIRES FREERIDE HAKUBA 2022」を開催した。後藤氏は「アースホッパー立ち上げでも、FWTとしての活動で築いたスキー場とのネットワークが生きた」と明かす。
 後藤氏は、ローザンヌの大学でスポーツビジネスを学んだ。事業拡大に向けてさまざまな可能性にチャレンジ
後藤氏は、ローザンヌの大学でスポーツビジネスを学んだ。事業拡大に向けてさまざまな可能性にチャレンジ
アースホッパーは、将来の事業拡大に向けた未来図も描く。
例えば、サブスクサービスとの親和性が高い他事業者との連携。「カーシェア、宿泊、多拠点生活などとも何か一緒にできるのではないか」と後藤氏。さらに、地域活性化の視点から、DMOとの連携も視野に入れる。「地域の観光施設にもQRコードを置いて、データを取得できれば、スキーヤーの行動が可視化できる」と目論む。
すでにアースホッパーに加入しているスキー場にはQRコードを設置し、ユーザーの利用動向のデータを取得。スキー場と共有しているが、その仕組みを地域の観光にも広げていく可能性を模索している。
さらに、国内のスキー人口が減少しているなか、インバウンドの復活に向けて中国市場に注目している。「中国のスキー場もアースホッパーに加えたい。中国人スキーヤーが中国国内でもアースホッパーが使えれば、日本のスキー場への誘客にもつながる」と話し、中国から日本へのスキーヤーの流れを創り出すことに意欲を示す。
中国、台湾、香港からのスキー目的での訪日は年間60万人ほどだと見られている。「日本のヘビースキーヤーの目的はスキーだけだが、訪日客は旅という視点から地方のいろいろなスキー場に行ってみたいと思うのでは」。定額制は、分散化を促すきっかけになる可能性があるとの考えだ。
「アーススポーツ」としてのプラットフォームに
アースホッパーはサブスクサービスのプラットフォーム。スキー場の共通パスだけにこだわっているわけではない。後藤氏は「自然のフィールドでの遊びにはツーリズムの要素がある。そういうものを『アーススポーツ』としてカテゴライズしていくことにトライして行きたい」と話す。今シーズンからは、キャンプやマウンテンバイクなどグリーンシーズンのコンテンツを加えていくことも考えているという。
「自然の中で体を動かす楽しみを繰り返していくと、自分が進化していくことを感じられる。それがスポーツの醍醐味。成長を感じることができれば、リピーターも増えてくる。アースホッパーをその入口にしていきたい」。アースホッパーを運営するパイオニアワークの事業コンセプトは、「自然の中でスポーツをするライフスタイルを作っていくこと」だ。
自然の中で遊ぶ。「その遊び方を知っている人たちの知識やスキルに注目すれば、新しいマーケットが広がる。そういう人たちが、旅行業界のヒエラルキーの中で上層に位置づけられ、稼げるようになれば、日本の隠れた資産が輝くようになる」。
FWTの社長が白馬を訪れた時、「これは世界の知らない宝石だ」と感嘆したという。そうした宝石は日本の自然の中にまだまだある。自然の中で遊ぶ「アーススポーツ」は定着するか。アースホッパーの挑戦は続く。
聞き手:トラベルボイス編集部 山岡薫
記事:トラベルジャーナリスト 山田友樹























 観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】
観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】