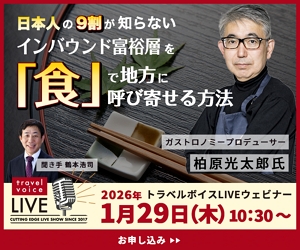経済産業省の商務・サービスグループ文化創造産業課では、日本各地の伝統的な祭りを体験型の観光コンテンツとして磨き上げ、地域活性化につなげるための実証調査に乗り出した。今秋、訪日旅行者や祭事開催者から集めた声をまとめて公表する予定だ。
ターゲット客層には、すでにゴールデンルートは訪れたことがあり、伝統的な暮らしや歴史に関心が高い訪日リピーター層を想定。2025年5月には第一回目の有識者会議を開き、ここでの議論をもとに、旅行者アンケートや祭りの開催者へのヒアリングを実施した。さらに10月には、訪日客が小豆島で祭りの準備から打ち上げまで参加する4日間のモニターツアーを実施。参加する側と開催する側、双方からフィードバックを集める。その狙いと今後について、同課調査官、古山貴規氏に話を聞いた。
「祭り」を軸に、全国各地へインバウンド誘致
経済産業省文化創造産業課が担当する領域は、アニメやゲーム、ファッションなど感性に基づく無形資産価値を海外向けにアピールし、貿易黒字を拡大するための政策作りや法整備。その中で、地域活性化につながるエンターテイメント系コンテンツの掘り起こしを担当している古山貴規氏は、昨秋から「地域伝統芸能などを活用した行事のインバウンド向けコンテンツ展開に関する実証調査」に取り組んでいる。
古山氏は、「祭りは、地域が誇る文化資源の一つ。これを基軸に据えることで、まだあまり知られていない全国各地へ、もっと訪日インバウンド旅行者を誘致できないかと考えた。また、祭りを『観る』ものから『参加する』ものに変えることで、訪れる人の滞在期間を伸ばし、地域に新たな利益を生み出し、地域の伝統文化産業の活性化へとつなげる方法についても検証していく」と説明する。少子化や人口減少により、祭りの維持・継承が年々、難しくなっている状況を解決する一助にもなるとの考えだ。
祭りによる地方創生という仮説を検証すると同時に、祭りを開催する側と訪れる旅行者、双方にとってメリットがあり、持続可能な形とするためには何が必要かを探ることが、今回の実証調査の目的だ。
海外の調査対象マーケットには、台湾、香港、タイを選んだ。「初めての来日では、やはりゴールデンルートを回りたいと思うので、地方への誘客はリピーターが主な対象になる。そこで訪日リピーターの多いアジアの3市場の旅行者を対象に、日本の祭りへの関心度、参加したいと思う金額などをアンケート調査し、どんなニーズがあるかを探った」(同氏)。
同様に、国内の関東および関西在住者向けにも、地方の祭りへの参加に関する意識調査を実施。国内外合わせて、計2000人からの回答を集めた。
一方、祭りの主催者向けのヒアリング調査は、モニターツアーを受け入れる小豆島を含む全国計9か所を対象に実施。祭りを継続していくための課題や、神社の氏子ではない人が担い手として参加することへの抵抗感などを聞いた。いずれも調査は完了しており、回答内容の分析をおこなっている。
経済産業省の商務・サービスグループ文化創造産業課 古山貴規氏
「祭りの準備」からの参加にこだわる理由
日本の祭りに詳しい関係団体、神社の神主、経済学や観光学、アドベンチャーツーリズムなど様々な領域の専門家が参加した第一回目の有識者会議では、「お祭り騒ぎを楽しむだけでは困る。ご祈祷など、神事の部分は絶対にないがしろにしないでほしい」といった意見や、「国が推進する男女平等やダイバーシティとぶつかる部分があっても、祭りについては、歴史伝統を最優先するべき」との声など、様々な議論があった。「要は、観光客向けの作り物ではなく、昔からの地域の祭りの姿を届けたいというのが一致した見解だった」と古山氏は説明する。
神輿をかつぐ、山車を引く、盆踊り、火を燃やすなど、祭りのタイプごとに、受け入れ可能なキャパシティ、注意事項や参加料の設定方法などが異なることも想定している。こうした議論に役立てるため、今年10月には、小豆島の祭り「秋祭り太鼓台奉納」に外国人旅行者が参加する第一回モニターツアーを実施。本番前の「宵祭り」から当日の祭り、終了後の「直会(終了後の打ち上げ)」までを体験してもらう内容だ。続く来年度も、各地で複数のモニターツアーを実施したい考え。
古山氏は、祭りの当日だけでなく、準備段階から参加する体験が最も理想的な形だと説く。なぜなら「祭りの本質は、準備にあるからだ。祭りのために、数か月前からみんなで準備をするなかで、コミュニティが形成されていく。祭りが終わった後も、そのコミュニティは残る」。地域と訪れた人との関係性が深まることで、関係人口がうまれ、将来的には2拠点生活の拠点や移住先に選んでもらう可能性も、視野に入れている。
こうした持論の根底にあるのは、古山氏自身の経験だ。故郷の広島県・鞆の浦の祭り「お手火神事」には、長年、祭事運営委員会の役員として携わっており、祭りの季節には家族そろって帰郷していた。地元勤務になった時、子供たちがすぐに友達の輪にとけ込んだのを見て驚くと同時に、「毎年、祭りに参加していたからだ。祭りには、人と人をつなぐ力がある」と実感した。旅行会社勤務時代には、お手火神事を体験する1組限定の旅館宿泊パッケージを企画したこともある。「通常の宿泊料金に5万円ほどプラスした価格だったが、ニーズはあることが証明できた」と振り返る。祭りを基軸にした地域創生は、10年以上、追いかけているライフワークでもある。
実現までの課題
2026年度は、祭り体験の商品化から販売チャネルまで、より具体的な流れについても検討する予定。さらに翌2027年度には、経産省が予算を確保して公募をかけ、全国の祭り開催者から、インバウンド誘致の実証事業への参加を募りたいと考えている。
ただし、経済産業省の実証事業は、新しい取り組みのスタート期を支援するものであり、2年目以降、補助金なしで自走できることが選定の条件となっている。そのため、主催団体が単独で参加するよりも、自治体と連携した形での応募が望ましいとの見方だ。「地域への経済効果や関係人口づくりに資することが見通せるなら、自治体も積極的に予算を組んでくれるのではと期待している。また色々な領域に関わることなので、観光庁や文化庁、ふるさと納税を管轄する総務省などとの協力も、将来的には必要かもしれない」(古山氏)。
実現に向けて、色々なハードルを乗り越える必要があることも覚悟している。例えばプロモーションのコスト負担。「各地域にとって、祭りの開催は一年に一回だけ。毎日、催行できる体験ツアーとは、プロモーションの費用対効果に大きな差がある」と同氏。打開策として、お祭りに興味があるインバウンド旅行者にとって利用しやすい全国のお祭り情報プラットフォームを作り、そこでPRを展開するなどの仕組みを検討している。
神社や仏閣など、主催者側の協力がどこまで得られるかも、今後の課題だ。古山氏は、自身の故郷での経験も踏まえつつ「どこで線を引くか、せめぎあいだ。だが現状のままでは、10年後、同じ形で祭りを存続させるのが難しいことも皆、理解している」。
鞆の浦の「お手火神事」では、燃えている松明と一緒に自撮りしていた大学生のカメラに冷却用の水がかかり、トラブルになったこともある。「地域外から参加者を迎えることで、もちろん色々な軋轢は出てくるだろう。だからこそ、まずは実証調査を行い、注意ポイントなどを検証することが重要だ。トライ&エラーで進めながら、ある程度、マニュアル化もできたらよい。今、できることに全力投球していく」(古山氏)。
実現すれば、伝統的な祭りの維持、来訪者の高い満足度、地域のコミュニティの活性化が実現する三方よしの取り組みになる。今後の動向に注目したい。






















 観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】
観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】