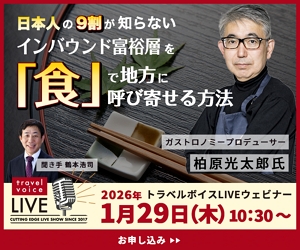日本観光振興協会、最明仁です。
先日、観光関係者を対象にした論文コンテストの審査員を務めました。「観光産業の未来像」「観光産業への提言」「新時代を繁栄で飾るための旅館経営論」などをテーマに、宿泊業、旅行業、運輸業、行政など観光に関わる人々、かつて関わっていた人、これから関わろうとする人たちから世代や立場を超えて多くのすばらしい作品が寄せられました。
観光を日本の基幹産業として育てていくには、人材育成の場としての「学」、観光関係者にとって「知」の拠りどころとしての「学」の役割が重要になります。観光を学び、研究する人たちが集い、議論する場が「学会」ですが、その課題と期待する姿、役割について私の考えを述べたいと思います。
旅館経営者の悩みに驚きの回答
私が審査員を務めた論文コンテストの作品の中で、江戸時代から続く老舗旅館の経営者による一文が目に留まりました。旅館という日本文化について、その方は「接遇おもてなし」「料理の盛りつけ、食器へのこだわり」「すみずみまで清掃が行き届いている」といった目に見える要素だけではなく、「目に見える何かではないけれど、何もないけれど、良かったらいつでもおいでよ」と言える心、すなわち多くのことが効率化されていく現代においても、なお、人々に説明のつかない安心感とともに、ずっと変わらずそこにあり続ける“日本古来の生活文化”を通して「帰れる場所」と述べていました。
一方で、ビジネスとして利益を上げるためには業務の効率化や生産性向上が欠かせません。ある意味の矛盾を抱えながら日々の旅館経営を実践し、少子高齢化や急速なグローバル化が進む日本の社会変化の中で「旅館らしさ」を再定義しようと思案しているとのことでした。他の旅館経営者たちとも「旅館って何だろうか」と議論しても、それぞれが言葉を詰まらせてしまい、結論に至ったことはないそうです。そのため、大学院で「旅館経営」を教えている教授に「旅館の定義」を尋ねたところ、その教授からは間髪入れずに「部屋数が少数であること」と「泊食分離でないこと」と2つの条件のみを提示されたといいます。
旅館文化を守りながら経営を成り立たせることに腐心している経営者が納得できるはずもなく、経営の経済効率だけの紋切り型の回答に驚き、ガッカリした様子が論文の内容から伝わってきました。旅館には、もちろん部屋数の多いところもありますし、すでに泊食分離をオプションにしているところも多くあります。ほんの一握りとはいえ、「観光学」を司る立場の大学院の教授が、自らの研究領域内の知見だけで思慮の浅い対応となっているようでは、産官学の一つの柱が傾きかねません。
日本の観光関係学会が抱える主な課題
1.学会、学際間の連携不足
日本の観光学は、例えば経済、経営、会計、文化、地域経営、旅行業、ホテル業、都市工学、建築、人間行動学、社会福祉など多くの分野の中で研究が行われています。それぞれの専門領域内では日常的に活発な議論、研究が行われていますが、残念ながら分野を横断した議論や共同研究、これらを統合的におこなうアプローチが十分とはいえないようです。また、観光学は体系化が遅れているとの指摘もあり、観光を俯瞰する役割を学会で担うなど、議論をリードする組織づくりを進める必要があります。日本の主要な観光学会の一つ「日本観光研究学会」でも、多くの研究者がこのことについて言及しています。
2.地域との連携の弱さ
観光を手段にした地方創生の好事例が増えるとともに、観光学の重要性が高まっていますが、残念ながら地域住民や自治体との連携が不十分なケースが依然として多く見られます。せっかくの研究活動が地域で知られることなく、プレゼンスが低いまま、研究内容も地域や現場とのニーズと乖離してしまうこともあります。そして、研究成果が地域政策に活かされにくいという問題もあります。
2025年9月にAICHI SKY EXPOで開催されたツーリズムEXPOジャパンには、多くの大学の観光学部がブース出展をおこないました。学生が主体的にブース運営をしたり、大学が所在する地域の課題解決への提言や研究成果の発表もありました。すばらしい内容で心強く感じる反面、理論とフィールドワークをバランスよく指導、研究している大学が少ないなとも感じました。観光学が体系化され、基本理論の土台が定まっていれば教育、研究の効率化と深みにもつながります。
3.急速な変化への対応力、データ活用と研究手法の限界
コロナ禍以降、観光産業は大きく変化しています。特に、インバウンド需要の急拡大、旅行内容の変化への対応が急務です。しかし、観光学会の研究テーマや手法が変化のスピードに追い付いていないという指摘があります
観光データの収集・分析では、デジタル化、ビッグデータやAIなど先端技術の活用が遅れ、従来型のアンケート調査や事例研究に依存しがちで、実証性や予測力に乏しい研究が多いとされています
4.国際的視野の不足
日本の観光研究は国内中心で、国際的に比較研究や海外学会との交流が限定的です。グローバルな観光トレンドに対する理解や発信力が弱く、国際競争力のある知見の創出が課題となっています。
例えば、DMO関連の米国や欧州の統括団体の総会でも、日本から参加する研究者はいつも同じ顔ぶれで、限られた人が参加しているのが現状です。国際規格ISOの審議の場にも、本来は研究者が積極的に参加し、議論をリードしていくことが期待されますが、産官学が一体で取り組む他国と比較して、日本は劣勢に立たされているのが現状です。
ツーリズムEXPOに出展した国学院大学のブース(筆者撮影)
観光の「知」の結集を、「知」の拠りどころを
これらの課題を克服するためには、学会の枠を超えた連携、地域との協働、そして柔軟な研究体制の構築が求められています。観光を経済活性化、地方創生の手段にとどめず、社会行動として捉え直し、持続可能で包摂的な観光のあり方を探ることが、今後のカギとなるでしょう。
理想をいえば、土木学会のように産官学を強力に束ね、広範囲にわたる研究分野を横串しでつなぎ、交流を活発化させ、俯瞰して観光を体系的に論じる学会組織づくりが必要です。また、冒頭の旅館経営者のように、現場から生まれる疑問や相談に対して、観光学会がワンストップで「よろず相談所」として受け止める機能を持てば、観光産業からの求心力や信頼もより高まるでしょう。
一方で、「学」には本来果たすべき役割があります。「学」側から見て、産業や行政の対応にも大いに問題があると思っています。産官学それぞれの役割と長所・課題を共有し、長所と課題を包み隠さず共有し、率直に議論できる場を構築することが必要だと思います。理想論に聞こえるかもしれませんが、一度、研究者の皆さまとも議論を深めてみたいと考えています。























 観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】
観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】