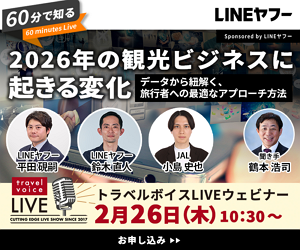国学院大学・観光まちづくり学部教授の塩谷英生(しおや ひでお)です。
前回のコラムでは、訪日市場の基本統計である「インバウンド消費動向調査」を中心に観光統計の読み解き方について紹介しました。今回は、日本人の国内旅行の基本統計「旅行・観光消費動向調査」についてご紹介したいと思います。
国内旅行の重要性
2024年のインバウンド消費額は8.1兆円となり、前年に比べて2.8兆円増加して存在感を強めています。しかし、日本人の旅行消費額は26.2兆円あり、こちらも3.4兆円増加しています。両者合わせた旅行消費額34.3兆円に対する日本人のシェアは76%で、依然として日本人マーケットは重要と言えます。ドル円レートも予断を許さない状況で、もともとインバウンド市場は変動リスクも大きいですから、国内旅行市場の健全性を維持することが大切です。
さて、この“日本人の旅行消費額”を推計している基本統計が「旅行・観光消費動向調査」となります。2000年から調査が開始され、総務省承認の統計となったのが2003年からです。この調査は家計調査の一種で、直近の宿泊旅行や日帰りの実施回数、消費額や旅行内容について調査したものです。
日帰り旅行の定義は、日常圏を離れ、片道の移動距離が80キロ以上、または旅行の所要時間が8時間以上かかった場合としています。この定義は、この統計を作成する前に行われた予備調査で、だいたい8割程度の人がこれは旅行だなと感じる距離や時間を基に決めています。なお、宿泊を伴う移動は基本的に旅行として扱われますが、交通機関の乗務や出稼ぎ、1年を超える滞在は旅行活動とはみなされません。
余談ですが、この統計の弱点として、あまり旅行をしない人に調査票を送っても「自分とは関係無い」と考えて回答しないケースが多い点があります。そのため、旅行量が過大推計になりやすいのが特徴です。逆に、ビジネスでの旅行頻度が多い人などの場合は、回答する負担、不在がちなどの理由で回答率が下がるケースもあります(過少推計となる)。もちろん、旅行しなかった方にも回答してもらうよう依頼文を送付する、無回答者に督促を行うなど回収率の向上に努める工夫は行われています。
但し、一般論として申しますが、こうした統計調査は価格競争入札で行われているため、低価格で受託した事業者は調査コストを抑制する可能性があります。委託者である国側は、調査品質の管理や、インサイダー情報の漏出防止などにより留意する必要があるでしょう。
宿泊旅行市場の構造、「宿泊旅行が伸びている」の実相
さて、2024年度の日本人旅行市場の内訳は、宿泊旅行20.3兆円、日帰り旅行4.8兆円です。
国内旅行で圧倒的に重要なのは宿泊旅行です。目的別の消費額をみると、観光・レクリエーション13.6兆円、帰省・知人訪問等3.6兆円、出張・業務3.1兆円です。コロナ禍前の2019年はそれぞれ、10.5兆円、3.6兆円、3.0兆円でした。帰省旅行も出張旅行も、額としては横ばいですが、そのシェアは帰省が21.2%から17.8%、出張が17.8%から15.1%へ落ちています。
出張旅行は、経費削減も兼ねてオンライン会議に切り替える例も増えたと思われます。また、宿泊単価の高騰から社内規定の宿泊費で泊まれる施設が都市部などでは限られてきます。実費精算を認めてもらえる場合でも社内承認の手続きは増えますので、こうした障壁も出張旅行の減少に影響していると考えられます。
結果として、観光目的の宿泊旅行のシェアが61.1%から67.1%へと伸びています。もっとも、消費額の増分の多くは観光宿泊旅行の単価上昇によるものと考えられます。
総務省の「消費者物価指数」から「宿泊料」をみると、2019年を100とした場合の2024年値は128で、28%も上昇しています。もちろん、宿泊費以外の飲食費や交通費など他の費目の単価も上昇しています(宿泊費ほどではありません)。また、後述の海外旅行費用の高騰は、代替需要が国内へ向かう要因となっていて、宿泊観光旅行を底支えしています。従って、国民の観光旅行需要は、物価水準の変動を考慮しない名目の伸びほどには伸びていないというのが実態と考えられます。
なお、宿泊・日帰り旅行のほかにあるのが、海外旅行の国内支出分の1.0兆円。海外旅行へ行く際、国際空港までの交通費や旅行会社手数料など国内で発生する支出です。海外に支払われる額は、海外旅行消費額4.3兆円からこれを除いた3.3兆円となります。
コロナ禍前の海外旅行消費額は4.8兆円でしたから、市場はずいぶん回復したかに見えますが、そうではありません。2019年の海外旅行者数は2003万人で消費単価24.2万円でした。これに対して2024年の旅行者数は1291万人に過ぎず、円安の下で単価は33.2万円と37.3%も上昇しています。これほど上昇しても、平均泊数は8.2泊から5.9泊に短くなっていますから、海外旅行の単価は実質的には5割以上割高になっているといえるでしょう。特に観光目的の海外旅行の平均泊数は7.8泊から5.3泊と短くなり、近場が増えていたとみられます。その消費額も3.7兆円から3.0兆円へと減少しました。
日本人の底堅い旅行需要は誰が支えているのか?
日本人の観光需要が名目ほど伸びていないのが実態とはいえ、旅行単価の高騰の中でも旅行需要の底堅さは感じられます。では、誰が旅行市場を支えているのでしょうか?
これも「旅行・観光消費動向調査」のデータが参考になります。旅行頻度の多い層、特に年4回以上のコア層は、2024年に約11.3%を占めています。そして、この1割強の人々が宿泊観光旅行の延べ旅行回数の実に55.5%を占めているというのが旅行市場の構造となっています。宿泊観光旅行が、必ずしも誰もが楽しむことができる活動とは言えない商品となっており、2024年に旅行をしなかった人が国民の50.5%と半数を占めているのが実態です。この旅行回数ゼロの比率は、2010年45.5%、2015年46.8%、2019年48.0%と長期的に上昇する傾向がみられます。
そして、コア層の人々の特徴は、もちろん消費における旅行の選好度が高い層ではあることが前提ですが、やはり収入が高い職業や、公務員のような安定的な職業に就いている人が多く含まれています。従って、経済的要因から旅行から遠ざかっている人々を市場に呼び戻すためには、可処分所得の向上や、雇用の安定といった経済政策が先ず基礎となるべきではないでしょうか。
その上で、宿泊旅行の6割で利用されるマイカーやレンタカーについてはガソリンの暫定税率の廃止、高速道路料金の割引制度拡充なども有効だと思われます。また、国民の旅行需要のオフシーズンへの分散や、旅行先の分散、特にインバウンド客が集中する地域以外への旅行促進なども施策の基本方針として重要となるでしょう。合わせてインバウンド客の旅行時期や旅行先の分散についても、日本人の需要と重ならないように進める工夫も必要です。
























 観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】
観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】