
ブッキング・ドットコム(Booking.com)では、2年前に米国でローンチした「AIトリップ・プランナー」のEU市場投入に向け、準備が大詰めを迎えている。GDPR(一般データ保護規則)、DSA(デジタルサービス法)など、世界で最も厳格なルールを敷く欧州でのローンチは、生成AIによる旅行プランニングの本格的な幕開けになると同社は位置づける。さらに、2025年夏頃には日本語版も稼働したい考えだ。
生成AI活用による旅行プランニングの現在と近未来について、オランダ・アムステルダム本社から旅行テックの国際会議「WiT Japan」のために来日したプロダクト担当シニア・ディレクター、エイドリアン・エンギスト氏(写真)に聞いた。
試行錯誤を繰り返した導線づくり
「AIトリップ・プランナー」とは、ブッキングの既存の機械学習モデルをベースに、オープンAIのチャットGPTと連携して大規模言語モデルを部分的に導入したもの。2023年6月、米国のブッキング・ドットコム一部会員を対象にパイロット版が始動した。チャット形式でユーザーと自然な会話をしながら、相手の興味関心に合いそうな宿泊施設やデスティネーションを選んだり、おすすめ情報を提案したりするもので、文字だけでなく、画像も表示する。
「世界最大のOTAであるブッキング・ドットコムの強みは、旅行サービスに関する価格や在庫、施設の概要など、圧倒的な規模を誇るデータベースを構築していること。だが、せっかく膨大な情報があっても、旅のプランが何も決まっていない人に対しては、フリーテキストによる会話を糸口にレコメンドしたり、旅のインスピレーションにつながる情報を提示したりすることはできなかった」と、エンギスト氏はかつてのもどかしさを振り返る。
旅行者が目当てのものを絞り込むための検索フィルターでさえ、その数が多すぎて、一度にすべてを表示するのは難しいケースもある。「生成AIがブッキング・ドットコムのデータベースの中からその人に合ったものを探し出してきてくれる、フレキシブルな使い方を目指して開発した」(同氏)のがAIトリップ・プランナーだった。
とはいえ、ベータ版をローンチした当初は、ユーザー側がまだ生成AIの使い方に慣れておらず、検索ボックスのチャット版のような利用が目立ったという。そこで、これを改善するために、「この宿泊施設の雰囲気は?」「食事のオプションは?」など、より自然な会話的アプローチで、詳しい情報の紹介へとつなげられるように、AIトリップ・プランナーとのチャットの導線づくりを試行錯誤してきた。
現在も修正と最適化を繰り返しながら、精度アップを進めている段階であるため、AIトリップ・プランナーは「今もまだベータ版」(同氏)との認識で、大々的なプロモーションなどはおこなっていない。だが、仕事や日常生活でAIを活用する人が増えるなか、ブッキング・ドットコムのプラットフォームでも、AIトリップ・プランナーと対話しながら、上手に情報を引き出すユーザーは増えているという。「まだ公表できる規模の数字はないが、AIに色々な質問を投げていた人が、最終的に旅行を予約するという相関関係は、確実に出ている」とエンギスト氏は話す。
日本はコンテンツ連動型を検討
AIトリップ・プランナーは、米国に続いて英語圏の英国、シンガポール、豪州、ニュージーランドでもの利用は始まっているが、大きな節目は、EU市場でのローンチになるとエンギスト氏は考えている。米国に比べて、EU当局によるデータ・プライバシー保護関連の規制ははるかに厳格であるため、これに対応できる仕組み、「ゴールデンスタンダード」を確立するべく、コンプライアンスや安全面の課題解決に多くを費やしてきた。2025年中には、欧州6カ国語でAIトリップ・プランナーを稼働したい意向で、その後、日本を含む他の市場への横展開を進められればと話す。ただし、スケジュールありきではなく、「注意深く、慎重に進めている」とも明かす。
日本における、日本語版のAIトリップ・プランナーの展開手法については、「当初の計画を少し見直して、打ち出し方を調整しているところだ。インデックスページで『なんでも聞いてください』と呼びかけるスタイルよりも、コンテンツ連動型のエントリーポイントを絞り込む方向で検討している」(同氏)。
残念ながら、生成AIは完璧ではないため、ブッキング・ドットコム独自のオーケストレーション・レイヤー(複雑なプロセスを自動化・管理するレイヤー)を構築し、生成AIが既存の機会学習モデルやレコメンダー(おすすめ機能)と一緒に機能する仕組みを整えている。「ブッキングがこれまでに構築し、改良してきた機械学習や人間による内容のチェックや修正作業は引き続き、欠かせない。ハルシネーションを避け、事実に基づいた内容、法令違反がなく、インクルーシブでバイアスのかかっていない情報が提供できる体制作りが必要だ」(同氏)。
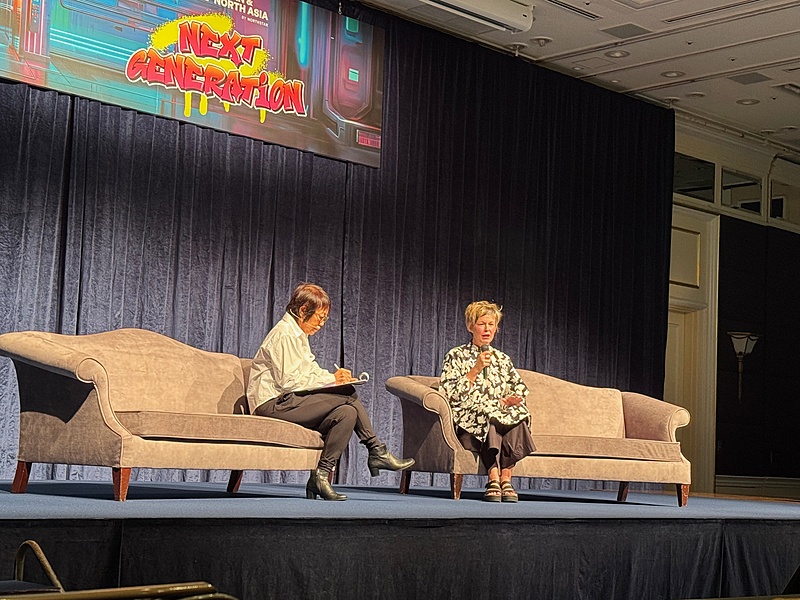 旅行テックの国際会議「WiT Japan」登壇時のエンギスト氏
旅行テックの国際会議「WiT Japan」登壇時のエンギスト氏
生成AIとの会話がゲートウェイになる
ブッキング・ドットコムのプラットフォーム上における生成AIの利用者数が、既存の検索ツール利用者数を超えるまで、あと何年ぐらいかかるか?との問いには、「今の状況から推測すると、あと6カ月。遅くても来年の夏ぐらいではないか」とエンギスト氏は即答。「6カ月前に、同じことを聞かれていたら、3年と答えていた」と付け加えた。背景にあるのは、自律型AIの技術進化で、生成AIは「おしゃべりな友人」から「ほぼ自律型のデジタル同僚」へと変貌を遂げつつあるという。
「そもそもグーグルのジェミニ(Gemini)やChatGPTは、初期のユースケースの一つが、旅程作りの相談相手だった。生成AIとの会話が旅行プラットフォームの入り口になり、そこから旅程作りを始める時代へと、あっという間に進むだろう」とエンギスト氏は予想している。
ただし、生成AIとの会話だけで、複雑な旅程作りを完結できるようになるには、もうしばらく時間がかかると指摘。理由の一つに、エンギスト氏は「旅行のスケジュール作りは、基本的に数学的なタスクで、大規模言語モデルだけでは対応できない」ことを挙げ、自律型AIのさらなる進化が欠かせないとの見方を示した。
生成AIを味方につけて成果を出すために
日本の宿泊施設など、パートナー事業者の反応はどうみているのだろうか。「AIトリップ・プランナーが動き出せば、今まで主流だった検索とは違うルートで、旅行者から見つけてもらう機会が増える。期待と不安があると思うが、基本的には、実はこれまでと変わらない。検索結果の上位表示に向けたSEO対策と同じことが必要になると思う」(同氏)と話し、画像、動画、ゲストレビュー、施設についての紹介文などの充実がカギになるとしている。
なかでも宿泊ゲストによる詳細なレビューは、引き続き重要になると話す。「生成AIが何千件ものレビューを読み込み、質問に答えるので、たとえば『ペット・フレンドリーなホテル』という項目にチェックが入っているだけでなく、実際に宿泊した飼い主による体験談があれば、それを参照してAIがより詳しい説明をする。こうした情報が充実しているほど、旅行者と生成AIとの対話も深まるため、特にポジティブな体験をしたゲストには、レビューをお願いするべきだ」とエンゲスト氏はアドバイスした。
取材・記事 谷山明子























 観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】
観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】









