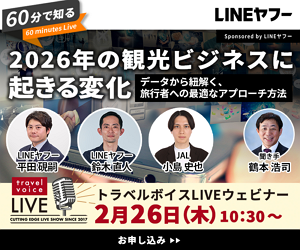国学院大学観光まちづくり学部の井門隆夫です。
かつて、観光学を学ぶことができる大学の数は、ごく少数でしたが、いまでは100を超える大学が学部や学科、専攻コースを設けています。今回は、当大学と学生たちを事例として、観光産業の未来に向けて今起きていることを再考します。
「観光×地域コミュニティ」を考える人材育成
国学院といえば、近年、駅伝やスポーツで近年知られていますが、創立140周年を迎える令和4(2022)年に観光まちづくり学部を新設しました。
なぜ、今、「観光まちづくり」なのか、なぜ学部名に「まちづくり」が入るのか。それは、日本が失いつつあるコミュニティについて考える人材を育て、地域を再生していく必要に迫られているからといえます。神社界とも関係の深い大学ですが、このままでは神輿の担ぎ手も不在となるという危機感もあったと思います。そうした、まちの課題を観光で解決しようという理念から、「観光まちづくり学部」が生まれました。
コミュニティを考える上で、私のゼミでは「コミュニティ・ベースド・ツーリズム(community based tourism)」をテーマに掲げ、離島や海外にも視野を広げてフィールドワークを実践しています。コミュニティ・ベースド・ツーリズムとは、地域コミュニティが主体となって観光を推進するツーリズムの形態です。コミュニティが失われると社会にどのような影響が生じるのか。答えのない問題に対して仮説をたて、検証を続けることが学生のミッションです。
そんな本学部の学生たちの姿を紹介しましょう。その姿からは、観光の未来に向けた課題と解決策が見えてきます。
学部には今春、初々しい4期生が入学してきました。入学式前の4月1日に、まずおこなったことは、全員でクラスの仲間をみつけるゲームでした。先輩学生の「一人で入学式に行くのが不安だった」という声で始まりました。社会人からすると、18歳は、そんなにやわなのかと驚かれると思いますが、常に友だちがいないと不安が募る心理はセーフティネットを失った日本の子ども社会の典型的現象です。
そして、授業開始後に、学生に1つの質問をしてみました。「今、社会の出来事で興味を持っていることは?」という問いかけです。口頭で聞いても答えないのでスマホを使いますが、1分で1人2つも3つも答えてくれます。入試の課題では、時事ネタを挙げた学生たちですが、今聞くと、ほぼ全てが芸能ネタか政治ネタ。バラエティには興味あるけれど、米の価格上昇や旅行業の海外展開など新聞に載っているような情報は、誰も挙げません。理由は簡単。そうしたネタを知っていても仲間との話題にならないからです。大学での最大の目標は友だちを作ることなのです。
ユニセフの子どもの健康に関する調査では、日本は先進国38か国中、身体的健康が1位の一方でメンタルは37位。日本の15歳の子どもたちの人生の幸福度が先進国最低レベルである背景には、家族間の衝突や学校でのいじめの存在のほかに、友だちを作るのが難しいという悩みがあることが示されています。大学でも親の子どもに対する過保護、過干渉を感じることがよくあります。就職活動も親が干渉している学生ほど、無駄な作業をしがちです。しかし、いつまで経っても子どもが頼れるのは家族だけ。そうした意味でも、もう少し家族や学校以外の社会に触れる機会や、セーフティネットを生む仕組みが必要なのです。
学生たちの実像、「お金がない」は本当か?
そんな20歳前後の若者に社会へ訴えたいことを聞くと、私たちが年金をもらえないのはおかしいと言います。まだ社会にでも出ておらず、年金も納め始めてもいないので心配はまだ早いと思うのですが、親も祖父母も将来に向けて貯金しなさいと言うそうです。しかし、そうした不安心理が日本の経済・社会、ひいては観光需要の縮小につながっていないかと問題提起しています。
1970年代から赤字国債で積み上げてきた日本の負債は1000兆円を超えます。そのことをして若者は不安視しているのだと思いますが、日本人の個人金融資産の合計はその倍の2000兆円。政府の負債が個人の資産に置き換わり、日本は物質的に豊かになりました。それでもまだ老後不安から貯金しようと考える思考が、消費の減退につながっているのではないかというのが私の仮説です。観光を学ぼうとするのであれば、若者らしく旅に出て消費すればよいのです。そう言うと間違いなく、学生たちは「お金がない」と答えます。
旅に出るお金がないのであれば、親からの援助を考えられないでしょうか。生前贈与は年110万円まで非課税です。祖父母からの教育資金の一括贈与の非課税枠なら1500万円です。World Giving Indexによると日本の金融贈与は142か国中141位。寄付文化が根づいていないので、贈与という発想にならないのかもしれません。
それ以前に、お金の使い方がゲームやサブスクの課金である限り、親も子を信用できないのかもしれません。ただ、目の前の社会から逃避する上で、ゲームやSNSが恰好のセーフティネットになっている現実もあり、しかたない側面もあります。
旅の消費意欲が、お籠もりや貯蓄欲に勝らない限り、観光の未来を描くのは難しく、観光需要がインバウンド依存になってしまいます。
おそらく「お金がない」は言い訳です。どこに行けばよいのかわからないのです。行くとすれば、インスタグラムやTikTok、YouTubeで見た観光地。旅の行き先でも、若者の行動は常に「同調」です。これを打破するためには、知らない地へと連れ出すしかありません。それも国内ではなく海外デビュー。社会人になる前にパスポートを取り、これまで学んできた英語を海外で実際に使ってみることが目標です。
日本旅行業協会(JATA)では、2025年3月から海外旅行拡大プロジェクト「もっと!海外へ」を展開していますが、まさに同感です。
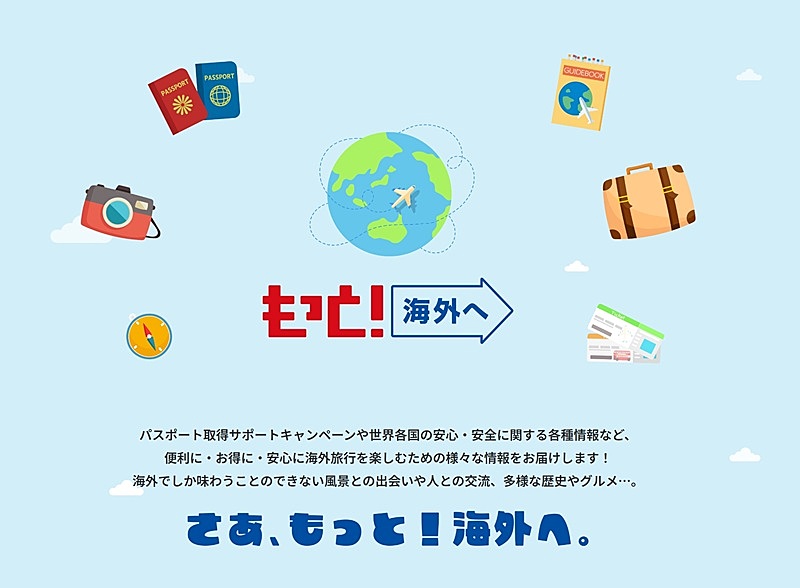 日本旅行業協会(JATA)が展開する海外旅行拡大プロジェクト「もっと!海外へ」
日本旅行業協会(JATA)が展開する海外旅行拡大プロジェクト「もっと!海外へ」
海外での経験は豊かな学び
観光まちづくり学部では、2年生の希望者を対象にベトナム・ダナンへとスタディツアーに連れていきます。多くが初海外の学生ですが、そこで学ぶことは、信号のない道路の渡りかた、日本円以外での買い物、食べなれない異国の料理を味わうこと、などたくさんあります。まずは日本以外を知ることが目的です。
そして、海外体験に慣れた翌年、私のゼミではカンボジアの少数民族の村へとホームステイに出かけます。水を安心して飲めるのは日本を含めて世界で9か国しかないことや、一見、原始的な生活でも環境保全につながっていることを理解します。あるいは、核家族制のカンボジアでは、中学生になると家を出て、自立に向け手に職をつけるために学校に行くことなど、進学か結婚まで家を出ない男子直系家族制の日本との文化や規範の違いを学びます。
村では、雨水の貯水槽から水を流すシャワーに慣れず「風呂キャンセル」となったり、神が宿ると言われ裸足で入ることがルールのトイレに土足で上がったり、日本カルチャーに染まった学生は異文化に慣れるのに時間がかかります。ミネラルウォーターを買ってきて頭を洗う学生を不思議そうに村の方が見ていたりします。小学生の英語の授業に交じっても、日本人が周囲で聞いている限り恥ずかしくて英語が話せません。その割にいつも日本人ばかりで固まっています。そのため、2人ペアくらいで活動をさせるようにします。
学生たちは時間が経つにつれ地域に慣れ、力をつけていきます。そして、現地の生活のなかに、いつでも帰ることができるコミュニティが存在することに気づきます。反抗期になる前に巣立ったカンボジアの少数民族の子どもたちにとって、コミュニティはセーフティネットなのです。親は子どもが巣立った時のままの家で、神々に守られた循環型の生活を維持しています。
村にとって、小さな子供たちを外国人と交流させることが学びとなり、自分たちの文化を紹介することが誇りにつながります。私たちを受け入れてくれることこそ、コミュニティ・ベースド・ツーリズムの原型になっているのです。
観光まちづくりを考える上で、教室での学びには限界があります。ゲーム機を置き、旅に出ることから学びが始まります。
























 観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】
観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】