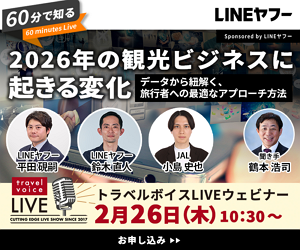ポルトガル政府観光局は、「The Art of Tasting Portugal」プロジェクトの一環として、2025年4月~10月にかけて日本でポルトガル料理のプロモーションを実施する。
このプロジェクトは、日本市場にポルトガルのガストロノミー(美食文化)の魅力を紹介するもの。観光局は、プロモーション戦略の重要な柱に位置付けている。今後展開するプロモーションでは、ポルトガルの7つの地方から、7名のシェフが来日し、日本でポルトガルの食の魅力を発信する。
※上写真は、第一弾イベントの様子。
第一弾は、東京と大阪で、ミシュラン1つ星とグリーンスターを獲得するヴィゼウのレストラン「Mesa de Lemos」のディオゴ・ロシャ氏と、リスボンの「Tasca da Esquina」のヴィトール・ソブラル氏、日本からはレストラン「Noda Harajuku」の野田祐貴氏、3名のシェフがコラボレーションするイベントが開催された。
また、ビジット・ポルトガルは、最新キャンペーンとして「Portugal, uma receita por escrever(ポルトガル、まだ綴られていないレシピ)」も展開している。
 左から、ポルトガル政府観光局取締役会メンバーのリディア・モンテイロ氏、「Mesa de Lemos」ディオゴ・ロシャ氏、ジルベルト・ジェロニム駐日ポルトガル大使、「Tasca da Esquina」ヴィトール・ソブラル氏
左から、ポルトガル政府観光局取締役会メンバーのリディア・モンテイロ氏、「Mesa de Lemos」ディオゴ・ロシャ氏、ジルベルト・ジェロニム駐日ポルトガル大使、「Tasca da Esquina」ヴィトール・ソブラル氏
ガストロノミーツーリズムで地域活性化、住民参加を促す
このほど、プロモーションのために来日したポルトガル政府観光局取締役会メンバーのリディア・モンテイロ氏に、今回のプロモーションの狙いと取り組みについて聞いた。
同氏によると、近年、ポルトガルでは星付きのレストランが増加。2024年には、「ミシュランガイド」のスペイン・ポルトガル版が、両国の合冊版から一か国ずつの独立版となった。ポルトガル各地に、「良いレストランが増えているのが理由」と、その豊富さに自信を見せた。
ガストロノミーツーリズムを重要視する理由については、「ポルトガルの食は、タビナカ体験のひとつ。その体験を、それぞれの地方の人が紹介することが意味がある。農家や地域の人々が、観光に参加することになる」と説明。そして、「地域の多様性、その土地の魅力を知ってもらうためにも、観光に住民が参加することは大事なこと。ガストロノミーツーリズムは地域活性化のために欠かせないもので、それによって雇用が生まれて地方が豊かになる」と話した。
ポルトガルの外国人延べ宿泊数は、2023年7718万泊、2024年は過去最高となる8030万泊を記録した。同氏によると、世界的に不確実性が増しているものの、2025年も堅調な伸びを示しているという。一方で、訪問先としてリスボン、ポルトの2都市に集中している課題もあり、その他の地方へ分散・誘客をしていくうえでも、地域の食を発信していくことは欠かせないとの考えだ。
日本市場へのアプローチでは、開催中の大阪・関西万博も観光プロモーションの場として期待をかけている。
万博のポルトガル館のレストランでは、第1弾の食のイベントに参加したシェフ、ディオゴ・ロシャ氏が特別メニューを監修。また、来館者に向けた食とクラフトを融合させた試食イベントも実施した。5月にはポルトガルが英国の「アフタヌーンティー」文化が確立するきっかけとなった歴史、日本とのつながりを感じさせるイベント「五時のお茶」(木曜日から日曜日)を開始した。
モンテイロ氏は。「万博は、自分の国の持っている魅力を、特に日本の人に見せるという大切な意味のある機会ととらえている。多くの国がそう考えているはず」と力を込めた。























 観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】
観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】