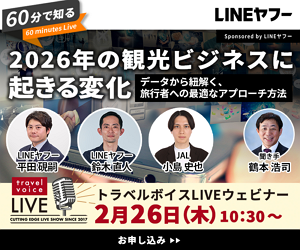多言語化AIソリューションを展開するWovn Technologies社は、インバウンド消費の拡大に向けた施策を考えるイベント「GLOBALIZED by WOVN.io インバウンド 世界は、もっと日本を好きになる」を開催した。交通・小売・宿泊・レジャー・外食・メーカーなど多様な業界が集まり、政府目標のインバウンド消費15兆円に向けた現状や今後の取り組みなどを共有した。
そのうち、宿泊関連では、「インバウンド宿泊体験の“多様化と深化”─2030年に向けたホスピタリティ戦略─」として、近鉄・都ホテルズ取締役ホテル運営本部副本部長の能川一太氏、温故知新代表取締役の松山知樹氏、Nazuna代表取締役の渡邊龍一氏が登壇。ターゲティング、滞在中のサービス、顧客満足度や再訪意向の向上などについて意見を交わした。
インバウンド宿泊者の現状は?
まず、3氏は自社施設でのインバウンド宿泊者の現状を説明。近鉄・都ホテルズの能川氏は、国内で23施設を運営する都ホテルズ&リゾーツについて、「半分強がインバウンド。エリアによって割合は異なるものの、大阪が一番多く、東京、博多、京都が続く」と話した。セールスやプロモーション費用も全体の半分ほどをインバウンド市場に振り向けていると明かす一方で、「ターゲットが1つの国やエリアに偏るとリスクもある。様子を見ながら予算や施策を考えている」と付け加えた。
全国で宿泊施設を展開する温故知新のインバウンド比率は、地域や季節によって異なる。長野県・白馬の施設では、冬のスキーシーズンに95%ほどがインバウンド客になるが、夏季になると減少。北海道・礼文島や五島列島の施設では数%にとどまるが、松山氏は「その人たちは、我々の施設がなければ、絶対にそこには来ていなかった」と話し、同社の目的である「旅の目的地となるホテル」が功を奏していると自信を示した。
Nazunaは、京都を中心に町屋などをリノベーションした宿泊施設を展開。そもそも京都はインバウンド旅行者が多いことから、8割がインバウンドで、日本人が2割だという。同社はインバウンド集客ではSNSマーケティングを強化。渡邊氏は「外国人向けには、宿泊施設のハード面だけでなく、その土地の歴史など背景のストーリーや体験できることを中心に発信している」と明かした。一方で、「日本人旅行者に支えられている部分もある。日本人、インバウンド双方に魅力的な宿泊体験を提供している」と強調した。
インバウンド向けの販売チャネルは?
3氏は販売チャネルについても説明。Nazunaでは、OTAが予約流通のメインとなるが、直販の比率も45~50%まで伸びているという。渡邊氏は「SNS時代、自社の発信力を強化していくことが非常に重要」と話したうえで、「写真1枚変えるだけでも、予約件数が増えることもある。SNSマーケティングでの様々な数字を紐解いて、課題を洗い出し、改善していくことが大切」として、データドリブンの分析に注力していると説明した。
一方、近鉄・都ホテルズの能川氏は「意外とアナログなアプローチが効く」と話す。ターゲットとする市場の旅行会社との関係を築きながら、その国の歴史文化や習慣を学び、それを自社ホテルに持ち帰って共有することが、インバウンド受け入れには重要になってくるとの考えを示した。
温故知新の松山氏は、SNSマーケティングへの予算配分では試行錯誤している段階としたうえで、「まずはグループのブランド力を高めて、各市場で知名度を上げていくことを考えている」と説明。また、海外エージェントとの信頼関係の構築の重要性についても触れ、「温故知新のホテルに送客すれば大丈夫と思ってもらえることは極めて重要」と強調した。
地方誘客に向けて魅力を発信
国の取り組みとしてインバウンドの地方誘客が推進されているなか、3氏は日本の魅力の発信についても意見を交換した。温故知新の松山氏は、ストーリーテリング(物語)が大切としたうえで、地域に根付く職人に焦点を当てたクラフトツーリズムを提案。「職人にお金を払い、職人のストーリーを聞きながら現場を見学すれば、職人にとっては新たな収入源にもなるし、購入機会にもつながる可能性もある」と話した。
「おせっかい」をサービスのコンセプトに掲げるNazunaの渡邊氏は、リピーターの創出に向けて、「滞在体験では、スタッフと接することで感じられる日本人の温かさをしっかりと届けることが重要」と強調。そのうえで、課題としてタビアトでの宿泊者との接続性を挙げた。
近鉄・都ホテルズの能川氏は、都市と地方のホテルとでは伝えていくものが違うとして、「地方のホテルでは、情緒的価値を提供していくべき」と話し、例として、食文化のストーリーを挙げた。
このほか、今後の課題についても意見交換。温故知新の松山氏は、訪日客6000万人に向けて地方空港での受け入れ強化、Nazunaの渡邊氏は宿のストーリー性の発信、近鉄・都ホテルズの能川氏はターゲットに合わせた情報発信を挙げた。























 観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】
観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】