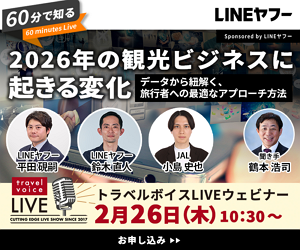観光需要が好調に推移する一方で、依然として課題となっているのが地方誘客だ。インバウンド宿泊の約7割は三大都市圏に集中し、地域経済の活性化に向けても観光産業がどう関わるかが焦点となっている。こうしたなかで、地域の資源を磨き上げ、消費を地方に循環させるための事業を進めているのが観光庁の観光資源課である。
同課が近年、力を入れているのが、地域の魅力を語って体験として伝える「ローカルガイド」人材の育成や、新たな市場として期待される「デジタルノマド」誘致促進だ。政策の最前線や根本にある考え方について、観光庁観光資源課長の矢吹周平氏に聞いてきた。
実証事業を通じて課題抽出、全国に共有
「地方に観光客を呼び込むことは、政策上の重要なミッション。需要と供給のバランスを経済活動につなげていくことが肝だと考えている」。矢吹氏はこう語る。単に人を呼び込むだけでなく、地域の資源に関わる人も含めていかに体験価値として磨き上げるかがカギになるとみる。
地域の魅力を直接伝えるローカルガイドは、従来の観光案内だけではなく、文化・自然・歴史の背景を理解し、旅行者と地域をつなぐ存在としての役割が期待される。それにもかかわらず、人口減少や高齢化が進む各地で確保に苦慮しているのが現状だ。観光コンテンツのサービス供給に直結し、造成したコンテンツの自走化やサプライヤーの持続的な経営への影響も懸念されている。
観光庁は2024年度に「地方部における観光コンテンツの充実のためのローカルガイド人材の持続的な確保・育成に向けた有識者会議」を実施。課題と現状を整理し、2025年度から実証モデル事業を全国で展開中だ。北海道、石川、山梨、兵庫、鹿児島など地域ごとの特性に応じて育成やオペレーションの効率化を試行し、成果を全国で共有することを目指している。
事業推進の方針について矢吹氏は「地域が自らの課題を設定して必要なスキルを探るとともに、全体の課題解決につながる共通認識、アウトプットを得ることが大切。税金を使って実施する以上、課題を誤れば、どんな支援策も本質に届かない」と話す。単なる人材確保ではなく、他地域の参考となる普遍的な課題を抽出することが事業の中心にある。
ローカルガイドは「地域の外交官」
ローカルガイドはスキル体系やキャリアパスの不明確も指摘されている。たとえば、先行する箱根地域では、基礎的なガイドから英語でアドベンチャーツーリズムに対応できるプロ水準までのステップを育成プログラムとして構成し、可視化する取り組みが進む。「人手不足を叫ぶ一方で、育成の仕組みが確立していない。経験則に頼らず、キャリア設計を研究していかなければならない」
ガイド像も変わりつつある。専業のプロフェッショナルだけでなく、他産業との兼業や、地域に根ざしたボランティア活動まで多様化している。矢吹氏は「持続可能な形で人材が再生産されなければ、産業としての成長は難しい」と指摘する。自身の所感として、ヨーロッパやカナダではガイドが高いステータスを持ち、憧れの職業として定着している例を挙げ、「収入と誇りを両立できる職業として確立できるかが、日本のガイド育成の次のステップだ」と話す。
スルーガイドとローカルガイドの役割分担についても矢吹氏は、「前者が旅全体を演出する“総合コーディネーター”だとすれば、後者は地域の魅力を語り、体験を深化させる“コンテンツシェフ”。両者が信頼関係で結ばれたとき、旅行者の満足度は大きく高まる。地域で時間を過ごしてもらうための仕掛け人として、ローカルガイドの存在価値は今後さらに高まるだろう」と明確に示す。ローカルガイドは「地域の外交官」とも表現し、旅行者の最も近い距離で関わることで再訪を促し、地方誘客の持続性を支えると考えている。
働く旅人が地域を変える
世界的なデジタルノマド市場の拡大に呼応した観光地域づくりも求められている。デジタルノマドは、長く滞在し、地域を転々としながらリモートワークで働く新しいタイプの需要。「観光と決定的に違うのは、仕事をしに来る人だということ。リモートワークのための通信環境やコワーキングスペースなどの基本的なインフラ整備だけでなく、地域の人々との交流を通じてアイデアが生まれるような場の仕掛けが必要だ」と指摘し、こうした動きが地域間のネットワークを線として結び、地方誘客の新たな回廊を形成する可能性を秘めていると説く。
観光庁は2025年度「質の高い消費と投資を呼び込むためのデジタルノマド誘客促進事業」として、全国5地域のモデル実証事業を選定。たとえば、金沢ではモニターツアーが始まり、地域コミュニティとの接点づくりや受け入れ体制の検証が始まった。「まだ政策としてはよちよち歩きの段階だが、地域とともに育てていきたい」
デジタルノマド誘致は「生活の視点」が重要
デジタルノマドを誘致するうえで、重視しているのは長期滞在がもたらす「生活の視点」だ。日常的な利便性や居心地のよさ、安全性、食や環境の快適さなどが評価の軸になる。「観光は刺激を求める活動だが、ノマドは生活と仕事がベースにある。日本は治安が良く、食もおいしい。暮らす安心感が強みになる」と語る。
ノマドが1カ所にとどまらず、各地を“ホッピング”しながら滞在することにも期待している。桜前線に合わせて南から北へ移動するように、季節や興味に応じて地域をめぐることで、広域的な経済波及も期待できる。「長くいてもらえるからこそ旅のカタチを増やし、日本の多様性を感じられる体験を提供したい」との考えだ。
その一方で、日本のデジタルノマド政策はまだ世界に十分発信されていない。先行するタイなどに比べて情報発信が弱く、認知度向上が課題だ。「日本で働くこと、地域をめぐりながら仕事ができることの楽しさを、もっと世界に伝えていく必要がある」と強調する。
最後に今後の抱負を聞くと、「観光客がわざわざ時間とお金を使う理由は“感動”にある。観光庁のスタッフはもとより、地方行政、地域の観光事業者と連携し、感動をともに生み出す仲間として取り組んでいきたい」と力を込める矢吹氏。
誇りある職業観を持ち、地域の魅力を伝えるローカルガイドを増やすとともに、日本の多様な資源を活かし、仕事をしながら地域に滞在する新たな価値観のデジタルノマドの誘致に取り組む。消費から共創へ、2つの潮流の結束点も意識しながら、日本全体を感動あふれる、何度も訪れたい国にすることを目指している。






















 観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】
観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】