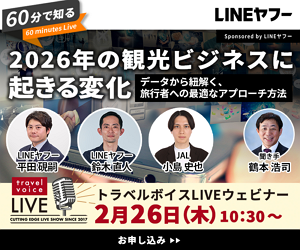東京都立大学観光科学科の清水です。
私は、日本観光振興協会が展開する事業のいくつかに総合研究所所長の立場で関わっています。先日のコラムで、その日観振の理事長である最明仁氏が日本の観光系学会に対して問題提起をおこないました。その問題提起については、私も「基本的にその通り、勇気を持って言ってくださった」という思いです。一方で、学にはその基本的役割や矜持もありますし、最近の学者一般がおかれている就業環境もありますので、私の理解や経験を通じて、という限定的範囲になりますが、それらをお伝えしておこうと思います。
観光学の現場から
言うまでもなく、学の役割は専門分野のこれまでの知の歩みを体系化するとともに、調査研究を通じて最新の問題を把握して、その解決に客観的に答えを出していくことにあります。真摯な学者であればあるほど、不確実なことに対して無責任な回答をしたくないという思いが強くなります。
観光分野はどうでしょうか。
観光という行為には、人々の感情が深く介在するため、観光客を研究対象として客観的に分析することは極めて難しいように思います。私はかつて、若気の至りで土木屋のくせに無謀にも観光心理学の分野に足を踏み入れようとしたことがあります。世界の観光学トップジャーナルに掲載されるようなその分野の研究は、既往研究を整理する部分では「これはすごい大作だ!」と思うのですが、肝心の分析パートになると、急激にトーンダウンするように感じていました。
観光客の行動に影響を与える心理要因を客観的に抽出しようとすればするほど、他の余計な要因の影響をできるだけ排除した被験者調査が必要となり、必然的に分析パートではその着目する要因の有意性だけが厳密に論じられることになります。しかも、その要因概念は全ての観光客に共通して確認される必要があるため、非常に漠然としたものになりがちです。
学問の態度としては確かにそうあるべきなのですが、一方で論文の最後に、「産業への示唆」といった部分が必ずあります。編集方針で無理矢理書かされるのだと思いますが、単に「誘客のマーケティングに役立つ」といった曖昧な記述になっていることが多く、「これでは産業には参考にならないよなぁ」と感じたものでした。この状況を少しでも変えようと頑張ってみたのですが、あっという間に限界を感じ、性に合わなかったこともあり、数年で断念してしまいました。
同時に、観光分野にビッグデータの波が到来し始め、理系の観光を標榜する首都大(都立大)観光に在籍する私としては、「いよいよ時が来た!」と感じたものでした。しかし、その波は学が対応できる速度を大幅に超えて、あっという間に地域を飲み込むことになりました。当時は(今も)観光学分野に大きな研究予算が投下されるわけではなく、各研究者がなけなしの研究資金でささやかに人流ビッグデータを購入していましたが、直ちにこれでは太刀打ちできないことを痛感しました。研究者が予算の範囲内で調達できるデータ量では観測数が少なく、地域では全くビッグなデータにはならないのです。
これに問題意識を感じ、国際観光旅客税(いわゆる出国税)の使途の議論があったタイミングで、「官学が共同利用できるビッグデータ調達と観光関連学会への研究予算支援」を観光庁の幹部の方々に提言したこともありましたが、全く響きませんでした。状況は、現在も基本的に変わっておらず、観光学でビッグデータ研究が案外少ない一因になっていると見られます。
地域の各種事業から学べること
2019年頃から観光圏観光地域づくりプラットフォームや観光地域づくり法人(DMO)との付き合いが増え始め、どう見ても身の丈に合わないデータ調達が進んでいく現場に直面することが増えました。「即刻止めた方がいい」と言いたかったのですが、一方でデータベンダーのビジネスを壊してはいけないので、ジレンマを感じていました。実は、私のような交通研究者であれば、地域では人流が“ビッグなデータ”にならないことは、深い研究をしなくてもセンスで分かります。今は、「地域とデータベンダーがWin Winになれるデータ調達のあり方」を学会から提言しておくべきだったと反省しています。
コロナを契機に、これからの観光マーケット動向を見据えつつ、観光庁では地域の体力を増強するために、既存コンテンツの磨き上げや新たなコンテンツ造成のための補助事業が複数立ち上がりました。私はある事業で伴走支援有識者として携わっていますが、恥ずかしながら自分でコンテンツを作ったり磨いたりしたことはありません。力不足ということで辞退したかったのですが、学界のために関わっておきべきだと思い直し、派遣される地域の皆様には申し訳ないのですが、「自分も一緒に勉強しよう」というスタンスで臨むことにしました。
その事業では、事業名を変えながら毎年切れ目なく継続し、毎年全国で500オーダーのコンテンツ提案が採択されていますので、既に通算で数千のコンテンツが提案されているはずです。しかし、この一連の事業のほとんどが補正予算となっていることも影響してか、事業成果が積極的に情報公開されていません。
どんなコンテンツ開発が成功と位置づけられるのか。失敗した場合の理由は何か。学者の立場からは、その条件や要因を詳細な研究で明らかにしたいと考えます。しかし、造成され、磨き上げられたコンテンツが、その後、安定的に販売されているのかなどのフォローアップ調査がおこなわれていません。これでは、事業効果の検証が不可能であるだけでなく、今後のコンテンツ開発に向けて何の科学的知見も残せません。この危機感から、観光庁が保管する膨大な事業報告書を学会に提供してもらい、同時に調査予算も提供してもらってフォローアップ調査が出来ないものか、様々な関係者に訴えかけていますが、これも響きません。
研究のあるべき姿と、未来への課題
ここまで、いくつかのエピソードを書きましたが、私個人としては、学問的知見を武器に観光政策や観光産業の発展に貢献したいという思いは強いものの、大きな壁に直面している状況に忸怩たる思いがあります。そして、同じような思いを抱く観光学者の仲間も少なからずいると信じています。一方、個人の限定的な成功体験だけで政策提言や伴走支援するような専門家(学者とは言いたくない)が現場から重宝されていることも事実です。いずれも産官と学の距離が遠すぎることが原因だと考えています。最明氏と同じ意見ですが、産官学の相互理解のための場を可及的速やかに設定すべきです。
観光学に限らず、最近の大学は、程度の差はあれ、研究論文の数(しかも影響力の大きい海外誌の掲載される論文の数)の大小が雇用や採用に大きく影響するようになっています。特に、研究者に成り立ての若手教員は、研究室にとどまって懸命に論文を書かなければ、学者としての道が閉ざされてしまいます。地域に入り込んで長い時間をかける必要があるような研究課題は、徐々に倦厭されていくかもしれません。
私のような学者の活動スタイルは絶滅危惧種なのかもしれません。このような環境で、若手研究者を実践的な観光研究の世界に導くにはどのような戦略が必要となるのか、学界やシニア教員陣はこれに答えを用意する必要があります。























 観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】
観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】