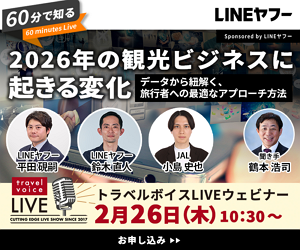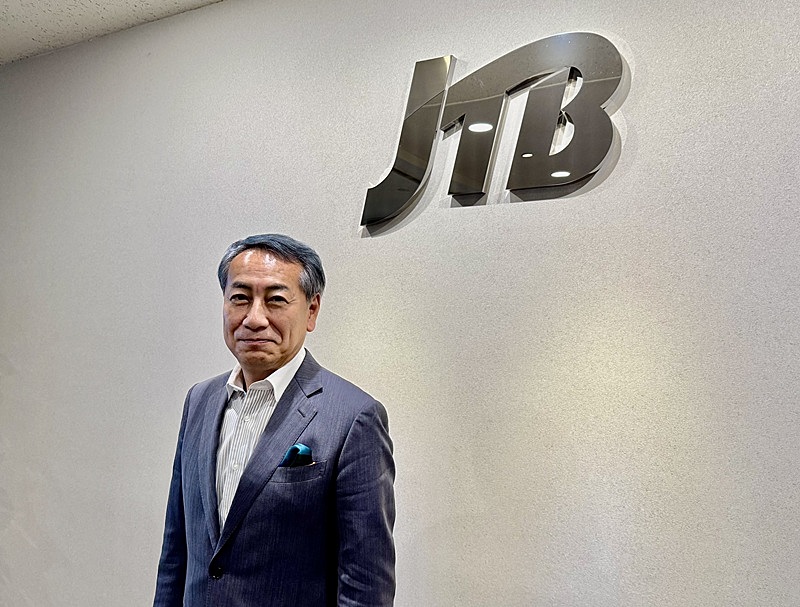
未曾有のコロナ禍で直面した経営危機を経て、かねてから掲げてきた「交流創造事業」の考え方をさらに深化させているJTB。売上高は、2024年度、2025年度決算の2期連続で1兆円を超えた。人と地域、組織、そして未来を「つなぐ・つくる・つなげる」理念のもと、事業を拡大するなかで、成長著しいのがグローバル領域だ。将来的には、グローバル領域の事業で営業利益の50%を稼ぐ考えも示している。
グローバルDMCやMICE展開を着実に進める一方、同社の新たな基軸として打ち出したのが「インテリジェンス」だ。ツーリズム産業における知見と情報を経営マネジメントに生かす取り組みである。JTBは2025年8月29日、観光産業B2Bメディアの世界最大手Northstar Travel Group(ノーススター・トラベル・グループ/NTG社)を買収し、独立した完全子会社として運営していくと発表。これまでにないツーリズム、そして交流を生み出す原動力にしようとしている。
NTG買収によってJTBが描く未来と、グローバル事業の飛躍とは? JTB代表取締役社長執行役員の山北栄二郎氏に話を聞いた。
世界の知を結び、ツーリズムの価値を高める
JTBが完全子会社化したNTGは、世界のツーリズム産業向けに最新ニュースやトレンド、マーケティングソリューションを提供する、業界トップのBtoBメディア企業だ。「Travel Weekly(トラベルウィークリー)」「Business Travel News(ビジネストラベルニュース)」「Phocuswire(フォーカスワイヤー)」などの14のメディアブランドを保有し、デジタル・ソーシャルメディアと13カ国で開催する100以上のイベントを通じて130万人以上の業界関係者とつながっている。
また、観光産業に特化したメディアやイベント運営に加え、調査・情報部門も保有している。その中でも中核をなすのがPhocuswright(フォーカスライト)だ。同部門は、観光産業の動向に関する信頼性の高いデータと分析を提供し、世界の観光関係者の意思決定に大きな影響力を持っている。さらに、世界の観光リーダーが集う国際会議「Phocuswright Conference」を主催しており、この会議は世界の観光における最新トレンドや知見が集約される重要なプラットフォームとなっている。
「コロナで人の動きが世界中で止まってしまったことで、ツーリズムは不要不急とされ、基幹産業になり切れていなかったと痛感した」と山北氏は振り返る。サステナブルをはじめ、生産性の低さや労働条件の厳しさ、オーバーツーリズムといった課題は常に意識していたが、あらためて、旅や交流の価値が論理的・科学的に十分に可視化されていない現実を突きつけられた。本来はボーダレスに文化や人をつなぐ産業であるにもかかわらず、世界の変化や議論が日本には十分に届いていない。そうした閉塞が、危機下で日本のツーリズム産業の限界を浮き彫りにした。
「旅行会社だけでなく、航空、鉄道、ホテル、レストランなど、関わるすべての事業者がグローバルな知見を取り入れ、学び合いながら持続的に成長していくためには、新たな基軸として“インテリジェンス”を加えることが必要だと考えた」。世界の知を結び、ツーリズムの価値を理論的に裏づける力を模索したことが、NTG社に着目するきっかけとなった。
もうひとつがテクノロジーの進化だ。「インターネットの普及によって、旅行の検索や予約、体験のプロセスは格段に便利になったが、産業全体の付加価値は必ずしも上がっていない」。NTG社はデジタルやソーシャルメディア分野にも強みを持つ。今後AIが主役となる時代に入り、いかにテクノロジーを活用して産業を高次化できるかを見据えた判断でもあった。そして、NTG社との連携を深めるユニットとして、Global Tourism Intelligence事業を立ち上げた。
交流そのものがメディアの力を発揮する
グローバルな知見や情報を得ることは、JTBのシンクタンクであるJTB総合研究所を「世界のツーリズム産業におけるオピニオンリーダー」へと育てるための一歩でもある。従来、日本の旅行動向を発信してきたJTB総研を、今後、世界のトレンドを俯瞰し、ツーリズムをより良くしていくための情報を積極的に発信していく組織に変化させる。それによって、自社の研究機能を高めるだけでなく、グループ全体、さらにはツーリズム産業全体の価値創造につなげたい考えだ。
さらに、グローバルイベントやネットワークに強みを持つNTG社のノウハウも生かしながら、ツーリズムに関わる企業や地域、さらには異業種のプレーヤーを巻き込み、産業全体を牽引する新たな仕組みをつくっていく。そこには、交流そのものを“メディア”ととらえる発想もある。「リアルな場に新しい関心や課題意識を持つ人々が集まり、そこに企業や自治体が関わることで新たな価値が生まれる。その場こそが、情報を生み出し、社会を動かすメディアとして機能する」と山北氏。JTBはグローバルな舞台でも、まさに交流創造の可能性を広げようとしている。
AIやデータ活用も、単なる効率化のためではない。世界の動向を読み解き、ツーリズムの未来を構想する“インテリジェンス”を高めるための手段だ。山北氏は、「NTG社のデータをそのまま取り入れるのではなく、あくまで独立したユニットとして運営してもらう。それによって得られる知見や考え方が、これからのビジネスをつくるうえで大切だと考えている」と語る。
JTBグループの社員に対しては、NTG社とのつながりも契機に、海外イベントへのより積極的な参加やグローバルなネットワーク構築の機会を提供する。「日本人にとってネットワーキングが苦手な部分もあるだろうが、実際のビジネスを通じて関係をつなげる経験を積むことで、人財としての力を高められることを期待している」。すでに国籍問わず、多様な部門に参加できる制度を整え、日本でキャリアを積んだ後に海外拠点での経験も可能にしているという。
山北氏はさらに、「たとえば日本国内でビジネスを担当しているとしても、社員一人ひとりが世界を意識し、情報感度やアンテナを高く保つことによって、グローバルな交流創造や事業拡大につなげてほしい」と力を込めた。
 グローバル事業について語る山北氏
グローバル事業について語る山北氏
数ではない、セグメントごとに圧倒的な力を発揮していく
グローバル事業においては、世界各地域の競合やパートナーとの関係を見極めつつ、単独での拡大だけでなく、戦略的なパートナーシップを強化していく。一例として、ヨーロッパのクオニイツムラーレ(KT)とJTBアメリカスグループの一員として設立されたTPIグローバルのネットワークを統合して北米市場におけるDMCリーダーシップの確立を図っているように、「競争環境は常に変化しており、単に規模で勝つのではなく、セグメントごとに圧倒的な強みをつくることが重要」と強調。必要に応じてM&Aをおこなったり、パートナーとの連携を柔軟に設計したりしながら、各地域・セグメントでの存在感を高める方針だ。
グローバルな倫理観と共通理念の共有も意識する。「地球を舞台に、人々の交流を創造し、平和で心豊かな社会の実現に貢献する」とのJTBの経営理念は、どの地域・事業においても共通の基盤となる。山北氏は「事業展開の基本は、どこでも‘つなぐ’という価値創造の源泉にある」と語る。
もちろん、AIやデータ活用も重要な柱だ。現在、専任チームを置いて情報を蓄積・分析するとともに、社員が日常的にAIチャットを活用できる仕組みを整えている。「AIで生まれた時間を、より創造的な活動に振り向けることが、人財育成やインテリジェンス向上につながる」。社員には国内外問わず、グローバルな視点を持ち続け、ネットワーキングやイベント参加を通じて実践的な力を養う環境を提供していく考えだ。
加えて、グローバル事業の最終目標は、利益創出だけでなく、グループ全体の安定した事業ポートフォリオを形成することにある。国内事業の重要性は維持しつつ、海外展開を強化することで、事業面・カルチャー面のバランスを保ち、ダイバーシティ推進にもつなげていく構えだ。
山北氏は長年の海外経験で培った視野とネットワークも活かしながら、コロナ禍で停滞したツーリズム産業の立て直しに取り組んできた。「人々の旅や交流の価値を再び社会に届けたい」という思いが、社員一人ひとりにも伝わり、世界の知見やトレンドを積極的に取り入れる姿勢を育んでいる。こうした経験と理念が、単なる経営判断にとどまらず、ツーリズム産業全体の未来を見据えた発展戦略へとつながっている。
聞き手:トラベルボイス編集長 山岡薫
記事:野間麻衣子























 観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】
観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】