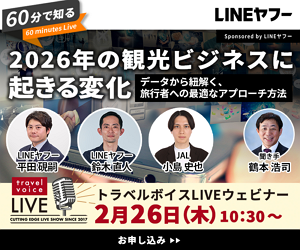国学院大学観光まちづくり学部の井門です。
今回は、大学生をはじめとする若い世代を、どうすれば海外旅行に向かわせることができるかについて考察したいと思います。
パスポート保有率に着目すると、全世代平均である17%であるのに対し、20代は53%と高く、海外旅行には出かける機会が比較的多い層です。しかし、大学では、年々学生が海外旅行への関心が低くなっている実感があります。これは、他大学の先生方も同感のようです。「車は持たないけれど運転免許は取っておこう」「海外旅行の予定はないけれど、パスポートは取っておこう」という心理も働いているようです。
現在の学生と海外旅行
学生たちの海外旅行への関心が低い理由は、いくつか考えられます。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響が、そのひとつです。高校の3年間、行動制限を受けた世代が現在の大学生です。彼らの多くが修学旅行に行くことができず、実施された学年でも行き先は国内に変わりました。家族旅行も同様です。小・中学生時代に海外家族旅行に行く機会も失いました。コロナが海外旅行経験を奪ったことが、海外旅行を身近に感じられない大きな要因であることは間違いありません。
また、海外旅行は金銭的負担が大きい点も、学生たちが必ず主張する理由です。日本人の実質賃金は30年間も上がっていないので、若い世代がそのような感覚を持つのも仕方ありません。将来不安から老いも若きも、企業まで、消費や投資をせずに貯蓄に勤しんでいます。日本人は不安遺伝子が他国民より高いという研究もあります。こうした貯蓄優先思考は、先々の不安から自分自身を守るためであり、経済的、社会的なセーフティーネットなき国民の防衛本能が、旅を遠ざけているように思います。
さらに、学生たちは常に「時間がない」と言っています。1987年の労働基準法改正で勤務上限が週48時間から40時間へと減り、働き方改革も進み、労働者の休みは増えているはずです。一方で、賃金の伸び悩みや労働者確保のため、非正規雇用が常態化し、学生もアルバイトの出勤を強く要請され、アルバイトを最優先するようになりました。所得税扶養控除の上限が103万円から150万円に引き上げられたことも、彼らのアルバイト意欲をさらにかき立てたと思います。お金は貯まる一方ですが、家族や友人と旅に使う時間は、より減ってしまいました。
そして、推し活をはじめとする旅行以外の消費へのシフトが究極の理由とも考えられます。多くの学生が「日本で十分楽しい」という理由を語ります。すなわち、海外旅行より楽しいこと、やりたいことがたくさんあり、海外旅行の優先度が低いままなのです。そうした推し活やアルバイトでの多忙さから、友人同士の共通の時間を確保することが困難です。1日でも予定を合わせるのが難しい中、海外旅行のための1週間を捻出、調整するのはほぼ不可能に近いと考えているのではないでしょうか。
若者に刺さる旅の提案とは
では、こうした若者をどうすれば海外旅行に向かわせることができるでしょうか。それは、大人向けマーケティングとは異なるアプローチが必要です。
よく「映え」が大切と言われますが、必ずしも旅の動機づけにはならなくなっています。旅行先で「映え」を意識することはあっても、日常生活でSNS映えする写真を見ただけでは行動につながりにくいのです。特に、非日常の映え写真よりも、日常のありのままの発信を好む「Be Real世代」は、むしろ映えや匂わせ画像を避ける傾向があります。インフルエンサーの発信や映えが有効なのは、30~40代以上ではないでしょうか。現在の大学生は以前よりSNSでの発信に以前ほど熱心ではなく、他者の発信より大切にしているのは、日常の自分自身のアイデンティティなのです。
また、ガイドブックや雑誌、地図もほとんど見ません。旅行会社のパンフレットなどは、手に取ったこともないのではないでしょうか。アナログ資料を目の前に置いても、ささっと眺めるだけで読みません。大学でレポートも参考文献はほぼWebサイト、ノートもめったに取らず、メモはスマホ、テレビも見ず、必要があれば無料配信サービスのTVerで十分です。動画は倍速再生があたりまえ。自分の好きなことに費やす時間を優先するためのタイムパフォーマンス(タイパ)追及は、デジタルネイティブ世代の生き方そのものです。
「成長」や「仲間意識」を鍵に
日常優先の彼らを海外旅行に誘うには、どうすればよいでしょう。それは、自分ごとに落とし込むこと、そして仲間意識を活かすことです。
この世代は、コロナ禍の影響もあり、成長願望が強い傾向があります。そのためか、海外旅行が自己成長につながる意味、意義があれば動きます。この旅行に行くことで、自分が成長できると思えば、初めて行動に移します。これまでの「観光」の文脈とは少し違います。少し功利主義の傾向がありますが、意味さえあれば、海外に向かいます。あるいは、多少観光要素が強くても、仲間と一緒に行ければ、それでも大丈夫です。個人同士では都合が合わずに出かけられないものの、ツアーを企画する第三者が前もって半年以上前に提案しておけば、お互いの都合を合わせることができます。数か月前程度では、予定が入ってしまうので、もっと早いタイミングで提案するのです。そしてお互いのキャンセルに抑止力が働く仲がよい友人同士、または大学のゼミやクラスといった強制力のあるグループが理想的です。
コンテンツとしては、たとえば、海外の社会施設や観光現場でのボランティアやアクティビティを通じた、成長につながるインターンシップなどです。日本では経験し得ないプログラムも必要です。そこで何かを乗り越えた経験があれば、社会に出た時に活かせると思うとともに、就職活動で使う大学時代のエピソードにもなり得ます。TOEICの点数アップに向けたトレーニングにもなります。
そうした実益を理解でき、さらに仲の良い友人たちと旅ができれば、喜んで海外旅行に向かうのではないかと思います。
その際、社会人向けのような旅費では却下されます。アジアでは20万円程度以下、欧米でも30万程度以下くらいが理想です。そのためには、格安ゲストハウスや路線バス、LCCなどを使う必要もあり、大手旅行会社やオペレーターでは商品化しにくいかもしれません。若者と共創する形の受注型企画旅行(パッケージツアー)として進めるのが理想でしょう。こうした商品をプログラム化し、目的に向かって「赤じゅうたん」を敷いてあげれば突破口が開けると考えています。
次回は、カンボジア、タイ、ベトナム各国でのプログラムの実践事例を紹介します。
























 観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】
観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】