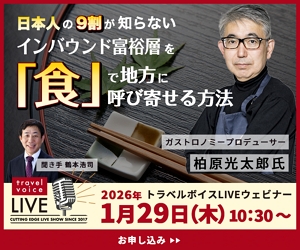訪日インバウンド客数は、2024年に過去最多の約3700万人に達し、2025年も単月で過去最多の記録を塗り替え続けている。1~6月までの段階で累計2000万人を超え、7月までの累計では2495万5400人となった。国が目標として掲げる2030年6000万人、消費額15兆円に向けて成長が続いている。
こうした日本のインバウンド観光政策を推進する中核組織として位置付けられているのが日本政府観光局(JNTO)。正式名称は「独立行政法人国際観光振興機構」だ。その歩みは、訪日市場拡大の軌跡でもある。国際観光振興機構がまだ特殊法人だった1994年(平成6年)から同組織で訪日プロモーションに携わるJNTO理事の伊与田美歴氏に訪日プロモーションの黎明期から成熟期の振り返り、未来を見据えた今後の取り組みについて聞いた。
国際観光振興機構から日本政府観光局へ
国際観光振興機構の前身である国際観光振興会が特殊法人として設立されたのは1964年。日本交通公社(現JTB)が民営化され、日本観光振興協会の前身である社団法人日本観光協会が設立された時期と同じだ。伊与田氏が同会に入った年の訪日外国人数は346万人で、現在の1ヶ月分ほど。1357万人の日本人海外旅行者数とは1対4という状況だった。
当時の国際観光振興会の海外事務所は13カ所。市場別で見ると、アジア市場が米国を逆転する状況だったことから、伊与田氏は「欧米にある事務所を閉めて、これから伸びていくアジアに海外事務所を開いていく時代だった」と振り返る。
2003年(平成15年)には、国際観光振興会が独立行政法人として国際観光振興機構に移行。当時の小泉内閣が「観光立国宣言」を打ち出し、訪日外国人旅行者を2010年までに倍増させることを目標に「ビジット・ジャパン・キャンペーン」が始まった。伊与田氏は「国として、インバウンドにしっかりと予算をつけて、観光全体を盛り上げていこうという時期。私たちにとっても大きな転機となった」と話す。
海外プロモーションの強化では、前年の2002年に日韓で共同開催された「FIFAワールドカップ」も大きなきっかけになった。JNTOでは1995年に開設した英語版のウェブサイトを順次、アジアの言語に展開していたが、この年には対応言語を10言語に拡大。多言語でのデジタルプロモーションが本格化した。
「日本政府観光局」の呼称が使用されはじめたのは2008年7月。その前年には、観光立国推進基本計画が改定され、国際観光振興機構について「外国人観光客の来訪促進の中核を担う、我が国の政府観光局として位置づける」という文言が入った。それを契機に、対外的なブランディングとして、国内では「日本政府観光局」、海外では「Japan National Tourism Organization: JNTO」のもと情報発信の強化を進めた。
伊与田氏は、「当時のミッションは、今と基本的には変わらない。環境が変化し、手法が異なる部分はあるが、日本の魅力を海外に訴求して、日本に来ていただくということ」と力を込める。
 インバウンド市場の変遷を見てきた伊与田氏
インバウンド市場の変遷を見てきた伊与田氏
拡大する日本政府観光局のビジョン
伊与田氏は、日本政府観光局としての歩みの中で大きな転機となった出来事として、2015年にビジット・ジャパン・キャンペーン事業の執行機関が日本政府観光局となったことを挙げた。予算を持ち、実際にキャンペーンを主体的に動かすことができるようになったということだ。それによって「海外目線で機動的にプロモーションを行うための体制が取れるようになった」という。
この当時を振り返ると、訪日客数は2010年までの目標1000万人に向けて、800万人台まで増加していたが、2011年の東日本大震災で大きく落ち込み、2013年になってようやく1000万人を達成した時期だ。
日本政府観光局のロゴを一新して、経営理念を打ち立てたのもこの時期。2015年にビジョンとして、「国民経済の発展」「国際的な相互理解の促進」「地域の活性化」「日本のブランド力向上」を掲げた。伊与田氏は、「国の戦略の中で大きな転機を迎えていた時期に、内部でも職員の意識や価値観を統一する機会になった」と明かす。
経営理念策定にあたっては、「若手職員が自主的な勉強会を開き、業界からの意見も汲み上げながら作り上げて、経営側に承認してもらった」。その伝統は受け継がれ、現在でも毎年、若手職員が中心となって、プロジェクトチームが組織され、経営理念の浸透について議論する場を設けているという。今年は経営理念策定10年目にあたることから、「これが時代に合っているのかどうか、経営サイドと職員とで考えていく時期」と話す。
現在、日本政府観光局の海外事務所は26カ所に拡大。体制は1室5部1総室制となり、職員も223人(2025年4月現在)まで増えた。また、海外事務所には現地採用の職員、民間企業や自治体からの出向者も受け入れている。同じ方向性を向いて事業を進めていくことがますます重要になっている。
地方誘客に向けて地域との連携、ますます重要に
一方、伊与田氏は、今後の課題も指摘する。その一つが、国内でのJNTOの知名度だ。「旅行業界には名前を知っていただき、一緒に活動していただいていける場が増えてきたと思っているが、一般的にはまだまだ努力が必要」との考えを示す。知名度不足の解消に向けた取り組みとして、2020年8月に広報グループを立ち上げた。
また、東アジアではナンバーワンのデスティネーション、欧米豪でも人気ランキングで上位に入るなど日本の観光ブランド力はここ数年で確立されつつあるが、「地域のブランド力を高めていく点ではまだ課題がある」との認識を示す。
2030年の訪日外国人6000万人、消費額15兆円に向けて「地方への誘客は必須」。しかも、オーバーツーリズムなどを避けながら持続可能な形で達成していく必要がある。ビジョンの一つとして掲げている「国民経済の発展」も、ここ10年で、その質が変わってきている。伊与田氏は「従来から各市場別にターゲットや訴求コンテンツなどを訪日プロモーション方針として公表してきたが、2023年からは新たに『訪日マーケティング戦略』として、何を誰に届けるというところを深掘りし、地域と共有しながら、協業してプロモーションしていくように心がけている」と強調。「日本政府観光局としても国内の関係者との密接な連携が、ますます大事になってきている」と付け加えた。
さらに、伊与田氏は、危機発生時の観光の回復力を高める「観光レジリエンス」についても言及。活動の主体ではないものの、「インバウンドの安定的な成長を支えるため、戦略的に市場の分散化を図っている」との考えを示した。JNTOでは、災害時の訪日外国人へのSNSなどでの情報発信も強化し、24時間コールセンターも設置した。
このほか、観光振興という側面で大阪・関西万博への期待も大きい。万博を契機とした訪日外国人の地方誘客のほか、「日本のSDGsや持続可能な取り組みをアピールする機会にもなる」と日本のブランド力向上にも期待をかける。低迷が続く日本人の海外旅行市場への刺激にもなることから、「万博は、旅行に対する波及効果は大きい」と位置付けた。
「これからの10年は、これまでの10年とは違うものになる」と伊与田氏。「これからは本当に世界トップクラスの観光立国を目指していく段階」と力を込め、その目標に向けて地域や事業者に対して「ぜひ日本政府観光局を利用してほしい」と呼びかけた。






















 観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】
観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】