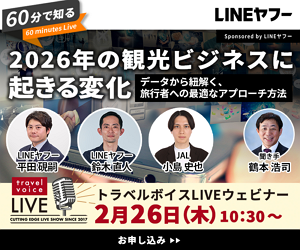東京都立大学観光科学科の清水です。今回からトラベルボイスでコラムを執筆することになりました。記念すべき初回のテーマとして、観光産業の人材育成を取り上げ、思うところを述べたいと思います。
私が所属する都立大観光科学科は、2018年4月に設置された日本で唯一の「理系」の観光関連学科です。教員は、ほぼ全員が元々観光学を専門としておらず、都市地域計画、土木計画学、環境学、生態学、農学、造園学、地理学、情報学などの専門家で構成しています。1学年の定員は30名と弱小集団ですが、産業や行政においてデータや科学的分析に基づく観光EBPM(証拠に基づく政策決定)を推進する貴重なトップマネジメント人材を輩出したいと考えています。
大学の観光関連学科の現状
そもそも、2000年までの日本では、学科や学部レベルで観光を学べる大学は数校しか存在しなかったようですが、2001年以降に都立大を含め、多くの大学で観光関連学科・学部が設置されました。日本交通公社が発行する旅行年報では、2023年度で46大学に観光関連学科があると整理されています。定員は合計で5000名以上になると考えられ、このうち3割が観光産業に従事すると仮定すると、これから10年間で1万5000人以上の観光を学んだ担い手が産業に参入する訳です。
今後期待するインバウンド需要の伸びを想定すれば、これは非常に心許ない人数だと考えられるかもしれません。給与水準が相対的に低いと考えられている観光産業ですが、それが平均的な産業よりも高くなれば、より多くの卒業生が産業に就職するようになるでしょう。あるいは、最近の学生のマインドを考えると給与水準は決して高くなくとも地域コミュニティの中での様々な交流を通じて幸福感が得られるのであれば、それに魅力を感じて観光地に移住して産業に従事するような流れも期待できるのかもしれません。
今、観光産業に従事する方々には、より多くの卒業生を送り出せる産業として魅力的な就業環境にして頂きたいと思います。
今でもはっきりと覚えている出来事があります。10年以上前のある研究会で旅行会社勤務から大学教授に転身された方が「観光業は儲からない」と発言されました。それに対して、私は即座に手を上げて「観光学の先生がそんなことを言ってはダメだ」と怒りを表明したことがあります。一方で,「儲からなかったのは事実かもしれないので,これから卒業生に自信を持って産業に入ってもらうためにはどうしたらよいのだろうか?」と考えてしまいました。
それから約5年後に日本観光振興協会で非常勤職員として関わることになり、旅行・運輸・宿泊などの民間企業からの役職の出向者が多くいる職場で、出向元企業の経営状況や戦略を理解することも可能になりました。これらの経験が、これからの観光産業におけるビジネスモデルを考えてもらうような講義を設置したり、インターン系講義に力を入れたりするきっかけになりました。
人材育成の講座・プログラムの課題
現在、観光産業に従事する方々で、過去に海外で観光・ホスピタリティ学を学んだ経験のある方はごく一部です。その他の多くの方々は、観光学そのものを学んでいません。そこで,観光MBAプログラムやリカレント教育プログラム、社会人対象の研修プログラムなどを受けて頂き、最新の観光・ホスピタリティ学を理解してもらうことが重要だと考えています。動画コンテンツを含めて、全体像を把握できないほど多くのプログラムが提供されていますので、読者の皆さんも何かしら受講されたことがあるのではないでしょうか。
私自身は、2017年頃から恒常的に国、自治体、民間が提供している多くの観光関連の人材育成講座プログラムに講師として協力しています。また、東京都産業労働局観光部からの委託で人材育成に関する調査研究を定期的に行い、その成果を活用してこの8年間講座企画・提供を行ってきました。そして都立大と日観振の共催で、観光産業の将来のトップ人材を育成する「観光経営トップセミナー」の企画責任者も8年間に渡って担当してきました。これらの経験から、人材育成の講座やプログラムには、次に述べるような課題があると感じています.
第一に、一部の講座プログラムが「成功」とされている事例をつまみ食いするだけのものとなっていることです。これは,「成功事例が知りたい」というアンケートでのニーズが多いことが一因だと考えていますが、1時間くらいの話を聞いて成功事例をまねできるのなら誰も苦労しません。そもそも、現時点では「成功事例」である理由が体系的に整理されていない(成功判定が単なる企画側の思い込みや、他者の評価を鵜呑みにしているだけのことが多いと感じます)ので、役立つとも思えません。観光経営トップセミナーでも、安易に成功事例の情報を求める受講者が少なからずいて困惑しています。
第二に、一時的に予算が付いたような講座プログラムが乱立したことです。例えば「ワーケーション」など、企画時の旅行市場内の「流行」に著しく偏った賞味期限の短い内容が散見されました。このような講座は、市場動向やコンテンツ・商品開発の基礎の知識を学ぶ前に聞いても意味がないと感じます。
第三に、これを一番改善しなければいけないのですが、講座プログラムの企画・運営業務の外部委託のための仕様書が適正に作成されないなど思いつきレベルの域を出ない講座が散見されることです。講座プログラムの企画を命じる行政・企業の部局責任者や、実際に企画する実務担当者のいずれもが観光・ホスピタリティ学の基礎を理解していないために発生します。講座の仕様の要求内容と受講者層が整合しない無謀な講座プログラムもあり、参加者が思い通りに集まらずに動員をかけることになることもあります。これに付き合わされる受講者はたまったものではありません。
本当に役立つ人材育成プログラムとするために
では、どうすればよいのでしょうか?
私は、以下の3つが重要だと考えています。
- 日観振を中心とする全国組織が主要な観光関連学会とタッグを組んで、講座プログラムを体系化し、国や自治体等が企画する同じような内容の講座が乱立しないようにすること
- コンソーシアムのもとで、主要大学がそれぞれの強みを生かしたリカレント教育プログラムを設置して連携すること
- これらの流れを観光庁が恒常的に予算化したり、受講者にメリットがあるような認定制度(例えば補助金事業の採択要件に含めるなど)を導入したりすることで後押しすること
私自身、同じような内容の講座依頼を国や自治体から受けることがあります。1については、本当に切実な思いを持っています。読者の皆さんも、学びの質の低い講座プログラムには是非厳しい意見を出して頂くとともに、「成功」事例に安易にすがらないように意識して頂きたいと願います。
























 観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】
観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】