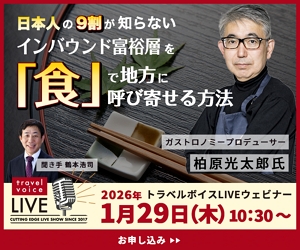BtoB向け観光商談展示会「iTT国際ツーリズムトレードショーTOKYO 2025」では、医療ツーリズムに関するセミナーがおこなわれた。「医療インバウンドの未来戦略:政策の方向性と現場からの市場展望」をテーマに、経済産業省商務・サービスグループ ヘルスケア産業課係長の栂香菜子氏が、国の医療ツーリズム政策を説明。国際メディカル・コーディネート事業者協会(JIMCA)理事の坂上勝也氏が現場での課題やニーズ、今後の市場可能性を語った。
医療インバウンド受け入れに向けた4つの取り組み
経産省の栂氏は、医療渡航市場について解説した。
全世界の市場規模は約10兆円、渡航人数は2000万人を超える。一方、日本への医療渡航者数は2019年で2~3万人にとどまっている。タイの360万人、韓国の49万人と比較するとその差は大きい。
経産省が中国、ベトナム、インドネシアに対して実施したアンケート調査によると、日本で受けてみたい治療や検診内容でトップは3カ国とも「人間ドック」。このほか、中国では「眼科治療」「セカンドオピニオン」、ベトナムでは「整形外科治療」「循環器疾患治療」、インドネシアでは「眼科治療」「セカンドオピニオン」のニーズが高いことがわかった。
このような中、栂氏は、医療インバウンド政策として、医療渡航患者の受け入れに向けて、身元保証機関登録制度の運用、日本の医療の強みの発信、身元保証機関となる事業者の質の担保などに取り組んでいると説明。そのうえで、「医療インバウンドを受け入れることで、日本の医療の発展、医療機関の経営力向上、富裕層などの呼び込みによる外貨の獲得、日本ブランドの価値向上を目指している」と話した。
「医療滞在ビザ/身元保証機関登録制度」では、医療滞在ビザを発給するために、身元保証機関から身元保証を受ける必要があり、観光庁と経産省が、身元保証機関の登録審査をおこなっている。登録身元保証機関は、2024年11月現在で183件。
医療滞在ビザは、最大1年有効で、1回の滞在は最長90日間。数次ビザは、必要に応じて最大3年まで延長することができる。発給件数は、一時、コロナ禍で激減したものの、2011年に創設以来、増加を続けており、2023年は過去最多の2294件だった。国別にみると、全体の6.5割が中国、ついで3割がベトナム。近年はベトナムでの発給が増加しているという。
2つ目の取り組みが「医療渡航支援企業や医療機関の認証」。海外からの患者を意欲的に受け入れたいと考えている病院や質の高い医療渡航支援事業者に対して認証を行っている。認証医療渡航支援企業(AMTAC)は、現在、正認証がJTBなど4社、準認証企業が2社。認証の要件には、旅行業の登録も含まれる。一方、渡航受診者を積極的に受け入れる医療機関の認証(Japan International Hospitals: JIH)については、2025年4月現在で43院が認証を受けている。
3つ目の取り組みが情報発信。日本の医療の強みや医療提供体制などについて、パンフレット、ウェブサイト、展示会などを通じて情報を発信している。栂氏によると、インドなど、近年一般のインバウンド旅行者が増加している地域でも、日本の医療ツーリズムはほとんど認知されていないという。
4つ目の施策として、キーパーソンや現地の主要医療機関と連携を強化し、医療インバウンドでの送客拠点構築を目指している。
このほか、国際メディカル・コーディネート事業者協会(JIMCA)が、医療インバウンド受け入れのサービス充実と品質向上を目的に、事業者向けにガイドラインを策定していることも紹介した。
医療インバウンド受け入れ、4つの課題
JIMCAの坂上氏は、医療インバウンドの課題について指摘した。
JIMCAは、医療インバウンドのコーディネートを行う事業者の業界団体。ガイドラインの策定のほか、勉強会、情報交換、政策提言などを行っている。
まず、坂上氏は、治療の問い合わせ後、在留資格を取得し、国民健康保険に加入することで、高額療養費を賄うという事例が報告されていると指摘。「日本の医療費の無駄につながる」として、国民健康保険の加入条件を見直し、不適切利用を防ぐ仕組みづくりが必要と訴えた。
次に、競合国と比べて医療滞在査証手続きが煩雑な点も改善の必要があるとする。例えば、韓国やシンガポールでは特別なビザは必要ない。「早く治療を望むニーズに対応できず機会を損失している」と指摘した。
また、医療機関の受入体制改善も挙げた。「日本の医療もホスピタリティは高いが、医療インバウンドの求めるサービスは質が違う、病室、通訳の配置、食事などのサービスも充実させていく必要がある」と話した。また、患者紹介の仕組みが医療インバウンドには馴染まない点を挙げ、「コーディネーターがビジネスとしてまとめていかなければならない」と続けた。
このほか、海外から問い合わせは多数あるものの、受入率が低いという課題もあるという。見積もりだけで終わり、他国へ需要が流れるケースも珍しくない。坂上氏は、「問い合わせが本気かどうかを見極めるためにもコーディネーターの役割は重要」と強調した。
坂上氏は、マーケット動向についても説明。医療滞在ビザの発給件数からも分かるように、中国以外では、ベトナムから来日する患者が増加。その背景には、経済成長による食生活の変化や長寿化があるという。JIMCAは昨年、ハノイ市保健局と日越における医療連携に関する覚書を締結。さらに、神戸大学医学部附属病院とベトナム国立統一病院は、学術交流協定を結び、教育・研究・臨床領域における交流や患者受入れなどで協力していくなど日越間で関係強化が進んでいる。
坂上氏は「ニッチな領域ではあるが、ニーズはある。官民一体となって医療インバウンドの受け入れを進めていくのが一番いいのではないか」と今後の展開に期待を込めた。






















 観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】
観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】