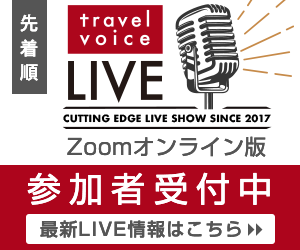法人向けにさまざまなICT事業を展開する「NTTドコモビジネス」。「産業・地域DXのプラットフォーマー」として、自律・分散・協調型社会の実現を目指している。観光産業とも親和性が高く、企業や地域が抱える課題の解決に向けて、さまざまなソリューションを生み出し、企業間・企業地域間で革新的な共創も仲介している。
NTTドコモビジネスが取り組む観光産業のDX、見据える観光の未来を同社ビジネスソリューション本部事業推進部グロースマーケティング推進室室長の徳田泰幸氏に聞いてみた。
課題解決を支援する産業・地域DXのプラットフォーム
NTTドコモビジネスは、2025年7月1日にNTTコミュニケーションズ(NTT Com)から社名変更をしたところだ。その背景として、徳田氏は「モバイル領域、ソフトウェア領域も含めた形で、統合的なICT事業を展開していくなかで、新しいステージでチャレンジしていくため」と説明する。今後は、大企業だけでなく、中小企業約180万社もターゲットに、幅広い価値を提供していくという。
中小企業もターゲットにすることで、「地域の活性化がキーワードになってくる」ことから、観光領域での関わりも増えているという。「観光の消費額を増やしていくことで、町全体を活性化し、強いコミュニティを形成していく。その点でNTTドコモビジネスは役に立てる」と自信を示す。
NTTドコモビジネスが目指すのは、地域の自律・分散・協調型社会だ。その社会形成に向けて、「データの利活用、業務コンサルティング、セキュリティなど提供する産業・地域DXのプラットフォームとして、企業や地域が抱える課題を解決していく」考えだ。
また、徳田氏は、産業・地域DXのプラットフォーマーとしてのあるべき姿として、「サービスを売るだけでなく、どのようにすれば結果につながるか、顧客と一緒に考え、伴走することで提供価値を最大化していくこと」と強調した。
 「観光領域でもドコモデータの利活用を」と徳田氏
「観光領域でもドコモデータの利活用を」と徳田氏
ドコモの約1億会員の包括的データ
NTTの強みは、通信ビジネス事業者として顧客と長い関係性を築いていること。約1億会員を持ち、1つのIDでユーザーのさまざまなライフステージに関わっている。そのため、生活の変化を発見しやすい。また、特定のユーザー層に偏らず、ユニバーサルなデータが取得できることから、「地域全体、日本全体の統計データを網羅的に取得できる」ことも強みだ。
その強みを活かした事業に、NTTドコモの「モバイル空間統計」がある。1時間ごとの人口を24時間365日把握することができる人口統計として、さまざまな場面で活用されている。
人流データを測定すると、旅行者も含めて、その町にいる人たちがどのような動きをしているかが把握できる。そのデータは、次の打ち手に繋げる起点となる。徳田氏は「モバイル空間統計による把握だけで終わるつもりはなく、地域が持つデータを掛け合わせながら、どのように出口に繋げていくか、地域と一緒に模索している」と話す。
地域では、人の流れやその属性だけでなく、どこで何が消費されているのかが気になるところだ。それが把握できれば、ターゲットを絞ったより効果的なアプローチも可能になる。「データによって顧客接点を高度化していく。データから仮説を立て、その仮説からピンポイントで広告を打ち、収益につながるサイクルをつくれれば、本当に効果的な観光事業の運営ができるようになる」。
「地域創生では、観光はあらゆる事業者が絡むことから、中核的存在であるのは間違いない」と徳田氏。そのうえで、地域の経済が潤うだけでなく、「地方発のビジネス創出の機会もつくっていく」とし、それが「自律分散型の社会につながる」と力を込めた。
観光領域での取り組み、顧客接点の高度化を
NTTドコモビジネスは、観光領域でもさまざまな取り組みを進めている。そのひとつひとつの取り組みで顧客接点の高度化を目指すとともに、生成AIソリューションを観光領域で活用する取り組みも進めている。
そのひとつが「デジタルヒューマン」だ。まるで人間の様な見た目のバーチャルなキャラクターがゲストの趣味や嗜好を汲み取り、ゲストが求める旅行体験や滞在の実現をサポートする。例えば、観光案内所などタビナカでの顧客対応を想定している。
2025年1月に実施した名古屋のホテルでの実証では、ドコモ会員のデータに加えて、ホテルのCRMデータ、天気や営業時間などの第三者データ、地域独自のデータをもとに、ゲストのヒアリング情報を掛け合わせて、生成AIが行き先や滞在の方法をリコメンドする。多くのデータがあることで、生成AIによるリコメンドの精度があがる。徳田氏は「顧客接点で、かなり高度なコミュニケーションを目指していきたい」と意欲を示す。
現在は、タブレット上での展開だが、将来的には等身大のデジタルヒューマンやアプリでの実装も視野に入れている。発話も多言語に加えて、地域の方言で対応するなどローカライズも検討していく考えだ。
徳田氏は「現在でもチャットボットはあるが、逆に顧客体験を下げてしまっている部分もある。例えば、『今日はイベントがあって混んでいるから、こっちに行ったほうがいい』というようなリコメンドもできるようになれば、蓄積したデータを活用する意味が深まる」と話す。
 まるで人間の様な見た目のバーチャルなキャラクター「デジタルヒューマン」のイメージ。実在する社員をモデルに、話し方やトーン、身振りなどの「個性」を再現することで、本物の人間のようなリアリティを追求するという
まるで人間の様な見た目のバーチャルなキャラクター「デジタルヒューマン」のイメージ。実在する社員をモデルに、話し方やトーン、身振りなどの「個性」を再現することで、本物の人間のようなリアリティを追求するという
また、瞬時に顧客属性を捉えて、リアルタイムに最適な広告を出し分けるソリューションも開発した。モニターの前に立つと、その人の顔を認証し、データに基づいて、その人に合う広告を瞬時に映す。群衆と個人を見分けることも可能だ。ドコモのデータ、事業者のファーストパーティデータ、リアルデータなどさまざまなデータの連携でマーケティング精度を向上させることが可能になる。
「AIが最後の顧客接点を作り出すところが非常にエポックメーキング」と徳田氏。改めてデータの重要性を認識したという。実装に向けては、パフォーマンスのさらなる向上とマネタイズポイントの確保がカギになるという。
NTTドコモビジネスは、顧客接点だけでなく、観光産業のDX化でも生成AIの活用を見据えている。予約管理、販売戦略、人材不足対策など「バックヤードのプロセスを効率化させていくことは、観光産業を盛り上げていくトリガーになる」との考えだ。そのうえで、自律分散型社会を目指すためには、「自治体にスキル自体を残していく取り組みも必要になる」との考えを示した。
データドリブンの観光マーケティングで地域を強く
NTTドコモビジネスは、未来をひらく「コンセプトと社会実装」の実験場として「OPEN HUB for Smart World」を展開している。徳田氏は、その狙いを「さまざまな企業が混ざり合って、イノベーションを起こすこと」と説明する。
異なる企業が持つアセットを掛け合わせる共創プログラム。例えば、観光領域では、有力なコンテンツとなっているスポーツと地域振興とを掛け合わせる議論も進んでいるという。しまなみ海道周遊促進事業も、その共創のひとつの形だ。
2025年3月には、広島県観光連盟、NTTドコモビジネス、早稲田大学、インテージ、電通総研など産官学による広島県での観光実証実験が開始。インバウンド観光客の属性や流入ルート、周遊ルートなどをつかめず、効果的な施策が打てないという課題の解決に向けて人流データを分析した。
徳田氏は「地域の小さな企業と大企業との共創なども進めていきたい。観光の文脈でも、地域からさまざまな企業が参加することで、新たな流れをつくっていきたい」と意欲を示す。
観光DXについては、「デジタルを入れたから、DXになるのではない」と話す。観光マーケティングでは、統計による把握だけではなく、分析し、インサイトを得て、施策を打ち、効果が出るまでを見ていく必要がある。「先の世界をどのように作れるのかを意識することが大切」と徳田氏。NTTドコモビジネスは、地域の課題の洗い出し、マーケティング支援、新たな顧客体験を作れるところまで伴走していくという。
最終的には、地域の一人ひとりがアイデンティティを持ち、シビックプライドを感じて地域を運営していける自律分散型社会を形成していく。「大都市からの一方通行の情報の伝達ではなく、地域がフルメッシュでつながる世界観の構築に貢献していく」と徳田氏。「そうなれば、日本はさらに強い国になるのではないか」と未来を見据えた。






















 観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】
観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】