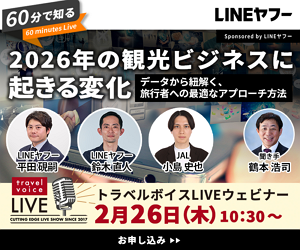インドネシア生まれ、東南アジア最大級の旅行プラットフォーム「Traveloka(トラベロカ)」が2025年5月、日本での事業を正式に開始した。6月からは東京・大阪エリアでテレビCMも投入し、存在感を示している。
東南アジア以外への進出は、2024年の豪州に続き、日本が2カ国目。日本から東南アジアへのゲートウェイを目指すと同時に、日本の国内旅行も取り扱うことでサプライチェーン強化を狙う。先ごろ、来日した同社社長のシーザー・インドラ氏(写真)に、トラベロカの強みと日本市場攻略への戦略を聞いた。
市場に合わせ柔軟な決済対応
トラベロカの本拠地であるインドネシアは、人口が約2億7000万人と東南アジア最大規模を誇り、その半分はデジタルツールを日常的に使う30歳以下が占めている。「当社の顧客層も、20~30代のデジタル世代が中心だ。初めての海外旅行という人も少なくないが、利用端末はモバイルがほとんど。インドネシアの場合、2014年以降、急激にモバイル・ユーザーが増え、これに伴い、トラベロカもモバイル対応の旅行アプリへとシフトした」とインドラ氏は話す。
現在、アプリの累計ダウンロード数は1億4000万回超、月間アクティブユーザー数は4000万人以上で、航空券、宿泊、鉄道、各種体験アクティビティなど、あらゆる旅行関連商品を取り扱うが、トラベロカならではの強みは、やはり東南アジアにおける圧倒的な品ぞろえだ。
決済サービスは50以上あり、日本進出を機に、新たにJCBが加わった。インドネシアでは独自の後払いサービス「T(トラベロカ)ペイレイター」を展開しており、ベトナムでは現地の金融サービスと連携した同様の後払い決済を提供している。一方で、クレジットカード普及率の高いシンガポールでは後払い決済は不要と判断するなど、進出先マーケットに合わせて柔軟に判断している。
コロナ禍では、それまでの成長拡大路線の見直しを余儀なくされたが、現在は「毎年、利益を出している。予約取扱高は前年比2桁増と好調に推移している」(インドラ氏)。
とはいえ、13年前、小さなアパートの一室で創業した当時は、航空会社の担当者に会うことすら難しかったという。「トラベロカに目を向けてもらうために、旅行者が感じていた困りごとの解決にひたすらフォーカスしてきた」と、インドラ氏は振り返る。
東南アジアのデジタル世代は「せっかち」
インドラ氏は、若いデジタル世代、なかでも東南アジアの同世代旅行者の特徴について、「興味関心の対象がどんどん変わること」を挙げる。「この旅行者層は、有名観光地だけでなく、もっと色々なところへ旅したい意欲が強いが、関心ある旅行先もすぐ変わる。一年前、よく売れたデスティネーションが、翌年も人気とは限らないため、刻々と変わるトレンド動向に即反応できるよう、幅広い取り扱い商品をそろえる必要がある」と指摘する。
もう一つの特徴は、せっかちで、待てないこと。「何か起きた時には、すぐに旅程変更したいという要望に応えるために、トラベロカでは、フライト変更や払い戻しの手続きを、旅行者がセルフ操作で完結できるツールの開発に多額を投じてきた」。現在、フライト変更および払い戻しについては、全体の9割がセルフ操作で解決できるようになり、ユーザーは電話やメールの手間がほぼなくなったという。チャットボットでの問題解決率は75%で、この数字をもっと上げて、より簡単でシンプルな使い勝手を実現することに取り組んでいる。
東南アジアが非常に間際予約の多いマーケットであることも、トラベロカにとっては、むしろ追い風の一つになった。「東南アジア域内の往来はビザ不要で、直前でも旅行の予定が立てやすいことが間際予約の一因。その際に生じる様々な弊害を克服できるソリューションを構築し、満足度の高いユーザー体験を提供したことで、トラベロカへの認知度が広がった。もちろん簡単なことではない」とインドラ氏。テクノロジーに投資して予約プロセスを最適化したり、パートナー企業から合意を得たりすることで一歩ずつ、前へ進んできた。
トラベロカでは社内に約1000人のエンジニアを抱えている。「我々の中核は旅行テック・カンパニー。旅行予約における困りごとを解決するテクノロジー提供会社と考えてもらってよい」(インドラ氏)。
インドラ氏は、旅行ビジネスについて「商品を販売するのはそれほど難しいことではない。問題は、むしろ販売した後だ」との見方を示し、予約体験の向上、手軽なスケジュール変更、スムーズなチェックインや旅行サービスの利用までを実現する旅行プラットフォームを目指している。
取材対応するインドラCEO
日本人の国内旅行も取り扱い
インドラ氏は「東南アジア発の旅行市場において、日本はずっと成長を続けているデスティネーション。インドネシアおよびベトナム発の2025年第1四半期の訪日旅行は、予約取り扱いベースで前年同期の倍に拡大している。トラベロカにとって、また東南アジアの旅行マーケットにとって、日本のサプライチェーン強化がますます重要になっている」と説明する。
一方、日本人の旅行取り扱いについては当初、海外旅行を中心に考えていたが、国内旅行マーケットの規模が大きいこと、ローカル・パートナーとの関係構築や仕入れ強化にも相乗効果が期待できることから、国内旅行もおこなうと決めた。
日本発の海外旅行では、「トラベロカが、日本人の東南アジア旅行のゲートウェイ」になることが目標だ。「我々の旅行プラットフォームは、東南アジアの旅行プロダクトの品ぞろえでは世界最大。13年かけて、宿泊からフライト、体験アクティビティまで、充実した幅広い選択肢、クオリティ、価格競争力、在庫数を揃えてきた」と自信を示す。同時に、クオリティを重視する日本市場への進出は、トラベロカのプロダクト全体のさらなる質向上にもつながると考えている。
新しいマーケット進出を成功させるカギは「ステイ・ローカル」。具体的には「顧客からのフィードバックを重視しながらマーケットへ最適化すること、そしてローカル・パートナーを獲得すること」と話す。日本の旅行産業のエコシステムを知り、全国各地でトラベロカのパートナーを増やすために、日本貿易振興機構(JETRO)や日本政府観光局(JNTO)に仲介役を頼み、旅行事業者や各自治体との関係構築にも力を入れていく。「国内旅行も取り扱うため、地域の旅行・観光事業者から金融機関、自治体まで、幅広いパートナーとの協力関係が不可欠になる」(インドラ氏)。
アプリを繰り返し使ってもらえるように
昨年、トラベロカは、日本を含む9か国で旅行者意識の違いを調査した。旅行プラットフォームの個人情報保護などセキュリティ対策に関する質問では、利用者から肯定的な回答(「まあまあ安心」62%、「とても安心」21%)が全体の83%を占めたインドネシアやシンガポールとは対照的に、日本は18%と低い結果になった。「旅行プランニングで最も使うデジタルツール」では、シンガポールが「旅行プラットフォーム」(53%)、インドネシアが「ソーシャルメディア」(56%)に対し、日本は「旅行ウェブサイト、ブログ」(36%)だ。
こうした調査データも考慮しながら、トラベロカは日本での顧客ベース獲得に向けて、「まずは日本人ユーザーからのフィードバックをよく分析していく。トラベロカのアプリをダウンロードした人が、その後も繰り返し利用してくれるようになることが第一の目標だ」とインドラ氏。「トラベロカで予約したから安心だ、というユーザーからの信頼を勝ち得て我々はここまで成長することができた。もちろん日本でも、同じことを目指していく」と力を込めた。
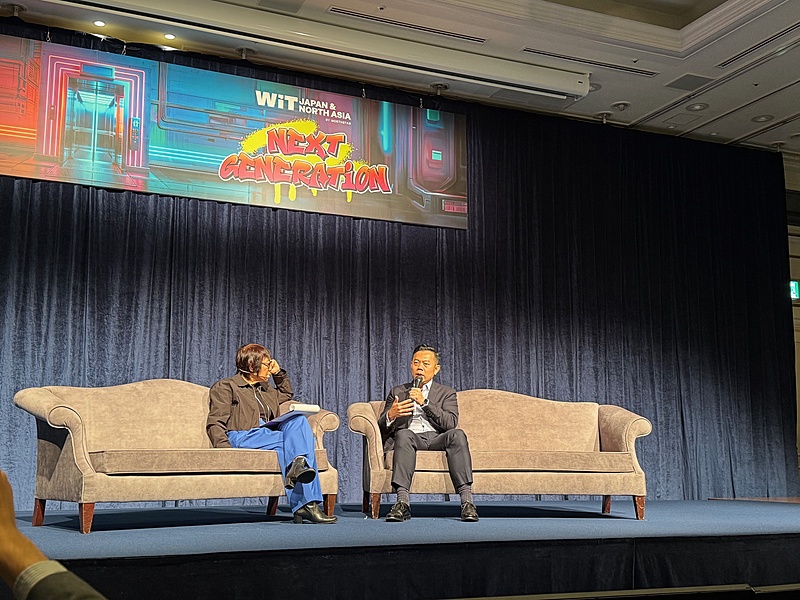 来日時は、旅行テックの国際会議「WiT Japan2025」にも登壇したシーザー・インドラ社長
来日時は、旅行テックの国際会議「WiT Japan2025」にも登壇したシーザー・インドラ社長
取材・記事:谷山明子























 観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】
観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】