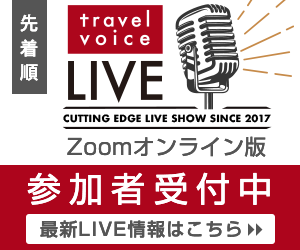2025年6月に開催されたBtoB観光商談展示会「iTT国際ツーリズムトレードショーTOKYO 2025」では、観光DXに関する各種セミナーも数多く開催された。そのうち、AICX協会代表理事で著書「生成AIの教科書」で知られる小澤健祐氏が「生成AIの教科書 ~生成AIで観光・宿泊業界はどう変わるか~」をテーマに講演。「作るAI」から「使うAI」へのシフトを背景に、生成AIがどのように観光産業における業務を革新するかを具体的な事例とともに解説した。
AIエージェントが手足となって実行する時代
小澤氏は、「AIエージェントを軸にした顧客体験が、これからどんどん進んでいく」と話す。小澤氏は、AIエージェントについて、大規模言語モデル(LLM)などの生成AIを核とし、特定の目的や継続的なタスクのために設計された自律的なプログラムであり、環境の認識、情報の処理、意思決定、行動の実行を一貫しておこなうことができると説明した。
言い換えると、「今までのAIが『頭脳』だったところに、AIエージェントは『手』や『足』になる」。手足となって実行できるのは、各種プログラムとの連携、API連携、MCP連携などによって可能になる。
グーグルの環境であれば、AIエージェントで実際にメールを送ったり、Googleカレンダーを操作することが可能。また、マイクロソフトの環境であれば、ワードやエクセルの操作もできるという。
小澤氏は、AIエージェントを「まさにドラえもんの四次元ポケットから秘密兵器を取り出して、いろいろなことをやってくれる」と表現する。
AIエージェントでできること
そのうえで、AIエージェントのトリガーによって、できることを3つに分類。まず、設定された特定の時間や日時に自動的に稼働する「定時型(スケジュール型)」では、定期的なタスクの自動化やスケジュール管理が可能。例えば、「毎朝8時に天気予報をメールで送信」したり、「毎週月曜日にバックアップを実行する」など、定期的な業務を自動化することで、時間を節約し、ヒューマンエラーを減少させる。
次に、特定の条件やイベントが発生した際に稼働する「条件型(コンディション型)」では、リアルタイムの監視と対応、条件に応じた自動アクションで使われる。例えば、「会議が終わった後に議事録を要約」したり、「資料請求が来たら自動的にメールを送信する」、など、迅速な対応が可能で、業務の効率化ができる。
ユーザーの直接的な指示やコマンドに基づいて稼働する「指示型(コマンド型)」では、ユーザーインターフェイスの補助やインタラクティブなタスクの実行をおこなう。例えば、ユーザーからの指示によって、レポートの作成や企画書の作成などが可能。ただ、現状では、複雑な指示の理解に限界があるという。
今後の生成AIのトレンドは
小澤氏は、2025年以降の生成AIのトレンドとして、AIエージェントに加えて、「ドメイン特化」と「モデルの強化」を挙げた。
「ドメイン特化」は、AIを「専門家」に仕立てるもの。大規模言語モデル(LLM)の回答精度を向上させる技術のRAGは、専門データベースを参照させて質問に答え、利用者個人の好みに合わせてパーソナライズする。例えば、「特定の観光地の情報のみを読み込ませることによって、それに特化した活用ということができるようになる」という。テキストだけでなく、YouTubeなどの動画の内容も解釈してスポットを探し、過去の検索履歴などから情報をパーソナライズする。小澤氏は、「これからの生成AIは、専門家化、パーソナライズ化が非常に重要になってくる」と話す。
「モデルの強化」は、AIの「基礎能力」を上げること。とにかく学習量を増やして、AIを賢くする。また、文字だけでなく画像や音声なども理解させるマルチモーダルを進めていく。低コストで省力化する点については、JALの「JAL AI Report」を紹介。JALの客室乗務員が過去に作ってきたレポートを、すべて学習をさせることで、レポート提出にかかる時間と労力を削減することに成功しているという。さらに、複雑な問題を十分に考えさせる推論を強化していくことも進むとした。
小澤氏は、「今後、3つのトレンドは個別に進んでいくわけではなく、融合しながら進化していく」と解説。加えて、将来的にはAIエージェントロボット技術とが組み合わされ、ロボットの行動を出力できるようになる世界が現れると見通した。






















 観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】
観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】