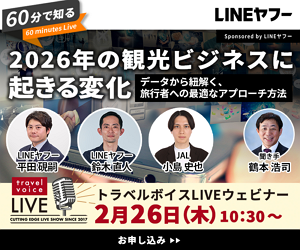日本観光振興協会の最明仁です。
前回の本コラムでは、海外における日本食レストラン数の推移、農林水産物、食品、クールコンテンツなどの輸出とインバウンド増加との連関について述べました。
今回は「地方創生2.0」や「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」「新たなクールジャパン戦略」をといった主要な地方、経済、社会政策が「観光」をどう位置づけているのかを整理し、観光とは一見無縁な業界が取り組む事例を紹介した上で、我々、観光産業はそれぞれの施策をどのようにとらえるべきか、私の意見を述べたいと思います。
※写真:2025年8月に東京・麻布台ヒルズで開催された「工場の祭典2025」プレイベントの様子(筆者撮影)
「地方創生2.0」とは?
政府は2025年6月に、今後10年間を見据えた「地方創生2.0基本構想」を閣議決定しました。2014年に地方創生の取組みが本格的に始まって以来、インバウンドの増加やリモートワーク、AI・デジタルの急速な普及などが地域に追い風となり、全国で好事例が多く生まれました。一方、東京圏への一極集中や地方の人口減少などの課題が顕在化しています。「地方創生 2.0」は、単なる地域活性化策ではなく、我が国の活力を取り戻す経済政策、多様な幸せを実現するための社会政策とされています。
「地方創生2.0」では、政策の5本柱を掲げています。
- 安心して働き、暮らせる地方の生活環境の創生
- 稼ぐ力を高め、付加価値創出型の新しい地方経済の創出:地方イノベーション創世構想(地域資源やサービスの高付加価値化、インバウンドの需要を最大限取り込むこと、海外に高く販売すること、施策の分野を越えて組み合わせる「新結合」を目指す)
- 人や企業の地方分散:産官学の地方移転、都市と地方の交流等による創生
- 新時代のインフラ整備とAI・デジタルなどの新技術の徹底活用
- 広域リージョン連携:都道府県域を超える「広域リージョン連携」の枠組みの創設、地方公共団体と経済団体や企業等の多様な主体が、周遊型観光の促進に連携して取り組む
「地方創生2.0」の施策集から、2の「稼ぐ力」に焦点を当ててみました。伝統工芸品やサイクルツーリズムなど担当者のその施策に賭ける渾身の思いが入ったものも、たくさんあります。ここでは限られたスペースの関係で一部を紹介します。以下のとおり、「地方創生2.0」では多岐にわたる施策において観光が言及されています。産業政策、地域経済の活性化の実現には観光が必要不可欠、観光の力が無ければ成り立たないことの証です。
- 農林水産物・食品の輸出、都会と農村との交流拡大:「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」に基づき、旅行者の農村誘致や高付加価値化を推進
- 酒蔵を中心とした輸出・インバウンドの強化:ブランド化・高付加価値化による輸出拡大、インバウンドへの魅力訴求を通じた関連消費の拡大
- 地場産業・伝統工芸品振興を通じた産業観光の推進:地場産業の歴史や技術の継承とあわせて商品価値を高め、地元への人材定着やインバウンド需要の獲得に向けたオープンファクトリーの推進。特に、伝統的工芸品の海外展開をさらに後押し
- 文化・芸術を通じた地方創生:文化庁と観光庁が連携し、「日本遺産」など振興。地域の文化施設が、インバウンド観光の拠点となるよう整備をおこない、インバウンド誘致に向けて文化資源の発掘と磨き上げ、活用、人材育成を推進
- コンテンツを活用した地方創生の好循環づくり:マンガ、アニメ、ゲーム、映画等の活用・人材育成、ロケ誘致、ロケ地の聖地化など
- サイクルツーリズムの推進等による自転車の活用の推進:自転車を活用し、地域資源を活かした持続可能な観光地域づくりを推進
製造業、農林水産業(6次化の取り組み)、インフラ、ふるさと住民登録制度などにおいても観光を活用して地域創生や経済活性化に成果を上げる事例も出てきました。ここでは私が注目する代表例を紹介します。
町工場が実践する産業観光 ―燕三条「工場(こうば)の祭典」
2013年に始まって以降、燕三条のものづくり技術の高さをデザインで表現する日本の代表的なオープンファクトリーイベントとして注目を集めています。
2021年に燕三条地域で開催された展覧会が世界的なデザイン賞「Red Dot Design Award 2022」でブランド&コミュニケーションデザイン部門の最高賞となる「グランプリ」を受賞しました。運営は世代交代や新組織への移行を経て、イベントの名前やコンセプトを継承をしつつ、持続的発展をめざしています。たくさんの工場が存在し、製品の金型づくりから加工、包装や物流までを地域内で完結できてしまう、ものづくりのまち燕三条。昨年は地域の工場109社が参加し、4日間で4万人近い来場者で賑わったそうです。今年は10月2日~5日に開催予定です。
生産者や地元大学を巻き込む ―庄内ガストロノミーツーリズム
鶴岡市のレストラン経営者・奥田政行氏が中心になり、2004年に始めた「ガストロノミーツアー」。徐々に農林水産業(生産者)、行政、山形大学農学部などを巻き込んで、開始から20年が経ちました、「食の都庄内」宣言をおこない、空港の愛称を「おいしい庄内空港」とし、様々な取り組みが功を奏して鶴岡市はユネスコの「食文化創造都市」にも認定されました。「食の庄内」ブランドによる地方創生の成功例と知られています。
私がJR東日本で庄内の担当をしていた頃、大きな列車事故で損なわれた地域のイメージを回復させる施策を模索する中で、ヒントを求めて相談したのが奥田氏でした。食という体験を通じて得られる感動、すばらしさを熱く語る姿に共感し、さまざまな取り組みのお手伝いもさせていただきました。庄内は今、「食」を柱にさらに大きな目標を掲げようとしているようです。
インフラツーリズムの魅力
ダム、橋、港、歴史的な施設を観光資源とするインフラツーリズムも注目されています。富山県「黒部ダム」、埼玉県「首都圏外郭放水路」などがよく知られています。巨大な構造物のダイナミックな景観を楽しむ、普段は入れない内部や今しか見られない工事風景など非日常の体験を味わうことができます。ガイドの案内を通してインフラの役割や背景を学ぶことも魅力です。
好事例のひとつに出雲大社と並ぶ地域のシンボル日本一の高さを誇る出雲日御碕灯台があります。出雲日御碕灯台は、日本一高い石造り灯台として100年以上にわたり日本海の安全を守り続けてきた海上インフラの一翼を担っている施設です。現在も現役で機能していて、橙光会が航路標識事業の周知・啓蒙活動を実施しています。灯台にのぼって景観を楽しむことができ、資料展示室も併設されており、インフラツーリズムならではの学びと楽しみを得ることができる施設です。
地域のファンと関係人口を増やす ―ふるさと住民登録制度
ふるさと住民制度は、住所地以外の地域に継続的に関わる人を「ふるさと住民」として登録し、地域の担い手確保や経済活性化につなげる仕組みとして創設される取り組みです。「地方創生2.0」の目玉の政策として、具体的な事業や戦略が2025年度中に策定される予定です。ふるさと納税、観光で何度も訪れることによる地域経済への寄与、ボランティア副業、二拠点居住などを通じて関係人口を増やす狙いがあります。
すでに地域単位で動いている事例としては、県外在住者が県内に滞在しコワーキングスペースでテレワークをした費用を補助する「ふくしまぐらし×テレワーク支援補助金」、高知県梼原町がふるさと住民登録者に対しておこなう地域だよりの配布やイベントへの招待、福井県小浜市のふるさと住民がボランティアや観光ガイドとして地域活動に参加するなどがあります。
「地方創生2.0」の施策集を読んで残念に思ったことは、各施策における観光への取り組みが一つにまとめられていない点です。観光は、政策実現のための一つのパーツとして扱われていることが多いのです。
観光産業は農林水産業やコンテンツ産業、製造業の背後にとどまるのではなく、それらを牽引していく気概を示し、日本の基幹産業として地位を確固たるものにしなければならないのではないでしょうか。来年度からの第五次観光立国推進基本計画の策定が佳境に入っている今こそ、それを主張するチャンスです。私たちは観光客「数」、観光消費「金額」だけでなくマクロの議論も積極的にしていくべきです。多少出過ぎた意見かもしれませんが、あえて提起したいと思います。























 観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】
観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】