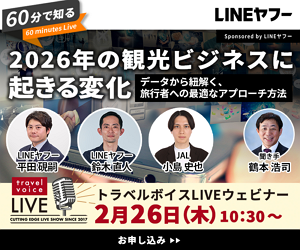日本旅行業協会(JATA)会長の高橋広行氏(JTB会長)は、2025年7月4日に開催した記者懇談会で「今年は我々にとって特別な年」と述べ、先ごろ取りまとめた第5次観光立国推進基本計画に対する政策提言の重要性を強調した。5月28日には観光庁をはじめ、外務省や文部科学省を訪問するなど、関係省庁や関係先への働きかけを強めている。
高橋氏は、提言書に「観光の将来に関わる課題とその対策を盛り込んだ」と話し、旅行業界の最大の課題が「訪日旅客数と日本人出国者の不均衡の深刻化」であることを説明。8章からなる提言書の1 番目に「日本人海外渡航者の拡大による均衡の取れた双方向交流の実現」を掲げ、その施策の1つに「地方空港の積極的な利活用を促進する長期計画策定と、国際線就航支援及びチャーター便運航促進のための助成制度の拡充」を要望した。
高橋氏は、国が目指す2030年の訪日旅行者数6000万人を実現するためには「国際交流は双方向交流が基本で、日本側が受け入れ態勢を進めるだけでは不十分。国際線が集中している東京・大阪の大都市空港は限界がきている」と指摘。その上で、今後は「地方空港の拡大が不可欠だが、訪日客だけでは地方空港を埋めきれない。維持するためには、日本人の海外旅行需要が必要。日本人の渡航者数が安定して初めて、インバウンドも活性化する」と話し、バランスの取れた双方向交流の重要性を強調した。
さらに高橋氏は、インバウンドの課題として「一部地域への一極集中」をあげ、提言書に「訪日旅行者の地方分散と地域経済の活性化」を盛り込んだことも説明。オーバーツーリズムの解消へ「日本人の旅行時期の分散平準化が与える効果は大きい」とし、提言書では一部自治体ではじまった「ラーケーションに代表される学校平日休み制度の推進」や「有給取得義務の拡大の検討」などを提案。それが「結果的に、総需要の拡大にもつながる」(高橋氏)と主張した。
旅行会社の価値創出へ
旅行部門別では、マーケット全体の回復が進む中での旅行会社の販売状況に対する認識を示し、従来手法からの脱却と旅行会社ならではの価値創出に向けた取り組みを強めている様子が説明された。
JATA副会長で、国内旅行推進委員長の小谷野悦光氏(日本旅行会長)は、2024年の日本人の国内宿泊需要や国内旅行消費額がコロナ前年を上回る推移であるものの、主要旅行業者の2024年度の国内旅行総取扱額は2019年度の85%程度であることを説明。OTAやサプライヤーの直販が加速化している中、「旅行会社の過去のやり方では、いまの消費者に選んでいただくところまでしっかり向きあい切れていない」と話し、「旅行業界全体として、『代売』から脱却した価値ある商品の企画販売が必要」との認識を示した。
好調の訪日インバウンドでも同じような課題を抱えている。主要旅行業者の外国人旅行(訪日インバウンド)の取扱額は、訪日観光客数が過去最多となった2024年度でも2019年度比3.2%減と減少した。JATA理事で、訪日旅行推進委員会委員長の百木田康二氏(東武トップツアーズ社長)は「海外のOTAがシェアを伸ばしている。これは我が国だけではなく、世界中の旅行会社が直面している課題」と述べるとともに「旅行会社にはOTAにはない力があり、まだまだ拡大の余地はある」との考えを示した。
一方、マーケット全体の回復が遅れている海外旅行では、より具体的な取り組みに着手した。今後のレジャーマーケットにおけるビジネスモデルを検討するための「海外旅行リエンジニアリングワーキンググループ」を設置した。
JATA副会長で、海外旅行推進委員長の酒井淳氏(阪急交通社社長)は「テクノロジーの進化で消費者が有益な情報を簡単に入手できるようになり、旅行会社の存在意義が薄れている」との認識とともに、活路として「我々の取引先も多様化している。そこで旅行会社の力を見せられるのでは」と強調。ワーキンググループでは、諸外国の事例を調査、考察しながら、マーケット環境を可視化し、業界全体で取り組むべき戦略や打ち手を検討して、海外パッケージツアーの新たな価値提案モデルを策定する方針を説明した。
最後に、JATA副会長の原優二氏(風の旅行社会長)が、業界の人手不足の現状と優秀な人材確保と育成に向けた取り組みを説明。JATA会員会社の従業員者数は2019年の約7万人からコロナ禍を経て2025年には約4.7万人となり、2019年の67%にまで縮小した。JATAでは、人材派遣会社との連携のもと会員会社へ経験者採用を斡旋しているほか、新卒者向けの業界特化型合同説明会を実施。2025年は約200名の学生が参加した。ただし、2020年は約530名が参加しており「学生の(就職先としての旅行業界への)興味関心も、コロナ禍前に戻っていない」(原氏)との認識だ。
一方で、早稲田大学の提携講座「ツーリズム産業論」は、毎年約400名の学生が受講する中、2025年は500名以上が受講。観光産業に対する関心の高さが見られるという。
アゴダへの対応
懇談会では、記者からOTA「Agoda(アゴダ)」をめぐる予約トラブルについて質問があった。海外に本社を置くOTAのアゴダだが、2024年7月に第1種旅行業を取得しており、JATA正会員でもある。そのため、JATAは消費者からの苦情相談に対応しており、一定数の相談が寄せられている。JATAは監督官庁である観光庁にも報告をしており、観光庁がアゴダへの指導を始めている。JATAとしても観光庁と連携をしながら、改める点を明確にして、指導していく考えだ。
会長の高橋氏は、観光立国推進基本計画への提言書にも「健全な観光産業の育成」として、「近年急増している宿泊転売の実態把握と、悪質な転売撲滅へ向けた対策の実施」を要望していることを紹介。「これから訪日インバウンドが増えていく中で、どうしても日本の法律で規制がかけられない不正な行為が出てくると思われる。観光産業全体の健全性を高める目的で整理をし、提言している」と話した。























 観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】
観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】