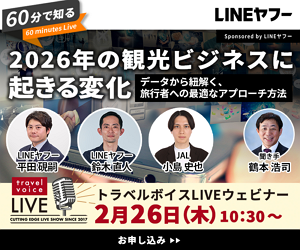観光庁が、2025年7月1日付で旅行振興担当の参事官を新設し、日本人による国内交流やアウトバウンドの活性化、さらに深刻化している観光人材の確保・育成といった政策課題に取り組む体制を強化する方針を打ち出した。
インバウンドとアウトバウンド(日本人の海外旅行)の不均衡、地域の稼ぐ力を高める関係人口の創出をはじめとした国内交流、経営の高度化など、さまざまな対策が喫緊に求められているなか、「観光産業が構造的に持続可能な成長ができるよう、政策を深化してサポートしていく」と語る参事官(旅行振興)の根来恭子氏に、そのミッションや新たなアプローチを聞いてきた。
ビジネス視点からの地方誘客を強化
新設された旅行振興担当の参事官は、もともと観光産業課が担当していた旅行業、観光人材の確保・育成、国際観光部(参事官)が担当していたアウトバウンド促進、観光資源課が担当していた国内交流を移管し、総合的に政策推進するために設置された組織。根来氏は「三位一体となり、人が移動することで交通や産業が回っていくという観点で、さまざまな課題に取り組んでいきたい」と力を込める。
まず、国内交流の打ち手として挙げたのが、「余暇に加え、ビジネス目的による地域の魅力発見と何度も訪れる仕組みの促進」だ。一例として、「第2のふるさとづくり」でも期待されるワーケーションについて根来氏は、「コロナ禍で本来の勤務先を離れて旅先で仕事をするという社員目線のワーケーションが一般的なイメージだが、企業自身が地域と関係を構築し、地域課題の解決に取り組む『業務型ワーケーション』に力を入れたい。」と話す。
根来氏自身、全国を飛び回ることが多く、出張を通じて地域の魅力に気づき、リピーターになった経験が多い。「出張の場合、必然的に地域の方々と触れ合う機会が多く、自分でも知らなかった観光資源をはじめ、刺激を得られる」。日本人による国内旅行の消費額は2024年に過去最高の25兆円を達成したとはいえ、物価高などから横ばい傾向にある。「余暇につかえる金額が限られているのは事実で、ビジネスでの移動をきっかけに出張と旅行を組み合わせたブレジャーや家族・友人とのプライベートでの再訪につなげ国内旅行市場を掘り起こす。プランニングに長ける旅行会社、地域の魅力を知り尽くしたホテル・旅館のコンシェルジュ等の活躍にも期待している」(根来氏)。
アウトバウンドは地方空港の活性化も不可欠
一方で、低迷が深刻なのがアウトバウンドだ。日本人による海外旅行者数は2024年に約1300万人となったが、2025年までにコロナ前の2019年水準越え、2000万人との政府目標には遠い。直近の日本人出国者数では、2025年1~8月累計で前年同期比14.2%増の946万2800人で推移している。
根来氏はアウトバウンドについても「ビジネスミーティングでオンライン、ハイブリッド型が浸透してきたが、信頼関係の構築には実際に会って話すことが重要だ。コロナ禍以降、海外出張が減少しており、アウトバウンド伸び悩みの一因になっている。インバウンドだけでなく、アウトバウンドもMICEが重要。」と強調。双方向交流の重要性にも言及し、「アウトバウンドとインバウンドは表裏一体で、アウトバウンドの回復がないかぎり、国際線の維持・拡大は困難で、将来的にインバウンドも頭打ちになってしまう。また、地方在住者は国際線が発着する空港への移動にも交通費、宿泊費がかかり、海外旅行に行きづらい課題を抱えている。地方空港の活性化を通じたアウトバウンド促進や地方誘客にも取り組んでいきたい」と力を込めた。
また、日本人の国際感覚の向上や相互理解を促進する観点から、海外教育旅行を通じた若者のアウトバウンド促進にも注力する方針で、学校や自治体との連携によるプログラム開発、シンポジウム開催など普及啓発も積極化するとした。
こうした企業・団体、自治体との関わりを強化し、休暇を取得して外出や旅行を楽しむことのできる職場環境を整えるとともに機運を高め、地域経済活性化に貢献することを目指して観光庁が内閣府、厚生労働省、経済産業省と共同で進めているのが「ポジティブ・オフ」運動。主に企業単位での賛同を募っており、現在は2865件に上っている。
この取り組みは参事官(旅行振興)が担っており、現在は企業・団体の取り組み事例や応援メッセージを紹介している段階だが、根来氏は「日本や海外にどんな観光資源があり、どんな体験ができるのか。地域や事業者の協力を得ながら体系的に情報発信できる仕組みを整え、旅行需要の底上げを図る」との構想を話す。
 ポジティブ・オフ運動のねらい
ポジティブ・オフ運動のねらい
持続可能な観光地づくりを実現する人材育成へ
もう1つの重要なミッションが、観光地・観光産業における人材不足対策事業だ。インバウンドをはじめとする観光需要の急速な回復に伴う、受け皿の強化は急務。旅行振興(参事官)では、主に人材確保の促進、外国人材の確保、人材活用の高度化に向けた設備投資支援、経営の高度化を担う。たとえば、人手をかける業務に人材を集中投下しサービス水準向上・賃上げを実現するため、DXを活用した補助事業、海外でのジョブフェア開催、宿泊分野における特定技能外国人制度などさまざまな取り組みを実施している。
もっとも、根来氏は「これまでの観光人材育成は、大学等で各自が学ぶ手法が中心だったが、持続可能な観光地域づくりのためにどんな人材が必要なのかあらためて考えるべきだ。理論はもちろん、実践的に課題解決できる総合力や行動力を持った人材が求められる」と指摘する。
一例として、着任してすぐの7月に自身が参加したミーティングをあげた。愛媛県道後温泉で早稲田大学ビジネススクールの講師を招いて、地元の旅館・ホテル、交通機関、飲食・物販、金融機関、DMO、旅行会社、自治体など多彩なプレーヤーが参画し、地域に根差した観光地経営の戦略立案とその実現に取り組むアクションラーニングのキックオフミーティングだ。今後、プロモーション、受け入れ環境整備、観光資源の磨き上げ・開発、消費額の拡大、滞在時間延長というテーマごとにワーキンググループをつくり、月1回のミーティングで連携しながら国内外からお客様を呼び込むための課題解決に取り組む。今後、道後温泉だけでなく、他の地域でも同様の取組を実施していく計画もあるという。
これまで、根来氏は、観光庁はもちろん、美術館や劇場、芸術祭などの文化資源への誘客を通して「日本の美と心」を国内外に発信する文化庁の「日本博」、日本の魅力の発信や訪日観光推進を通して対日理解を促進する外務省の「パブリック・ディプロマシー(広報文化外交)」など、観光産業につながる政策に多角的に関わってきた。新しい風を吹き込み、日本の旅のチカラを底上げする手腕に期待が集まりそうだ。























 観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】
観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】