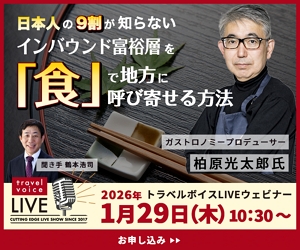国学院大学観光まちづくり学部の井門です。
夏休みに出かける学生が年々減少しています。かつて、夏といえば多くの学生が旅行へ出かけたものですが、今では動画視聴やゲームなど室内で過ごす時間が主流になりました。消費スタイルの多様化が一因といえますが、それでも旅の魅力を改めて高める必要があります。
学生に「旅に出ない理由」を尋ねると、「お金がない」「アルバイトを優先したい」という答えが多く、「面倒くさい」という声も聞こえます。非正規雇用が当たり前となった現在、時間とお金に余裕のない大人たちの生活リズムに、学生も巻き込まれているのかもしれません。若い頃の旅の経験は、大人になってからの旅へのモチベーションになると考えれば、学生や忙しい人でも楽しめる、誰にでもやさしい市場づくりが求められているといえます。
観光市場は量から質へ、脱大衆化で懸念も
日本の観光市場は「量から質へ」と転換が進んでいます。特に、コロナ禍をきっかけに、この動きは加速しました。全国旅行支援や県民割などの施策は一定の効果を上げましたが、価格重視の「プライスハンター」を呼び込み、普段とは異なる客層で観光地が混雑。クレームやサービス低下も目立つようになり、多くの観光事業者は「今後は単価アップを目指そう」と考えるようになりました。
観光庁の「地域一体となった高付加価値化事業」やオーバーツーリズム対策も、この流れを後押ししています。コロナ後は「富裕層の獲得」という言葉が各地で聞かれ、観光は“脱・大衆化”に向かいつつあります。地域に共感し、マナーを守る「ツーリストシップ」を備えた旅行者を歓迎したい―そんな思いが強まる一方、学生や可処分所得の少ない人たちが旅の市場から排除されつつある懸念も感じます。
大企業のベースアップや初任給の引き上げで給与水準は回復傾向にあり、世のマネジメント層は高価格の旅行商品を積極的に受け入れています。その結果、2024年は国内旅行者数が減ったものの、宿泊単価は過去最高を記録しました。一方、高付加価値化できない宿泊施設は市場から退出を迫られています。今後、価格の高い宿と一部の高所得者層だけが観光地の主役になるのでしょうか。それが私たちに突き付けられた問いです。
宿泊税や二重価格には合理的な理由の説明を
単価上昇と同時に、観光地では宿泊税の導入や二重価格が議論されています。インバウンド増によるオーバーツーリズムを背景に「受益者負担」の考え方で地域外来訪者に公共サービス費用を負担してもらうのは一定の合理性があります。
しかし料金を引き上げれば、需要は確実に減ります。追加負担の理由が不明確なら「便乗値上げ」と捉えられ、不信感が募ります。消費税、入湯税、宿泊税、入域料など多くの追加費用が発生する現状では、説明責任がより重要です。
さらに、民間事業者が設ける二重価格は「差別」と受け取られやすく、企業やブランドの評判が悪化することで、様々な損失が発生するレピュテーションリスクを伴います。外国人だけを値上げする場合は、特に注意が必要で会員制の導入や全体を値上げした上で割引の仕組みを加えるなど、合理的かつ公平性のある設計が求められます。
例えば、宿泊業や航空業では、レベニューマネジメントという「稼働率×単価」の最大化を目標としてプライシング(価格設定)をしています。客数が減っても単価の上昇で売上が伸びるというのが大前提です。つまり、価格を操作して需要を増やす、需要の価格弾力性を活かした戦略といえます。ただ値上げするのではなく、いかに総売上を増やすかという点が最終目標となります。
需要の価格弾力性を活かす
高所得者層と大衆の格差が広がるなか、誰も排除しない包摂的なプライシングが求められています。税なら課税対象を合理的かつ明確に設定し、価格なら対価の根拠を説明できるようにします。曖昧さは不信感の温床です。
一例として、旅館業の慣習である「1泊2食制」は、その曖昧さを象徴しています。1泊2食付き料金がだめなわけではありません。問題は、その料金が価格弾力性を活かしていないこと、つまり、稼働率の低い日まで空室を抱える結果につながる点です。
近年の人手不足から料理提供が難しくなり、1泊2食制の旅館が宿泊と食事を分離して宿泊のみを提供する「素泊まり」、いわゆる「泊食分離」が進んでいると言われていますが、その結果、旅館の稼働率が上がったのであれば、利益率が高まり経営改善につながったのではないでしょうか。
泊食分離の本質は管理会計にあります。室料などの固定費と、食事代などの変動費を切り分け、整合性のある価格設定を行うことが主旨です。需要によって室料を、原価によって食事代を変動させます。こうした土台があって初めて、レベニューマネジメントやダイナミックプライシングが機能します。このような基準が曖昧なまま、どんぶり勘定にしてしまうと、需要の価格弾力性を無視する結果となり、ガラガラの平日は部屋を空けておくだけとなってしまいます。
1泊2食制の時代、旅館は「宿泊業」というより「泊まれる料亭」に近い業態でした。料亭としてのステイタスを維持するため、値下げすることはご法度でした。
しかし、時代は変わり、本物を提供する料亭旅館を除けば、多くの旅館は宿泊業として稼働率の最大化を重視したプライシングにシフトしなければ利益確保は難しくなっていきます。
例えば、平日には室料だけの素泊まりだけを売る、といった戦術はどうでしょうか。調理場は休みができますし、学生をはじめ旅に不慣れな層も泊まりやすい料金になると思います。
稼働アップを前提とした宿泊業を目指した結果、草津温泉などで見られる 1泊1~2万円台の上質な素泊まり宿という新しい業態が生まれました。食事は外で取る必要がありますが、自由に食事を選べるほうが、価格感度的に満足度が高くなる客層も多い時代になったのではないかと思います。
脱“脱大衆化”のために
素泊まりだけではなく、食事やドリンクなど館内消費がすべて含まれたオールインクルーシブや、通年一律料金、人数一律料金という仕組みも考えられます。これこそ、旅に不慣れな層にとって、わかりやすいプライシングです。ただし、こうした料金は、あくまで稼働率を最大化でき、室料で安定収入を得られる体制が整って初めて実現可能です。
誰にもやさしい国内観光市場を作るために、様々な事業者が需要の価格弾力性を活かしたプライシングを試してほしいと思います。























 観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】
観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】