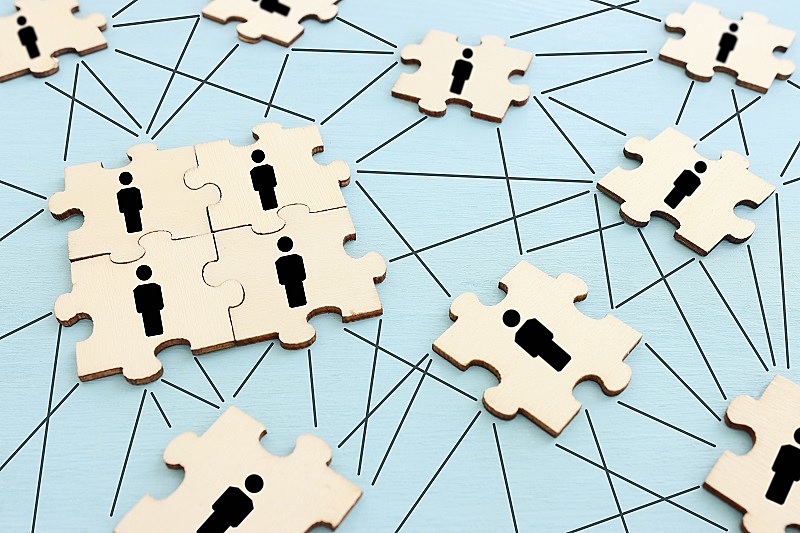
日本観光振興協会は2005年9月、ツーリズムEXPOジャパン(TEJ)で国内観光シンポジウム「フェーズフリーで進化する観光 安心と豊かさが築く次世代のデザイン」を開催した。日常と非日常の区別をなくし、“備えない”防災対策として注目のコンセプトである「フェーズフリー」に焦点を当て、観光分野における先進的な事例として、北海道小清水町と高知県鳴門市の取り組みを紹介した。
同協会理事長の最明仁氏は、訪日インバウンド市場が拡大するなか、災害時に「居住者ではないお客様の安全をどう確保するか」は、今後大きな課題になっていくとし、フェーズフリーの取り組みを広く知ってほしいと呼びかけた。
平時と有事を連続して考える
シンポジウムでは、まず、フェーズフリー協会代表理事の佐藤唯行氏が登壇。「有事に“備えられない”ことを前提にするのがフェーズフリーの考え方だ。日常というフェーズと非常時というフェーズの垣根をなくし、どちらにも役立つものにすることが、災害に強い、安心・安全な社会につながる」と訴えた。
観光・旅行分野では、比較的、新しいコンセプトだが、オフィス家具、靴、衣服、食品、賃貸住宅など幅広い業種で、すでに新しい商品企画やマーケティングに活用されており、ウェブサイトやテレビCMにも「フェーズフリー」という言葉は頻繁に登場する。佐藤氏によると、2014年に日本で生まれた防災の新コンセプトだ。
同様に、全国各地の自治体や国の各省庁でも、まちづくりの基本方針や官民連携の新しいコンセプトとして採用されている。地震からの復興途上にある石川県がまとめた「創造的復興プラン」でも、平時の延長で有事に備える、どんな状況下でもフェーズフリーで活用可能なライフラインを整備する方針を取り入れている。
「これまでは平常時の商品価値を高めるものと、地震や台風など、有事の対策は別々に考えられていたが、(2つのフェーズを)連続したものとして考えること」(佐藤氏)で、より合理的でサステナブル、効果の高い防災対策になるのがメリットだ。
また、同氏は「過疎化や人口減少が進み、日常においても問題が多いなかで、非常時にしか役に立たないインフラを整備することは、非常に難しくなっている」、「普段の生活をより良くする延長戦上で、非常時の課題も解決できるような社会デザインが求められている」とも指摘。観光振興におけるフェーズフリーについては、観光の魅力をさらに高めることが同時に非常時の暮らしをより快適にし、安心・安全につながることだと解説した。
 シンポジウムの様子
シンポジウムの様子
事例1. 防災と賑わいを実現した「小清水町役場ワタシノ」
北海道小清水町産業課課長の石丸寛之氏は、フェーズフリーのコンセプトを取り入れた地域振興の取り組みを紹介した。
北海道の東、オホーツク海に面した人口4300人の小清水町では、日本全国の鳥の50%を観察できることから、バードウォッチングを観光の核にして交流人口の拡大を進めてきた。この人流を市街地にもいざなって過疎化が進む地域を活性化すること、そして、防災拠点も兼ねるフェーズフリー型の施設として、複合庁舎「小清水町役場ワタシノ」を2023年春に開設した。
建物内には、役場のほかにカフェやスポーツジムがあり、町民のウェルビーイング向上の一助になっている。また、観光客からニーズが多かったランドリーをあえてここに設置し、市街にも足を伸ばしてもらうことを狙った。その結果、年間の来庁者数は4800人から12万2000人に増え、「用事がない時も人が集まるようになった。おそらく観光地化している」と石丸氏は手ごたえを話す。
「ワタシノ」は、万一の際は地域の防災拠点にもなる。たとえば、スポーツジムのマシーン類をすべて片付ければ、床暖房とシャワーのある避難所に。通常は有料で運営しているランドリーは、災害下では町民の衛生環境の保持に、カフェは炊き出しに活用する。
さらに、隣接地には大手ドラッグストアを誘致し、災害時、優先的に役場に商品を回してもらう協定を結んだ。石丸氏は、「日常使いできるものが、災害時にもシームレスに役に立つ仕組みであること、ただの無駄づかいではないことを町民には説明した」。結果的にクレームはなく、むしろ非常に喜んでもらっているという。
同町では、フェーズフリーの先進事例として、国や自治体から民間事業者まで、多くの視察も受け入れており、2025年8月には、フェーズフリーを体験コンテンツとした1泊2日のツアーを初めて催行した。小清水町の取り組みをベストプラクティスとして、北海道全体に広めようとする道庁直轄のフェーズフリー・プロジェクトチームも動き出しているという。
事例2. 年間130万人が訪れる、道の駅兼防災拠点「くるくるなると」
日本全国の自治体で初めて、2017年度からフェーズフリーの「地域防災計画」に着手したのが徳島県鳴門市だ。鳴門市戦略企画課副課長の藤倉大樹氏は「防災に普段から備えることは難しい、という前提のもと、従来の考え方を見直した」と話す。
南海トラフ巨大地震や台風、高潮などへの対応が必須である同市では、平常時は観光客が四国で最初に立ち寄るところ、有事には人的・物的支援の拠点となるまちづくりを目指している。ボートレース鳴門、道の駅「くるくるなると」、鳴門市役所本庁舎をフェーズリーな形に整備したほか、民間施設、道路、公園などの維持管理、学校教育などにもフェーズフリーの考え方を取り入れ、ハードとソフト両面で推進。2024年には「防災思想の普及」の功績が認められて内閣総理大臣表彰を受賞した。
その一つ、道の駅「くるくるなると」では、平時は憩いの場になっている屋上の見晴らしデッキや芝生広場が、有事は津波の一時避難場所に。屋内にある渦潮の形の滑り台や人工芝のスロープは、避難の動線や救援車両のアクセス経路として活用される。バックヤード・倉庫の保管庫にある食料は、平時は地元特産品などの商品として販売し、有事は避難者への食糧や物資とする。
「くるくるなると」には、2024年度実績で年間約130万人が来場、売上は20億円に達し、80以上のメディアで取り上げられた。「観光施設の一つとして四国内でもトップの集客力を誇るようになった。鳴門の魅力発信に加え、フェーズフリー推進のランドマークとしての役割も担っている」(藤倉氏)。
日常の価値を上げることに軸足を
佐藤氏は、2つの自治体の成功事例を踏まえつつ「津波用の避難施設を作ったものの、使われないまま老朽化してしまうケースもある。普段から地域住民や観光客でにぎわう施設が、非常時にも役立つ方が合理的で、維持管理も効率的だ。地域の知名度アップにもつながる」と話した。
これからフェーズフリーに取り組む自治体や企業へのアドバイスとしては、「日常の豊かさや利便性アップと、非常時の生活や命を守ることを考える時、後者の方がずっと重要だと思ってしまうこと」が注意点だと同氏。有事に役立つことを考えれば考えるほど、「日常の暮らしで欲しいものから離れてしまう。軸足は、普段の観光体験やツアーをもっと面白くすること、日常の提供価値を上げることに置き、それを非常時にどう役立てるかを考える」とのアプローチを提案した。






















 観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】
観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】








