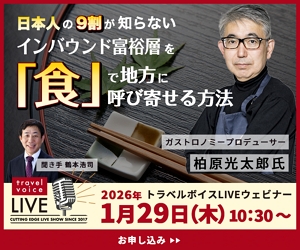BtoB向け観光商談展示会「iTT国際ツーリズムトレードショーTOKYO 2025」が2025年6月25日から27日にかけて東京ビッグサイトで開催された。「国際ウェルネスツーリズムEXPO」と「観光DX・マーケティングEXPO」が併催され、両イベントで66社・団体が初出展。来場者数は、3日間で累計1万152人となり、活発な商談が繰り広げられた。前年を上回る規模となった同イベントをレポートする。
観光庁、「まだまだ伸びていく産業」
iTT国際ツーリズムトレードショーでは、情報や知見を共有する各種セミナーも開催された。基調講演では、観光庁審議官の鈴木貴典氏が「持続可能な観光立国に向けて」をテーマに、これまでの日本の旅行市場を振り返るとともに、今後の政策について説明した。
そのなかで、インバウンド市場については、フランスやスペインなどを例に、「人口比で言うと、まだ伸びしろはある」と話し、改めて政府目標である2030年までの訪日外国人6000万人、消費額15兆円を目指していく考えを示した。
そのうえで、持続可能な観光を進めていくために、地方誘客、オーバーツーリズム対策などとともに、文化財の活用を含めて「もう少しインバウンド旅行者がお金を払って楽しめるような仕組みを考えていく必要がある」と指摘した。
また、日本人の旅行については、高齢化が進むなか、市場規模を維持・拡大していくうえで、高齢者の旅行のあり方や有給休暇取得率の向上を考えていく必要があるとした。
旅行者の利便性向上と観光事業者の生産性向上に向けた観光DXの重要性については、宿泊施設でPMSなどの導入が進んでいるものの、各メーカーの仕様が様々で全体として効率化が進んでいないことを問題点として指摘。その解決に向けて「⽇本ホスピタリティーテクノロジー協議会(JHTA)」が設立されたことを紹介した。
このほか、現在、議論が進んでいる2026年度からの新たな観光立国推進基本計画(第5次)についても言及したうえで、「観光産業は人手不足などの問題はあるが、まだまだ伸びていく産業」と将来への期待感を示した。
 今後の観光政策を説明する鈴木氏EYストラテジー、AIでOTAや旅行会社の役割に変化も
今後の観光政策を説明する鈴木氏EYストラテジー、AIでOTAや旅行会社の役割に変化も
また、EYストラテジー・アンド・コンサルティング・ストラテジックインパクト・パートナーの平林知高氏は、「生成AIがツーリズム産業に与える影響」について講演した。平林氏は、急速に成長するAI産業に触れたうえで、観光産業でのAIの活用分野として、パーソナライゼーション、業務自動化、コミュニケーションを挙げ、それぞれ事例を挙げて説明した。
一方で、「効率化だけがAIによって起こる世界観なのか」と問題提起。そのうえで、データの取り方、ビジネスモデル、人材、それぞれで変化が起きるとの考えを示した。
このうち、データの取り方では、パーソナライゼーションは、過去の旅行データだけで実現できるものではないと指摘。ニーズの状況は時間の経過とともに変わることから、「多くの情報を立体的に見せていく世界観になる」としたうえで、「どのようにユーザーから気持ちよくデータを提供してもらうかの仕掛けも必要」との考え方を説明した。
ビジネスモデルの変化については、これまで相対的に弱い立場だったサプライヤーが力を取り戻す機会になると予見。AIマッチングプラットフォームの登場によって、サプライヤーがOTAに在庫を提供し、旅行者がOTAに依存する現在のモデルから、在庫を持つサプライヤーが旅行者のニーズを把握し、旅行者と直接コミュニケーションをとることで、よりパーソナライズされた体験を提案できるようになるとした。
また、生成AIの時代、需要に対して、個別にアクセスできるようになれば、「OTAや旅行会社の役割も変わってくる」と指摘した。
人材については、最後はヒトによる「判断」が重要と強調。データサイエンスによる分析も生成AIが担うようになると、「その結果をどのように解釈すればいいのかが圧倒的に重要になってくる」とし、その判断力を養う人材育成の必要性を説いた。
 AIの登場で変わる旅行業界を解説する平林氏日本のウェルネスツーリズムに高い潜在性
AIの登場で変わる旅行業界を解説する平林氏日本のウェルネスツーリズムに高い潜在性
ウェルネスツーリズムについては、トラベルボイス鶴本浩司代表が「ウェルネスツーリズム2025」として、基礎知識から海外の注目事例までを紹介した。
ウェルネスツーリズムの世界市場規模について、グローバル・ウェルネス・インスティテュート(GWI)の調査結果から、2023年の8302億ドルから2028年には1.35兆ドル(約196兆円)、2030年には2.1兆ドル(約305兆円)になる試算を紹介した。
鶴本代表は、コロナ後の健康志向の高まりを受けて、世界でウェルネスに対する支出が増加していると説明。GWIの2023年のデータによると、ウェルネス旅行者は一般旅行者よりも消費額が高く、海外旅行者は1回の旅行で36%、国内旅行者は163%も多く消費するという。
海外の事例では、シンガポールの「メンタルヘルス・ツーリズム」、ドバイの最先端医療とラグジュアリーを融合させた取り組みなどのほか、個別の宿泊施設が実施しているウェルネス体験を紹介した。
日本については、恵まれた自然環境、健康的な食事、温泉文化、禅の思考などからインバウンドへの訴求力が高いとした。
そのうえで、日本での受け入れに向けては、ウェルネスツーリズムが広範囲に及ぶことから、地域で何が提供できるのか明確化する必要があるとしたほか、ストーリー性と高付加価値化、本物を見せる取り組みが重要と指摘した。
ウェルネスツーリズム、医療ツーリズムから温泉まで
世界的に注目が集まるウェルネスツーリズムのサプライヤーが集まった「国際ウェルネスツーリズムEXPO」。「ワーケーション・チームビルディング・ゾーン」と「医療ツーリズム・ゾーン」が設けられたほか、昨年に引き続き特設エリアとして温泉宿を集めた「温泉ストリート」が設置された。今年は、世界のウェルネスホテルに目を向けてもらう目的で「World Wellness Hotels Collection」として、海外から2社が出展した。
ワーケーション・チームビルディング・ゾーンでは、地域の自治体や事業者が多く出展。北海道観光機構、千葉県、宮城県南三陸町観光協会、沖縄リゾートワーケーション推進協議会などの観光団体のほか、アクティビティ系として、亀山温泉リトリート、鶴居村釧路湿原観光コンテンツ創出協議会、奥会津チルトリート、保津川下りなど地域のユニークな出展が来場者を惹きつけた。
 川旅と健康の新たな価値創造を提案する京都の 「保津川下り」
川旅と健康の新たな価値創造を提案する京都の 「保津川下り」
また、宿泊施設では、「温泉ストリート」として出展した温泉宿に加えて、京都大原の一日一組様限定のプライベートリトリート「京都大原はちかん」がシームレスなウェルネス体験を提案した。
医療ツーリズム・ゾーンでは、「治す」をテーマに、医療クリニックやリハビリテーション病院などが、メディカルツーリズムの潜在性をアピール。また、「国際メディカルコーディネート事業者協議会(JIMCA)」も出展し、医療を目的とする訪日外国人のコーディネートに関する情報を提供した。
観光DX、多くの初出展、新サービスから課題解決まで
観光DX・マーケティングEXPOでも、テーマごとにゾーンを設定。宿泊DXフェアでは、昨年に引き続き宿泊施設向けクラウドサービスを展開する「陣屋コネクト」やサウナを中心とした地域活性・観光体験の提供を目的に独自開発した「卵型サウナ小屋」の製造・販売する「Barca」が初出展した。
観光DXフェアでは、タビナカDXプラットフォームを提供する「NutmegLabs Japan(ナツメグ)」、音声ガイドやデジタルスタンプラリーなど複数のプロダクトを展開する「MEBUKU」などが広いブースを展開したほか、高品質なドローンショーを企画・運営する「レッドクリフ」などエンタメ系事業者も出展した。
また、施設の高付加価値化ゾーンでは、宿泊施設にアート作品を提案する「画廊アートエミュウ」が初出展。このほか、顧客支援・マーケティングゾーンでは、宿泊施設に関するクチコミや評価をデータ収集・分析する「TrustYou」など、人手不足/インバウンド対策ゾーンでは、多言語化ソリューションを提供する「Wovn Technologies」、在留外国人に特化した求人媒体の「Guidable」など多彩な企業が事業を紹介した。
 「タイムズ24」も初出展。無人で運営可能な特設駐車場を1日単位で開設する新しい駐車場管理サービスを紹介
「タイムズ24」も初出展。無人で運営可能な特設駐車場を1日単位で開設する新しい駐車場管理サービスを紹介
 今年は新たな試みとしてスマートモビリティ試乗体験コーナーも設置。会場内で「eMoBi」の電動トゥクトゥク、「日信電子サービス」の4輪立ち乗り電動カートや追従型電動車いすの試乗機会が提供された
今年は新たな試みとしてスマートモビリティ試乗体験コーナーも設置。会場内で「eMoBi」の電動トゥクトゥク、「日信電子サービス」の4輪立ち乗り電動カートや追従型電動車いすの試乗機会が提供された
また、最終日には日本観光振興協会共催イベントとして交流会も実施。参加者を自治体、観光協会、DMOに限定し、情報交換や人脈づくりの機会を設けた。
なお、2026年は6月17日~19日にかけて、「ホスピタリティテックEXPO」とリニューアルして開催。宿泊・観光・飲食とAI・DX・ロボットなどのテクノロジーを組み合わせた展示会となる予定だ。






















 観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】
観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】