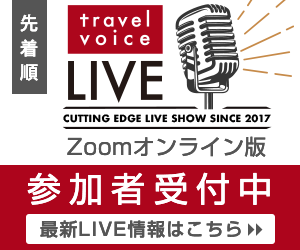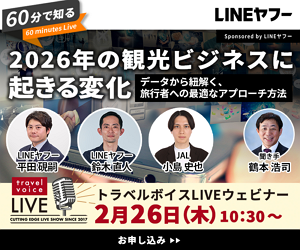政府が掲げる「2030年、訪日外国人6000万人」の目標の達成に向け、空港の役割が再び注目を集めている。なかでも、観光立国実現に不可欠なファクターとなりつつあるのが、観光地と直結する地方空港の機能強化と戦略的運用だ。
西村あさひ法律事務所と航空イノベーション推進協議会は2025年7月末に「航空シンポジウム」を開催。基調講演では、国交省・前航空局次長、現在は鉄道・運輸機構(JRTT)の副理事長を務める蔵持京治氏が登壇し「空港の国際化と観光振興の推進には、主要5〜6空港だけでは限界がある。地方空港の可能性を見極めた戦略が求められる」と語った。基調講演で語られた日本国内の空港の現状と今後をレポートする。
国内外の航空旅客は回復傾向、構造的課題は残る
コロナ禍からの回復により、航空輸送は着実に復調している。国内線は旅客数ベースでほぼコロナ前水準に戻り、国際線もおおむね同様の傾向を示している。ただし、蔵持氏は「構造的な変化がある」と指摘する。
最大の要因は、航空会社の収支構造における逆風だ。とりわけ国内線では、円安によるコスト高が直撃しており、燃料や整備費、空港使用料などの多くがドル建てであるため、経営を圧迫している。また、出張・業務利用といった高単価なビジネス旅客の減少により、収益性の確保が難しくなっている。
観光目的の旅客は、増加しているものの、価格感度が高く、ビジネス客ほどの収益性は見込めない。結果として、多くの国内路線は「乗っているが儲からない」状況に陥っている。さらに、訪日客の地方移動も新幹線など鉄道に流れがちで、国内線の活用が思うように進んでいないという実情もある。
 国交省・前航空局次長、現在は鉄道・運輸機構(JRTT)の副理事長を務める蔵持京治氏
国交省・前航空局次長、現在は鉄道・運輸機構(JRTT)の副理事長を務める蔵持京治氏
空港インフラは拡張中、6000万人の受け入れに備える
こうした課題を抱えつつも、日本の主要空港はインフラの拡充を着実に進めている。成田空港では2024年10月から年間発着枠を30万回から34万回に拡大し、3本目の滑走路も整備中だ。羽田空港では飛行経路の見直しを通じて発着回数を拡大し、首都圏として年間100万回の受け入れ体制を確保する。
関西国際空港でも大規模な飛行経路再編を実施し、発着枠を30万回に拡大。中部国際空港は24時間対応の滑走路メンテナンス対策として代替滑走路の整備に着手していて、福岡空港や新千歳空港、那覇空港でも滑走路増設や受け入れ能力拡大が進められている。
これらの整備により、物理的には6000万人のインバウンド需要に応えるキャパシティは整いつつある。ただし、こうした拡張の中心は、依然として首都圏・関西圏に集中しているのが現状だ。
蔵持氏は、「観光の国際化をさらに進めるには、地方空港が果たす役割がより重要になる」と強調。現在、日本の国際線旅客の約9割は、成田、羽田、関空、中部、福岡、新千歳の6空港で占められている。逆に言えば、それ以外の地方空港にはまだ大きな伸びしろが残されている。
実際には、多くの自治体が海外エアラインの誘致に向けてトップセールスを展開し、チャーター便から定期便化を狙う構図が繰り返されているが、その手法は知事によるトップセールスや補助金投入、経済界の動員など。蔵持氏は「それだけでは持続的な成果は得られない」と警鐘を鳴らす。
空港運用の現場課題にも目を向けるべき
海外エアラインの就航を実現するには、単に「飛ばしたい」という思いだけでなく、実際に空港が受け入れ可能かどうかの実務的なチェックも不可欠だ。グランドハンドリング体制や燃料供給設備、CIQ(税関・出入国・検疫)体制の有無など、いわゆる地上支援体制の充実が前提条件となる。
「実際には、こうした準備が不十分なまま誘致活動を進め、運航開始後にトラブルが生じるケースも少なくない」と蔵持氏。路線維持に不可欠な搭乗率の確保においても、インバウンド任せでは難しく、地元住民によるアウトバウンド利用の促進も含めた地域一体の戦略が必要となる。
空港を経営する時代、コンセッション活用も視野に
地方空港の真価が問われる今、求められているのは施設整備以上に「経営的視点」。空港を単なる交通インフラではなく、地域経済を支える事業体として捉え直す発想だ。
その一例が、コンセッション(運営権)による民間主導型の空港経営だ。空港ビルや駐車場、物販施設など非航空収入の確保を図り、航空旅客の増減に左右されない経営体制を構築する動きは徐々に広がりを見せている。
蔵持氏は「地域の観光振興・経済活性化と一体となった空港経営が、これからの地方空港に求められる」と指摘する。単なる路線誘致ではなく、空港そのものの価値を高め、観光の“入り口”として機能させる戦略が不可欠となっている。
講演の最後に、蔵持氏は地域空港や自治体の関係者に向け、「まずは自分たちの強みを知ることが出発点。隣の県が国際線を呼んだから自分たちも、という発想では戦略にならない。エアラインは冷静に収益性を見て就航を判断している。地域側もそのロジックを理解したうえで、地元の資源・需要・連携体制を冷静に分析すべき」と訴えた。
インバウンド6000万人の実現には、“闇雲な誘致合戦”ではなく、“地域主導の戦略的空港経営”がカギを握る。蔵持氏は、地に足の着いた整備とマーケティング、地元利用の促進、そして持続可能な運航支援体制が揃って初めて、地方空港は真の「国際観光拠点」として機能すると力を込めた。
トラベルボイス代表 鶴本浩司






















 観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】
観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】